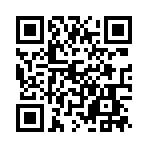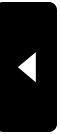2019年03月25日
開花宣言
そのたびにおおまかなことを答えながら、「下の桜が咲いたらブログで発表します」と答えていました。
興徳寺の桜の主役=駐車場の桜は、石段下の桜が咲いてから4~5日で開花となるからです。
ところが今年、昨年より3日早く 3月19日に開花したのですが、ちょうどお葬式と重なって、ブログの更新ができませんでした。
待っていて下さった方々にお詫び申し上げます。

下の桜は満開です。


石段下からの光景は伐採した分寂しくなりましたが、残した木がけなげに花を咲かしてくれています。


上の段(駐車場)の標準木が昨日チラホラと咲き始めたので、今年の「開花宣言」とします。

全体的にはまだこんな感じです。



今週末から来週半ばまでが、見ごろかと思われます。
どうぞお出かけください。
なおカメラマンの方は、どうぞマナーを守ってください。
植え込みの中には入らないよう、昨年踏みにじられた水仙が今年は開花してくれません。
また、せっかくお寺に来られるのですから、まずは本堂にお参りしてから・・・

今年植えた しだれ桜、30年経ったら、いい写真になるでしょう。
3月1日に開始した「彼岸のお経廻り」がようやく本日終了しました。
この間に、お葬式が2回、卒業式への参加や横浜での書道展覧会、「彼岸の法要」とそのための卒塔婆書きもありましたが、それにしても200軒足らずのお檀家さんに25日間は初めてのことです。

友人の唐津焼の窯元 岸田匡啓さんがやっと納得できるものができたからと送ってくれた 花立て、です。
2019年02月16日
100年後の期待

富士宮市小泉の立川恒春氏の作品で、平成5年の4月と記されています。
何かのコンテストで入賞し、それをきっかけに多くのカメラマンが訪れるようになったみたいです。
(”興徳寺のしだれ桜” と呼ばれるのは、この木のことですが上の方に伸びていた枝は20年ほど前に落ち、このような写真はもう撮れなくなっていました)
実はこの興徳寺のシンボルともいえる推定樹齢200年余の「古木」を伐採しました。
石段の脇にそびえる4本の古木のうち、下からの3本が内部の空洞化(洞)が進み、倒壊あるいは枝が落下して人身事故につながる恐れもでてきたため、まさに≪断腸の思い≫で決断しました。
――今まで多くの人を楽しませてくれた、もう見ることのできない桜たちを紹介します――

この4本のうち、下から1番目と3番目を伐採、2番目は張り出した枝を撤去しました。


これは下から見たところ、この大木ももうありません。

4本の桜を横から見る。1番上の木だけは残っています。

一番下の桜を横から

有名になった件の「しだれ桜」は上の枝はありませんが、まだまだ見栄えがします。

推定樹齢200年以上、の根拠がこの石碑。
石段が出来た時に建立されたもので、「天明元年」の文字が刻まれています。
天明元年は1781年、今から238年前でこれらの桜もその頃植えられた、と推察する所以です。
せめて皆にお知らせをして、今年の花を楽しんでもらったあとに伐採することも考えたのですが、花見客あるいは花まつりの客に落下のリスクもあり、それより新しい桜を植えることを早くしたいとの思いで、今回の決断に至ったわけです(桜の植樹は冬と決まっているので)。

幹には大きな洞(うろ)、近所の90歳になる長老が子どもの頃、この洞に鳥が巣を作っていたとのこと、その頃にすでに100年は越えていたのだろうと裏付ける証言でもあります。

伐採前のセレモニー

3本の木に 注連縄(しめなわ)、お経をあげて、たっぷりのお神酒を注いで・・・

一番下の木

二番目の木

三番目の木(しだれ桜)
〈伐採〉

2台のクレーン車を使って・・・


空洞が幹を貫いていた

〈植樹〉
新しい木を植えるにあたり、植木屋さんにお願いしたのは ただ一つ。
「100年後に価値の出る桜を選んでください!」
先人が遺し、代々受け継がれてきた大切な宝を私の代で終わりにしてしまった・・・
その忸怩(じくじ)たる思いを、せめて100年後に伝えたい、と思います。
望月造園の社長さんが 「はい分かりました」 と請け負ってくれました。

新しく植えた木、高さ6m、幹の周囲が50cm、15年ほどの八重の枝垂れ桜です。

100年後が楽しみです。


2月も半ば、そろそろ「興徳寺便り」を始めて、お彼岸の卒塔婆を書いて、「花まつり」の準備、
3月に入ったら「彼岸のお経廻り」が始まります。
2月は28日しかないので、もたもたしていられません。
2019年01月22日
七面山へ
私達にとっては、信仰の聖地、「七面山=敬慎院」です。
毎年、誕生日に『七面山』に登るようになって、10年が過ぎました。
今年は、当日どうしても外せない用があって 16日に。
朝4時過ぎに出発し、登山口に6時、真っ暗な中をヘッドライトの灯を頼りに登り始めました。
日頃の運動不足がたたって、足は上がらず、息は切れる・・・
ようやく明るくなってきたころ 13丁目「肝心坊」に到着、まずはお経をあげて、それから休憩します。


「肝心坊」の休憩所、このような休憩所が2丁目、13丁目、36丁目、46丁目と計4ケ所あります。
ちなみに、登山口から「敬慎院」までは、距離で50丁、1丁は長さの単位で60間、約109mなので、計5,5kmということになります。
何だそんなもんか、と思いますが 標高差が1200mあり、平らな所はなく常に登りつづけなければならないので、そう簡単ではありません。

いつもいつも感心するのですが、このような立派な参道を常に整備してくれている人がいるってこと、
私も山と関わっているのでよく分かるのですが、山道をきちっと整備するというのは、大変な手間と労力を必要とします。
必要な材料と道具を担って、そこまで歩いて行って、作業をするのですから・・・
歩くだけなのに、ツライだとか苦シイだとか、口が裂けても言えません。

昨年秋の台風で木が倒れ、電柱も倒されました。 復旧まで時間もかかりそうです。
今年は暖冬の影響か雪が少なく、楽と言えば楽ですが、ちょっと物足りない、

いつもはこんな感じです(昨年も雪が少なく、これは2年前)

苦しい登山道ですが、要所要所に立て札があって、その言葉に励まされます。
私のお気に入りは これ!

「何度でも 初心に戻れる 七面山」
私にとっての初心とは、あの坊さんになり立ての頃のミズミズシイ心、これを思い出すためにここに来ているんだ、と納得します。
そして今回の気づき!

「妙とは蘇生の義なり蘇生と申すは甦る義なり」
途中途中に小さな休憩所があって、そこに日蓮聖人の言葉が。
「南無妙法蓮華経」の「妙」という文字に「甦る」という意味が込められている、仏に成れる可能性を秘めているということですが・・・
この苦しい旅を終えた時に「私は甦る!」と、自分を励ましました。

46歳の時です。 ブラジルで事業を始めてすぐにつまづき、大きな負債を抱えました。
悶々とした日々、のたうち回っているような状況の中で、ある閃きを得ました。
「人生ここからスタート!」
何の根拠もありませんが、自分は甦る、と強く思いました。
それまでの人生が準備期間でここが折り返し、ならば92歳まで生きる!
状態が一気に好転したわけではありませんが、精神的にはとても楽になって今に至ります。

動物の足跡も楽しみ
46丁目の「和光門」まで来ると、もう境内。 嬉しさと安堵感、至福の時です。

49丁目の「随身門」

春分の日、秋分の日、富士山頂を通過した太陽光が、この門をくぐり本堂の奥に鎮座する「七面大明神」に到達する
驚くことにその光の線はさらに西に進んで、なんと出雲大社に達するのだそうです。

「敬慎院」
この山中にこれだけの建物をよくぞ建てたもの。


雪も少なく、気温もマイナス5℃と楽(?)でした。(冷え込むとマイナス20℃になるそうです)

ここまでの所要時間、4時間。 かつては3時間を切ってどこまでタイムを縮められるかに挑戦していたこともありましたが、今はここまで来られただけで嬉しい。 ただ感謝です。

「大やかん」のある囲炉裏で休憩。
お堂の中は撮影禁止なので紹介できませんが、「七面大明神」にお目通りし、私が気にかけている何名かの方の病気の平癒を祈願していただき、お経をあげて、帰路につきました。

「甦った」 けれど足が痛い・・・
1昨日(20日)から『寒行』がスタートしました。 お近くの方、是非参加してください。
興徳寺出発は23~25日、2月3日、お隣の妙泉寺での「節分」で終了です。
2019年01月05日
年のはじめの

平成最後の・・・という言い方がよくされますが、昭和~平成に変わった時、ブラジルに住んでいたので、元号が変わるということがどのような感じなのかよく分かりません。 ただ新しい元号になると2世代前の人=私たちから見た明治生まれ、になってしまうのか、などと漠然と・・・
同級生からの年賀状は 「いよいよ古希ですね~」、
そんな年を迎えました。 数えの70歳です。

12月は、とうとうブログを更新できませんでした。 初めてのことです。

12/1 からお檀家さんを廻り始めました。 何事もなければ15日間くらいですが、今回は法事その他もろもろの行事が挟まっていて、22日頃の終了予定でした。
ところが15日に檀家さんの訃報が入り、27日までにナント5件、最後のお葬式が終わって、納骨を済ませたのが30日の夜6時でした。
当然のことのようにお檀家さん廻りも遅れに遅れ、結局、まともなお掃除もできないままに大晦日を迎えてしまいました。
こんなことも初めてです。
『除夜の唱題行』

31日の23時半から 新年の0時半まで、瞑想と唱題(お題目を唱える)で過ごします。

和蝋燭の灯が幻想的です。
今年は参加者が少なくて、私を含めて7名でしたが、真剣に取り組みました。
そして終わった後は恒例の挽き立てコーヒーとパネトーネ(ブラジルでクリスマスに食べる定番のお菓子)で新年を祝いました。
皆が帰って、寝たのが2時頃、1年に一度の夜更かしです。

(1日は地平線が雲に覆われ、2日の日の出。 景色に変わりはないのに感動もイマイチ、不思議ですね~)
『元旦会』
元旦会(がんたんえ)、1月2日10時よりの恒例行事、

子ども連れで来て下さる方も多く、嬉しい限りです。

お正月なので 「法話」は趣向を変えて、日本昔話 を・・・
パーカッションを駆使して(?)の一人舞台、衣の袖が邪魔になることに初めて気づきました。
最後に皆で歌を唄いました。
「♪年のはじめのためしとて・・・」
この「年のはじめ」、という言葉、漢字で書くと、初め? それとも始め?
初め、かな~と何となく思っていましたが、「年末・年始」という言葉にぶつかって、????・・・
初め・始め、どちらも正解のような気もしますが、よくわからないので 平仮名にしました。

法要の後は、これも恒例の「特製お汁粉」と「甘酒」。 お汁粉の餡は友人の和菓子屋さんが毎年贈ってくれます。
「オイシイわけだ~」 と皆さんが・・・

この法要が終わるとやっと私のお正月。



うらうらとした陽だまりに、お餅やらシイタケなどを焼いていただきました。

あれから3日、何をしていたわけでもなく、ほとんど外にも出ず、日が過ぎました。
12月は寝るとき以外は法衣(坊さんの着物)を脱ぐことがありませんでした。 家の中を小走りで移動していました。
体の調子を崩すこともなく、よく持った、と思います。
でも何をすることもなく時間が過ぎる、ということを改めて実感しています。

本日をもってお正月はオシマイ。
2018年11月28日
お会式~植樹祭~団参
11月11日、『お会式』 宗祖日蓮大聖人の遺徳を偲び、御恩に感謝するための法要。
ご命日(10/13)の頃に行われますが、
興徳寺は 11月の第2日曜日です。


昨年は 落慶法要を兼ねていたので、改修後初めての「お会式」となりました。
僧侶7名、檀家さんが80名座ってまだ充分に余裕があり、改めて「ヨカッタ」です。

毎年、他寺院の僧侶に「法話」をお願いしておりますが、今年は埼玉県越谷市「源妙寺」住職、渡邊源昇上人。
長崎のサラリーマンの家庭に生まれ、縁があって出家し、このたび一からお寺を建立されました。
三年前、ある勉強会でお話を伺い、感動し、ラブコール(?)を送りました。
その心意気、情熱、求道者としての生き方にさらに感動し、来年は団参で皆で訪れることを決めました。
植樹祭
11月15日、地元の小学生と一緒に木を植える「植樹祭」も今年で第8回となりました。
参加者は小学生112名(3~6年生)+先生8名+スタッフ50名=120名でした。

山道を登る


下に見えるのが柚野(ゆの)小学校


閉会式で校長先生が挨拶

子どもたちが植えた木に自分の名札をつける。 大きくなって再会してください。

この子の胸のハートマーク、なんと「ひっつきムシ」、子どもはこういうところがオモシロイ。
団参
団参=団体でお寺に参詣すること。 興徳寺でこのバスツアーを始めて今年で5年目となりました。 お会式の終わった11月の第2金曜日~土曜日と決めています。 今回は 身延山本山での「輪番奉仕」、これは法主猊下(ほっすげいか)に代わって、お勤めをすることですが、興徳寺は8年ぶりのことでした。

担当のお坊さんに シャッターを押してもらったのですが「ハイ、チーズ!」 というあの場面で 自分の坊主頭を指さし「はい、ボーズッ!」
皆で大笑いでした。
広い本山の中を案内してもらい

法話も聴聞し、食事の後は門前町をブラブラ・・・

西山温泉「慶雲館」へ



翌朝、出発前に河原で写真を撮っていた時のこと、岩の下にフカフカの落ち葉が溜まっていたので、思わず飛び降りてみたら「ズボッ!」、何とその下を水が流れていました。
皆に笑われましたが、自分でも可笑しかった・・・ 実際には足が冷たくて困った・・・
バスの見送りに出ていた中居さんが、すぐに備え付けの使い捨ての足袋を持ってきてくれました。 助かりました。
昇仙峡
富士宮市あたりに住んでいる人は一度は行ったことがある観光地ですが、私も18歳の時、アルバイトしていた会社の慰安旅行で連れて行ったもらったことがあります。それにしても50年前のこと、他の方たちも皆似たり寄ったりの体験で、「ヘ~ッ、こんなイイトコだったけ~」などと、口々に・・・

紅葉を楽しみながら、川沿いの道を3,5km歩きました。



若い方は40歳、上は86歳、運転手さんもガイドさんもお檀家さんという気心知れたお仲間で、終始笑いの絶えない楽しい旅でした。

11月も もう終わりです。

いよいよ師走!
12月1日からは暮れのお経廻りが始まります。 今回は期間中にいろいろな予定が入っていて、廻り終わるのは12月22~23日頃になりそうです。
またバタバタとお正月を迎えることになるのでしょうね。
2018年11月05日
母のこと
毎年、同じお店で家族でお誕生日会を開きます。




92才であることは全然理解できず、 「そんなになるわけないじゃん」 と言いますが、
「じゃ何才?」 と問えば
「70才? 80にはなんないよね~・・・ なった~?」

冷蔵庫に張り付けたボードを見て、ケラケラ笑いながら 「そんなになった~? そろそろ逝かなくっちゃね~」
「いつ逝く~? 明日?」
「明日じゃ早いね~ もうちょっと置いてちょうだい」

朝のお勤めが終わると、母を起こします。 朝いちばんで、とにかく笑わせます。
母の横に潜り込んで 「オカアチャン、オハヨウゴザイマ~ス、朝になりました~」
「おはようございます」
「では 朝の歌を唄いましょ~! ♪ あ~さは ど~こからく来る~かしら~ あ~の山越えて、く~も越えて~・・・」
母も一緒に歌いだし、歌い終わると 「あっちの方でも歌ってるね~」 と遠くを指さしニコニコと・・・
母にはいつも歌が聴こえているらしいのです。

着替えは、まず靴下から・・・
部屋の端で靴下を持った私が立つと、母は足を斜めに差し出します。 それを目掛けて一気に突進、一瞬でかぶせます。 続いて一気にパジャマのズボンを脱がし、闘牛士よろしくズボンをヒラヒラさせると、今度は両足を差し出す。 そこへ一気に・・・
上着は片手を差し入れて手首が出たら”握手!” 首が出たら おでことおでこをコッツン!
おもしろいので孫に見せてやろうと、連れてきたら、さすがにやりませんでした。

母の部屋、ベッドから降りて 手すりに捕まるとそこがトイレのドア、一人でできます。 ベッドの反対側にフトンを敷いて 私が寝ています。

母は毎朝、梅干しに砂糖をまぶして食べます。 母の父親(私の祖父)の習慣でした。

「おかあちゃん、僕かわいい?」
「ウ~ン、ムカシは可愛かったね~」
「今は?」
「だって~ カワイイなんて歳じゃないじゃん」
「オカアチャン、子どもはいくつになってもカワイイもんだってよく言うよ~」

次の日、
「おかあちゃん、ムカシは僕、かわいかった~?」
「今でもかわいいよ~ わが子はいくつになっても かわいいもんだよ~」

母が「認知症」と診断されたのが 平成21年1月のこと、もうじき10年になります。
その時、「要介護2」と認定されましたが、いまだに「要介護2」のままです。 身体能力の衰えは若干あるものの、認知症そのものはまったく進んでいないように思えます。
たしかに、いまのことはすぐ忘れます。 あの誕生日の食事会だって、お店を出て車に乗ったら、もう思い出せません。 それは見事なもの。
だけど、認知症だから、何を言ってもムダ、ということはない。 もちろん人によって差はありますが、学習能力も0ではない。
毎年、妹たちと 「今年で最後かもしれないから」 と食事会に出かけるのですが、今回は誰もそんなことを言いませんでした。
来年もまたある、ってことを皆が信じていたみたい。

11月3~4日は 鈴鹿サーキットで バイクのレース「全日本ロードレース」が開催、観戦するべく、2ケ月前にはチケット・ホテルの手配を済ませ、新しいバイクの初ツーリングをウキウキ・ワクワクと心待ちしていたのですが、葬儀にて断念! よくあることです。
今度の日曜日が「お会式」、その週末が、お檀家さんとの「バス旅行」、 すぐに「興徳寺便り」に着手して、発送したらもう暮れの「お経参り」です。
年賀はがきも届いたし、師走まで秒読み段階です。
2018年10月29日
孫と過ごした日
オーストラリア・メルボルンに住んでいる長男家族が、9月末にやってきて2週間滞在しました。
2年ぶりでしたが、孫たちもそれぞれ大きくなって・・・

慎悟が3才9ケ月、慧美は2歳と3ケ月です。

日本語は話せませんが 「松永慧美さ~ん!」と呼んだら 「ハ~イ!」と応えるよう 躾け(?)ました。

富士宮の浅間神社へ。



本堂で。

嫁のアリソンは元体操選手だったらしい。


息子夫婦は 子どもに対して怒るということがほとんどない。
それは二人の性格によるものだと思うけど、とてもいいことと思えます。
子どもたちも落ち着いていて、大きな声でわめいたり、長泣きすることもありません。
でも食事の時など、じっと座って食べ続けることができない。
「どうしたらいいんだろう?」と相談を受けました。
「ファミリーMatsunaga のルールは作ったらいい」 とアドバイス。
だめなことはダメ! これをきちっと決めてぶれないこと、
「なぜ?」 と聞かれたら 「これは我が家のルール」 と答える。
皇太子が生まれた時、天皇夫妻(当時の皇太子夫妻)は 『なるちゃん憲法』 なるものを作ったそうです。 なるちゃんは徳仁(なるひと)親王の幼少時のニックネームです。 憲法の内容は知りませんが、その中に 「転んでもだれも起こさないこと」という一項があったそうです。 なぜそこだけ知っているかというと 私の父親が 「そんなこと俺もやっていた」 と言ったからです。
私が小さかったころ、転んで泣いているのを近所のおばさんが抱き起そうとした時、「自分で起き上がるまで放っておいてください」 と言ったそう。 「ひどい親だと言われたけど」 と・・・
私も子どもたちを育てるとき、そのようにしました。
ルールは成長に合わせて変えていけばいいけど、「子どもを自立させるために何が必要か?」 が 基本だと思います。



別れの日が「お葬式」と重なってしまいました。 久しぶりの親子3人、です。

バリ島に1週間、日本で2週間、帰りがけにバリ島の別の場所でもう1週間だそう、 よく動くこと。
1ケ月のバカンスなので楽しみたいのだそうです。

母のことを書きたかったけど次回で。
2018年09月25日
彼岸花の頃
2ケ月ちょっとの期間ですが、今年は特に異常な暑さもあり、なかなかハードではありましたが体調を崩すことなく乗り切ることができたこと、感謝!です。

9月23日、 『彼岸法要』、60名ほどの方が参列してくださいました。

彼岸は岸の彼方、と書きますが、じゃあ岸の彼方に何がある? 仏さまの世界がある。
私たち仏教徒の目的は皆で彼岸に渡ること、そのための修行をするための1週間、それが「お彼岸」という行事です。
彼岸に渡るということは悟るということ、つまりは仏になること。 ですが、それについてお釈迦様は明解な説明をされませんでした。
それは誰も見たことも聞いたこともないことを言葉で説明するのは不可能だと考えたからです。
見たことも聞いたこともないことを言葉で伝えることの困難さの例として、1月前ブラジルで研修していた弟子に、パンデイロ(ブラジルのタンバリン)に塗るワックスを買ってくれるようメールで依頼した話をしました。
「パンデイロのロールに使うワックスを買ってください」という文が彼はすぐに理解できませんでした。
檀家さんにパンデイロを見てもらい、ついでワックスを塗って、ロールという奏法も披露しました。
ついでに、弟子・泰潤にこのパンデイロを使ってブラジルの歌を唄ってもらいました。(なかなかイイ感じです)

最後に母に登場してもらいました。 認知症の会話は、ほのぼのと、そしてとっても楽しい・・・ 檀家さんもとても喜んでくれます。

『彼岸花』
天候不順にも惑わされず、今年も「彼岸花」がきっちりと咲いてくれました。 それはそれは見事です。
連日、見物客や写真愛好家で賑わっています。
小雨降る中、 小学生が来てくれました。

某旅行社が大型バスを仕立てて毎日来ます。 その数、1台~5台/日、送られてきたFAXでは 9月16日~30日までで、計41台、他にも関西方面からのツアーもあり、50台近いのかもしれません。 彼岸のお経廻りの最中でもあり、直接のアテンドはほとんどできませんでしたが、せっかく来てくれるなら、喜んで頂きたいと思うし、そのためのしっかりした打ち合わせはして欲しかった、と思いました。

それにしても、期間中、天気はいまひとつパッとせず、富士山は見えず、曇り~時々雨、の毎日でした。

興徳寺の彼岸花、下から紹介します。
①入口の辺り、右側が第2駐車場、左の坂を上って行くと、第1駐車場です。 右側の坂は本堂の裏手に出ます。

②石段の始まり。

③石段の途中

④第1駐車場から

⑤本堂前の広場には 色の異なる彼岸花(白・ピンク・黄色等々・・・)を植えてあります。 賛否両論? 観光客には概ね好評?


⑥石段の上から

⑦右側の土手

⑧左側の土手

毎年、花の数が増えています。
前にも書いたかもしれませんが、 市川さんという横浜から村に移住されてきた方が、毎年植え続け、管理もしてくれて、数年。
本当にありがたいことです。

この土手は イノシシに荒らされ、花も 疎ら(まばら)。 市川さんもすっかり落胆、今後についてはしばらく様子見です。
やっと晴れ間が出て(9月24日) 母に「彼岸花」を楽しんでもらいました。


「ワー キレイ~~!」と喜んでくれるのですが、部屋に着くとすべてを忘れてしまいます。
そんなとき、すかさずこの写真をプリントして見せます。
「これが動かぬ証拠~~!」
「認めざるを得ません、訂正します~~」
オモシロイですね。

*週末はオーストラリアの長男家族がやって来ます。 孫と会うのは楽しみですが、日本語は全然わからないらしい。
得意のボディーランゲージ(body language)が、どれだけ通用するかが試されるときです。
2018年08月29日
伝統の灯、今年も
私が子どものころも参加していた伝統行事ですが、そのころはそれぞれが家で作った「タイマツ」を持って夕方興徳寺に集まり、火をつけてもらったらパチパチと火の粉をまき散らしながら川まで運び、橋の上から川に投げ込んでオシマイ、という行事でした。
ブラジルから戻ってきたときこの行事が地元の子供会によって継続されていたことに感激し、友人たちの協力を得て「流しソーメン」から始まる一日行事になったのが平成20年、今年が11回目ということになります。
発足当時から手伝ってくれているスタッフもそれぞれに10歳年齢を重ね、炎天下での準備(2日間)~本番(朝9時から夜8時まで)~翌日の片づけ・・・ という労働がだんだん負担になってきています。
その対策として、今年は募集人員を80名にし(例年は100名)、流しソーメンはプラスチックの樋を購入しました。

プラスチックは軽いので 途中の支えをこまめに入れなければなりません。 息子の泰潤が工夫してくれました。
週間天気予報では雨の予想でしたが、前々日に 曇り に変わりました。
申込者82名、スタッフ42名、 前日夜半まで班編成や名札作りに追われました。
《8月16日 当日》
9:00 スタッフ集合

10:30 受付開始

11:00 開会式

開会式の後は それぞれが 竹のカップと箸を作る

初めてナイフを使うという子もいます
12:00 流しソーメン

スタートは実行委員長の叩くドラが合図

ミニトマト、ブルーベリー、飴なども流れてきます。

13:00 タイマツ製作~かき氷~ポン菓子~ゲーム

班ごとに別れ、それぞれがタイマツを作る。



ソーメンもかき氷もポン菓子も自作カップと箸で

15:00 スイカ割


全員が1回挑戦するが 割れてしまったチームはフウセンで代行して 終了後、皆でいただく
16:30 施餓鬼法要

全員が本堂で法要に参加する。
「流しソーメンもスイカ割もみんなオマケ、これからが本番です」

全員が作法に則ってお焼香

法要の灯をいただいて タイマツに点火する。
18:00 タイマツ行列



18:30 投入



芝川(しばかわ)の河原で読経の中、タイマツを投入し焚き上げる。

19:00 閉会式

お寺に戻って「閉会式」、迎えに来てくれた保護者に子供たちをお返しし、長かった一日のオシマイです。
そのあとのスタッフの打ち上げでお互いのガンバリを称え、大いに盛り上がるはずなのですが、皆すっかりくたびれてしまって、ボソボソとお話をして、以前は「え~ 宴たけなわではございますが、このあたりで一応中締めということに・・・」などと言っていたのが、誰ともなく「そろそろ終わりにしましょうか~」「あ~そうだね~」なんてフンイキに変わってきました。
「お疲れ様」などという月並みな言葉では言い尽くせませんが、スタッフの皆さま、本当にありがとうございました。
昨夜、反省会があったのですが、伝統の灯を守りつつ、どう継続していくか?が重要課題となりました。

川施餓鬼が終わって、片付けの後すぐに「興徳寺便り」の編集にとりかかり、27日に発送、それからは毎日草刈りです。
「彼岸花」の芽が出る前にすべての草刈りを終えなければなりません。
ありがたいことに 市川建男さんというお仲間が毎日来て、暑い中 黙々と草刈りをしてくれています。
定年後、横浜から移り住み数年前「何かをさせてください」と申し出て以来ずっと 興徳寺の斜面に彼岸花を植え続けてくれているお方です。
本当にありがたいことです。
9月20日頃から見ごろを迎えることと思います。 皆さまどうぞ見学に来てください。
いよいよ明後日からは、お彼岸のお経廻り、 日中は檀家さんを廻り、夜は塔婆書きというハードな日々が始まります。
2018年07月20日
暑さの夏
朝の本堂〈6:00〉で28~29℃です。 こんな暑い年あったかな~?と思います。
本堂の花がすぐ枯れる、 鉢植えの蓮が水が蒸発して枯れてしまった、 湿気が多くて畳にカビが、 暑すぎて蚊がいない(唯一いいことかな?)、
ガマンできずにとうとうエアコンを入れてしまった・・・
(エアコンなんてまったくぜいたくなものだと思っていたのですが、私の部屋は周りを部屋に囲まれていて風が入らず、おまけに明りを取るための天窓があるため日中は日光が差し込む)

先週の土曜日は「YUNOどんぐりの会」の作業日でした。 草刈り機を使って山の斜面の草を刈るのですが、2時間やったらもうクラクラ、 小休止の後、誰からともなく「終わりにするか~」、
ホッとしました。
このあたりの方言で「じちが無い」という言い方があります。「根性がない」という意味ですが、じち(根性)などと言ってられません。

【年輪の会】
6月の末、いつものお仲間と旅行へ。 今回は大阪のお菓子屋さん 岡田さんの工場を訪問し、夜は有馬温泉、というコースです。

(岡田さん、大阪の人気みやげ「プチバナナ」などを製造販売する「㈱瓢月堂」の社長さん)
沖縄~茨城県、計9名が新大阪駅に集合、グループ名を『年輪の会』といい私がほぼ最年少で上は85才です。
毎年2回、1~2泊の旅行を通して、年輪を重ねています。

近代的で清潔な工場を見学させていただきました。


《有馬温泉グランドホテル》
旅行の楽しみというと、見たことないもの見たり、オイシイもの食べたり、新しい体験をしたり、と色々あるのでしょうが、我々は一緒にいてよくおしゃべりをして、よく笑って・・ということがメインみたい。
必然、「ミーティング」が多くなります。

夜のミーティング

朝のミーティング
このメンバーは皆「日本を美しくする会」という お掃除の実践を通して環境も人の心もキレイにしましょう、という会の会員です。
私はブラジル時代、「ブラジルを美しくする会」を立ち上げた時の発起人の一人、メンバーのほとんどがブラジルに来てくれて、以来のお友達です。

旅館に泊まっても、起きたらすぐにフトンを畳む。 従業員の方たちの負担をできるだけ減らしたい、というやさしい方たちです。
どこにも出歩かず、「有馬温泉」って何も無い所だと思って帰ってきたら、ちゃんと(?)温泉街もあるんだとか・・失礼しました!
翌日は三田市永澤寺の「しょうぶ園」へ、



今回も人生の先輩たちと、よい時間を過ごさせていただきました。
【バイク】
バイクを買い換えました。
10年、7万キロ近く乗って、時々エンジンがかからない、というトラブルが発生するようになり、原因もいまひとつ特定できず(バイク屋に持っていくとかかってしまうので・・・)
「もうそろそろ限界?」という思いは医者がよく使う「加齢」にも似て、「仕方ないか」という心境になりました。
何といっても出先でエンジンがかからないというのはとても困る。
お別れの日、記念撮影をしました。
よく働いてくれた、と感無量!
下取りしてもらえると思ったら、「廃車!」だそう。 思わずポロリ・・・


新しいバイク、ヤマハの XMAX

シートが前のバイクより9cmも高くて「どうかな?」と思ったのですが、慣れたらとても乗りやすいバイクで満足です。
友人のゆかりさんが イラストを描いてくれました。

「花まつり」が終わって7月のお盆までが私のもっとも自由時間のとれる時ですが、
今年もやり残したこといくつか、
初夏の北海道に行きたいと毎年思うのですが、今年も断念。
【川施餓鬼】

「川施餓鬼」 、お子さん、お孫さんを参加させてください。
それから当日、あるいは前日、お手伝いしてくださる方がおりましたら、ぜひお願いいたします。

今月26日から お檀家さん廻り、8月16日が『川施餓鬼』
終わったらすぐに 秋のお彼岸の準備、1年でもっとも忙しい期間が始まります。