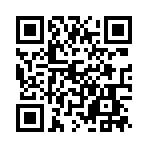2011年01月28日
ギフチョウ を 知ってますか?
”ギフチョウ” という名の 蝶 をご存知ですか?
ギフチョウ は 氷河期からの生き残りといわれている蝶で 明治時代 岐阜県で発見されたため 「ギフチョウ」と命名されたそう、 早春(当地では 3月下旬~4月末)の ほんのわずかな期間のみ出現し、その姿と舞いの美しさから ”春の女神”とも呼ばれています。


近年 蝶の生息できる環境の変化に伴い 個体数が激減しましたが 興徳寺の裏山の頂 桜峠 と呼ばれるあたりに わずかながら生息しています。 とくに この辺りの蝶は 個体の大きさ、色の鮮やかさにおいて 全国一 といわれているそうです。
この蝶を保護すべく 『芝川ギフチョウ保護の会』 が結成され、 平成11年より 活動を開始いたしました。 私も日本に戻ってきた 平成16年より メンバーに入れてもらいました。
主な 活動内容は 蝶の住む環境を整備すべく 毎月1回、周辺の森林の手入れ(間伐、下草刈り、また蝶の食 草である カンアオイや 蜜を吸う花である スミレやカタクリなどの植え付け)。 春のシーズン中は 捕獲を取り締まるためのパトロールや 蝶の観察 を行います。
毎月の例会は 日曜日に行われるため 私はお寺の行事と重なって ほとんど参加できませんが 今月は行くことができました。
「桜峠」。 整備中の 森林。


間伐 を 行いました。
針葉樹の植林は 最初 ”密植” といって 木と木の間隔を詰めて植えます。 そのことによって 木は真っ直ぐ伸び 下の方に枝がつきません。 そしてある程度 育ったところで 成長の悪い木を 間引きして 残った木を太くしてゆきます。 ところが この大事な 間伐 という作業をせずに 放置された林が 日本中に広がっています。 日中 日が入らず 草も生えていない 山です。
『ギフチョウ保護の会』では 山林の地主さんの許可を得て この 間伐作業を 行っているのです。 私は何もしておりませんが つくづくと 「えらいもんだな~」と思います。
間伐に よって 光 が 入るようになった山。

作業を終えて・・・ この日参加してくれたメンバー、 笑顔がとってもイイ

前列 左が 長谷川義教(よしのり)会長、 前列右が ミキオちゃん
そして この写真を 撮った背後に この富士山。

この山の 斜面に 地主の許可を得て 『ギフチョウ保護の会』 で 広葉樹 や 山桜 の苗を植えました。
そのまま 下に降りてゆくと 興徳寺の裏山に つながります。
興徳寺の すぐ裏から ここまでが 広葉樹でつながり、 境内を ギフチョウ が舞う!
それを見届けて 今回の 私の人生の the end としたい。
ささやかで そして 広大な夢 です。
相棒の ミキオちゃんと 「こうなったら 長生きしようぜ!」 と 言っております。
(このページ トップの 2枚の ギフチョウ の写真は ミキオちゃんから 借りました。 サスガッ!でしょ?)
ギフチョウ は 氷河期からの生き残りといわれている蝶で 明治時代 岐阜県で発見されたため 「ギフチョウ」と命名されたそう、 早春(当地では 3月下旬~4月末)の ほんのわずかな期間のみ出現し、その姿と舞いの美しさから ”春の女神”とも呼ばれています。


近年 蝶の生息できる環境の変化に伴い 個体数が激減しましたが 興徳寺の裏山の頂 桜峠 と呼ばれるあたりに わずかながら生息しています。 とくに この辺りの蝶は 個体の大きさ、色の鮮やかさにおいて 全国一 といわれているそうです。
この蝶を保護すべく 『芝川ギフチョウ保護の会』 が結成され、 平成11年より 活動を開始いたしました。 私も日本に戻ってきた 平成16年より メンバーに入れてもらいました。
主な 活動内容は 蝶の住む環境を整備すべく 毎月1回、周辺の森林の手入れ(間伐、下草刈り、また蝶の食 草である カンアオイや 蜜を吸う花である スミレやカタクリなどの植え付け)。 春のシーズン中は 捕獲を取り締まるためのパトロールや 蝶の観察 を行います。
毎月の例会は 日曜日に行われるため 私はお寺の行事と重なって ほとんど参加できませんが 今月は行くことができました。
「桜峠」。 整備中の 森林。


間伐 を 行いました。
針葉樹の植林は 最初 ”密植” といって 木と木の間隔を詰めて植えます。 そのことによって 木は真っ直ぐ伸び 下の方に枝がつきません。 そしてある程度 育ったところで 成長の悪い木を 間引きして 残った木を太くしてゆきます。 ところが この大事な 間伐 という作業をせずに 放置された林が 日本中に広がっています。 日中 日が入らず 草も生えていない 山です。
『ギフチョウ保護の会』では 山林の地主さんの許可を得て この 間伐作業を 行っているのです。 私は何もしておりませんが つくづくと 「えらいもんだな~」と思います。
間伐に よって 光 が 入るようになった山。

作業を終えて・・・ この日参加してくれたメンバー、 笑顔がとってもイイ

前列 左が 長谷川義教(よしのり)会長、 前列右が ミキオちゃん
そして この写真を 撮った背後に この富士山。

この山の 斜面に 地主の許可を得て 『ギフチョウ保護の会』 で 広葉樹 や 山桜 の苗を植えました。
そのまま 下に降りてゆくと 興徳寺の裏山に つながります。
興徳寺の すぐ裏から ここまでが 広葉樹でつながり、 境内を ギフチョウ が舞う!
それを見届けて 今回の 私の人生の the end としたい。
ささやかで そして 広大な夢 です。
相棒の ミキオちゃんと 「こうなったら 長生きしようぜ!」 と 言っております。
(このページ トップの 2枚の ギフチョウ の写真は ミキオちゃんから 借りました。 サスガッ!でしょ?)
Posted by kotokuji at
15:38
│Comments(0)
2011年01月25日
本堂からの富士山
興徳寺は 古いお寺で 境内のいたるところに 樹木がいっぱい。 永い事 手入れもされていなかったので、鬱蒼とした感じでありました。 マ、それはそれで 山寺の趣でもあったのですが、 やはり どこからでも 富士山が見える、ということが ここに来てくれた人への 何よりものご馳走ではないかと思い、 その目的に沿って 少しづつ整備をしてきました。
昨年より よい 造園業の方を紹介していただき 植木(梅や木蓮の古木等)を 移植してもらい おかげで本堂前が すっきりと広がりました。

こうなると 欲が出てきて 本堂から富士山が 見たい! と・・・
実は 杉と檜の大木が 邪魔をして 富士山が隠れてしまうのです。
(before)
全部で6本あるのですが 思い切って 右側の3本を倒す事に・・・

前日に ていねいに お経を あげて・・・
レッカー車を 使って 慎重に 伐ってゆきます。

無事、伐り終えました。
(大きな切り株)
かくして 本堂から 富士山が眺められるように なったのです。
(after)


倒した木は ステキなベンチ に生まれ変わりました。
キチッと手入れをします。
いつまでも 興徳寺を 見守って下さい。
今回の作業は 富士宮市北山の 望月造園さん にお願いいたしました。 私の 意向を簡単に伝えて すべてを お任せしたのですが 想像以上に よいものになりました。
プロ意識に徹しており 仕事ぶりを見るのが 毎日 楽しみでした。
ベンチも作っていただき 本当にありがとうございました。

寒行は 5日が終わって、 本日 興徳寺出発の 最終日、 おかげさまで 毎日20名を越す メンバーで 満天の星空の下 元気に歩いています。
お題目を 唱えてくださる方が 増えてくれていること、 何よりも 嬉しく思います。
残り10日間です。 1日でも参加してみたい と思われる方、 どうぞ ご連絡ください。
昨年より よい 造園業の方を紹介していただき 植木(梅や木蓮の古木等)を 移植してもらい おかげで本堂前が すっきりと広がりました。

こうなると 欲が出てきて 本堂から富士山が 見たい! と・・・
実は 杉と檜の大木が 邪魔をして 富士山が隠れてしまうのです。
(before)

全部で6本あるのですが 思い切って 右側の3本を倒す事に・・・

前日に ていねいに お経を あげて・・・
レッカー車を 使って 慎重に 伐ってゆきます。

無事、伐り終えました。
(大きな切り株)
かくして 本堂から 富士山が眺められるように なったのです。
(after)


倒した木は ステキなベンチ に生まれ変わりました。
キチッと手入れをします。
いつまでも 興徳寺を 見守って下さい。
今回の作業は 富士宮市北山の 望月造園さん にお願いいたしました。 私の 意向を簡単に伝えて すべてを お任せしたのですが 想像以上に よいものになりました。
プロ意識に徹しており 仕事ぶりを見るのが 毎日 楽しみでした。
ベンチも作っていただき 本当にありがとうございました。

寒行は 5日が終わって、 本日 興徳寺出発の 最終日、 おかげさまで 毎日20名を越す メンバーで 満天の星空の下 元気に歩いています。
お題目を 唱えてくださる方が 増えてくれていること、 何よりも 嬉しく思います。
残り10日間です。 1日でも参加してみたい と思われる方、 どうぞ ご連絡ください。
Posted by kotokuji at
10:14
│Comments(0)
2011年01月21日
寒行 始まる
昨日(1月20日)より 『寒行』が 始まりました。
寒行(正しくは寒修行)とは本来は寒中の30日間を、寺院・堂塔に詣で、水行・読経・書写・百度踏み等を行う修行のことです。
6年前、精進川・常境寺の金森上人、柚野地区の三澤寺・犬浦上人、妙泉寺・川手上人が大寒から寒明けまでの15日間、団扇太鼓を叩き、お題目を唱えながら、行脚する修行を計画され、興徳寺に戻ったばかりの私にもお誘いをいただき、初年度より参加させていただいております。 最初はお坊さんだけで、夜の道をお題目を唱えながらひたすら歩いておりましたが、その後、妙覚寺の乙部上人ご兄弟が参加してくださり、また檀信徒の中からの参加希望者も増え、今では毎晩10人から20人が、揃いの行衣(ぎょうえ=お題目を書き込んだ白装束)に身を包み、凍てつく夜の道を歩きます。
太鼓とお題目の音声とともに、すっかり村の冬の風物詩となりました。
興徳寺HPより
 昨夜は 妙覚寺からのスタートでしたが 近くの檀家さんたちが たくさん参加してくださり、毎年の常連さんたち と お坊さんが5人、総勢31名で 冬の道を 大きな声で 「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えながら 歩きました。
昨夜は 妙覚寺からのスタートでしたが 近くの檀家さんたちが たくさん参加してくださり、毎年の常連さんたち と お坊さんが5人、総勢31名で 冬の道を 大きな声で 「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えながら 歩きました。
満月に 富士山がくっきりと浮かび上がって それはそれは 美しかったです。
実際に歩いてみるとわかるのですが 寒くは ありません。
太鼓を叩きながら 大きな声を出しながら 歩く、からです。
「夜の道で大声あげられるチャンスなんて そうはないよネ~」
と 某女史(?)
「お正月で 緩んだ肉体をシェイプアップ!」
と 不純な(?)動機もありますが
私は
皆の心と 体が 「南無妙法蓮華経 〃 〃 」の中に溶け込む・・・
自然とひとつになった・・・
という感じが とっても好きです。
ダイナミックで 神秘的!
興味のある方 どうぞご参加ください。

平成23年 寒行予定
① 時間 ; 6時45分~本堂で読経 7時~スタート 8時~戻って、お茶 8時半~解散
② スタート ; 1月20日~22日=妙覚寺 23日~25日=興徳寺 26日~28日=三沢寺 29日~31日=妙泉寺 2月1日~3日=常境寺、 3日は 終了後 節分の豆まき を行います。
*興味ある方は 電話か メールで 問い合わせてください。

寒行(正しくは寒修行)とは本来は寒中の30日間を、寺院・堂塔に詣で、水行・読経・書写・百度踏み等を行う修行のことです。
6年前、精進川・常境寺の金森上人、柚野地区の三澤寺・犬浦上人、妙泉寺・川手上人が大寒から寒明けまでの15日間、団扇太鼓を叩き、お題目を唱えながら、行脚する修行を計画され、興徳寺に戻ったばかりの私にもお誘いをいただき、初年度より参加させていただいております。 最初はお坊さんだけで、夜の道をお題目を唱えながらひたすら歩いておりましたが、その後、妙覚寺の乙部上人ご兄弟が参加してくださり、また檀信徒の中からの参加希望者も増え、今では毎晩10人から20人が、揃いの行衣(ぎょうえ=お題目を書き込んだ白装束)に身を包み、凍てつく夜の道を歩きます。
太鼓とお題目の音声とともに、すっかり村の冬の風物詩となりました。
興徳寺HPより
 昨夜は 妙覚寺からのスタートでしたが 近くの檀家さんたちが たくさん参加してくださり、毎年の常連さんたち と お坊さんが5人、総勢31名で 冬の道を 大きな声で 「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えながら 歩きました。
昨夜は 妙覚寺からのスタートでしたが 近くの檀家さんたちが たくさん参加してくださり、毎年の常連さんたち と お坊さんが5人、総勢31名で 冬の道を 大きな声で 「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えながら 歩きました。満月に 富士山がくっきりと浮かび上がって それはそれは 美しかったです。
実際に歩いてみるとわかるのですが 寒くは ありません。
太鼓を叩きながら 大きな声を出しながら 歩く、からです。
「夜の道で大声あげられるチャンスなんて そうはないよネ~」
と 某女史(?)
「お正月で 緩んだ肉体をシェイプアップ!」
と 不純な(?)動機もありますが
私は
皆の心と 体が 「南無妙法蓮華経 〃 〃 」の中に溶け込む・・・
自然とひとつになった・・・
という感じが とっても好きです。
ダイナミックで 神秘的!
興味のある方 どうぞご参加ください。

平成23年 寒行予定
① 時間 ; 6時45分~本堂で読経 7時~スタート 8時~戻って、お茶 8時半~解散
② スタート ; 1月20日~22日=妙覚寺 23日~25日=興徳寺 26日~28日=三沢寺 29日~31日=妙泉寺 2月1日~3日=常境寺、 3日は 終了後 節分の豆まき を行います。
*興味ある方は 電話か メールで 問い合わせてください。

Posted by kotokuji at
14:05
│Comments(0)
2011年01月18日
趣味は?
「趣味は?」 と聞かれると 「ウーン・・・」 と 言うしかない 情けない私、
好きなことは いっぱいあるいけれど どれも 趣味のレベルに達しない・・・
それでも 唯一 続けていることといえば 必要に迫られて 町の書道教室に通い始めて もうじき6年、
昨年 やっと2段(漢字部門)になりました。 遅いペースではありますが 生来の悪筆、不器用、それに飽きっぽい性格の 私にしては よく続いているとも思えます。

私の通っている教室「恵舟書院」の 本部は横浜にあります。 『芳林書道院』といいます。
毎年 この時期に 全国の教室の生徒さんたちが出展して 「芳林書展」 という展覧会が 横浜の 神奈川県民ホールのギャラリーを借り切って 催されます。
会場内、たまたま お出会いした 美女たち

『芳林書道院』代表 水川舟芳先生の 今回の出展作品









私の先生、 西嶋恵舟先生 と 今回の 出展作品

今回、1ケ月以上 この作品と取り組んで
とても納得できる出来るものではないのですが・・・
「どこまでいっても 自分の作品に 満足できるなんてことは ないものよ」
と
先生は 慰めてくれた・・・
書道を始めたばかりのころ 本部の 月刊誌に 水川舟芳先生の インタビュー記事が連載されていました。
前略
聞き手 深く追求することが大事なんですね。
舟芳 若いときからいろんな趣味に手を広げていて、50,60になって書を初めても1週間に1回か2回、わずか30分か1時間筆をもつというのは、趣味とはいえないよね。 時間つぶしなわけ。
聞き手 時間つぶしですか。
舟芳 そういう人は、書というものの本当の面白さは感じないでしょう。 趣味ということは、趣がある、味わいがあるということなのね。 それこそ真剣勝負でやらないと趣があったり 味わいがあったりしない、 そういうのは趣味じゃなくて遊びなの。 趣味を取り違えちゃいけない、と思います。
後略
これを 読んだときは ショックでした。
「私の 趣味は~ 」などと 迂闊に言えない、 と思いました。
今、
せめて 「趣味は書道です」 と 言えるようになりたい、 と思います。

興徳寺 東屋(あずまや) 「富士見亭」より
好きなことは いっぱいあるいけれど どれも 趣味のレベルに達しない・・・
それでも 唯一 続けていることといえば 必要に迫られて 町の書道教室に通い始めて もうじき6年、
昨年 やっと2段(漢字部門)になりました。 遅いペースではありますが 生来の悪筆、不器用、それに飽きっぽい性格の 私にしては よく続いているとも思えます。

私の通っている教室「恵舟書院」の 本部は横浜にあります。 『芳林書道院』といいます。
毎年 この時期に 全国の教室の生徒さんたちが出展して 「芳林書展」 という展覧会が 横浜の 神奈川県民ホールのギャラリーを借り切って 催されます。
会場内、たまたま お出会いした 美女たち

『芳林書道院』代表 水川舟芳先生の 今回の出展作品









私の先生、 西嶋恵舟先生 と 今回の 出展作品


今回、1ケ月以上 この作品と取り組んで
とても納得できる出来るものではないのですが・・・
「どこまでいっても 自分の作品に 満足できるなんてことは ないものよ」
と
先生は 慰めてくれた・・・
書道を始めたばかりのころ 本部の 月刊誌に 水川舟芳先生の インタビュー記事が連載されていました。
前略
聞き手 深く追求することが大事なんですね。
舟芳 若いときからいろんな趣味に手を広げていて、50,60になって書を初めても1週間に1回か2回、わずか30分か1時間筆をもつというのは、趣味とはいえないよね。 時間つぶしなわけ。
聞き手 時間つぶしですか。
舟芳 そういう人は、書というものの本当の面白さは感じないでしょう。 趣味ということは、趣がある、味わいがあるということなのね。 それこそ真剣勝負でやらないと趣があったり 味わいがあったりしない、 そういうのは趣味じゃなくて遊びなの。 趣味を取り違えちゃいけない、と思います。
後略
これを 読んだときは ショックでした。
「私の 趣味は~ 」などと 迂闊に言えない、 と思いました。
今、
せめて 「趣味は書道です」 と 言えるようになりたい、 と思います。

興徳寺 東屋(あずまや) 「富士見亭」より
Posted by kotokuji at
20:21
│Comments(0)
2011年01月14日
あの素晴しい愛をもう一度
ちょっと前のこと、友人の 久美子さんより 私の誕生日に ランチのお誘い。 当日は 七面山に登ると決めていたので、その前日に予定を組んでもらいました。 すべては お楽しみ・・・ ということで 連れて行かれたのは 朝霧高原 の 三好礼子さんの経営する 「フェアリーカフェ」。

三好礼子さん(山村レイコ←旧仕事名)
自然回帰型生活びと・エッセイスト・農民・国際ラリースト
1957年12月15日生まれの53歳 酉年 射手座 血液型B
このような カッコイイ オネエサン です。
是非 HPをご覧下さい。
http://www.fairytale.jp/
礼子さんの農場

突然の呼び出しにもかかわらず 友人が集まってくれました。 ただ ビックリ・・・

美女から 花束を受ける、 初めての体験・・・


特別メニュー

”フォークデュオ 五十雀(ごじゅうから)”

後ろの壁は レイコさんが レースで使用した レーシングスーツ
ワルノリ最強ペア Kumiko ~ & Reiko ~~~!!

懐かしの フォークソングを 皆で歌いまくる。 これは 楽しかった・・・
「あの素晴しい 愛をもう一度」を 皆で歌った。 この歌は とっても好き、
命かけてと 誓った日から
素敵な思い出 残して来たのに
あの時 同じ花を見て
美しいと言った二人の
心と心が 今はもう通わない
あの素晴しい 愛をもう一度
あの素晴しい 愛をもう一度
こんな経験、何度もある。
心って 本当に不思議で やっかいなもの って思う。
誰かが 「この歌って 失恋の 歌だよね~?」 私もそう思っていたのだが 間を入れず
”五十雀”の 藤沢さん 曰く 「ちがうよ~ いろいろなことを 乗り越えて やっと結ばれたカップルに贈られた歌なんだ、 作曲の加藤和彦さんが 言ってたんだから間違いない!」
皆 「へエ~ッ!」 と絶句。
作詞家の北山修さんが 加藤和彦さんへ 結婚祝いとして詞を贈り、その年のクリスマスに加藤さんが曲を付けて夫人にプレゼントした・・・ ということらしい。 加藤和彦さんと 奥様ミカさんの間には 心が通わなくなったことも あっただろうな~ と 勝手に想像、 でも この歌に対する見方が 変わりました。

嬉しい 誕生日でした。 皆さん ありがとうございました。


三好礼子さん(山村レイコ←旧仕事名)
自然回帰型生活びと・エッセイスト・農民・国際ラリースト
1957年12月15日生まれの53歳 酉年 射手座 血液型B
このような カッコイイ オネエサン です。
是非 HPをご覧下さい。
http://www.fairytale.jp/
礼子さんの農場

突然の呼び出しにもかかわらず 友人が集まってくれました。 ただ ビックリ・・・

美女から 花束を受ける、 初めての体験・・・


特別メニュー

”フォークデュオ 五十雀(ごじゅうから)”

後ろの壁は レイコさんが レースで使用した レーシングスーツ
ワルノリ最強ペア Kumiko ~ & Reiko ~~~!!

懐かしの フォークソングを 皆で歌いまくる。 これは 楽しかった・・・
「あの素晴しい 愛をもう一度」を 皆で歌った。 この歌は とっても好き、
命かけてと 誓った日から
素敵な思い出 残して来たのに
あの時 同じ花を見て
美しいと言った二人の
心と心が 今はもう通わない
あの素晴しい 愛をもう一度
あの素晴しい 愛をもう一度
こんな経験、何度もある。
心って 本当に不思議で やっかいなもの って思う。
誰かが 「この歌って 失恋の 歌だよね~?」 私もそう思っていたのだが 間を入れず
”五十雀”の 藤沢さん 曰く 「ちがうよ~ いろいろなことを 乗り越えて やっと結ばれたカップルに贈られた歌なんだ、 作曲の加藤和彦さんが 言ってたんだから間違いない!」
皆 「へエ~ッ!」 と絶句。
作詞家の北山修さんが 加藤和彦さんへ 結婚祝いとして詞を贈り、その年のクリスマスに加藤さんが曲を付けて夫人にプレゼントした・・・ ということらしい。 加藤和彦さんと 奥様ミカさんの間には 心が通わなくなったことも あっただろうな~ と 勝手に想像、 でも この歌に対する見方が 変わりました。

嬉しい 誕生日でした。 皆さん ありがとうございました。

Posted by kotokuji at
19:30
│Comments(0)
2011年01月11日
何度でも 初心に戻れる 七面山
昨日、1月10日は 私の誕生日。 61歳になりました。
毎年、この日は 一人で 七面山に登ります。
お正月は 年始客等も多いので、 この日を1年の新たなるスタートと決め、 自分を見つめる機会ととらえています。
朝の5時に 家を出て、 登り始めたのが 6時半。
このところの 運動不足が端的に現れ かなりキツイ思いもしましたが だんだん慣れてきて・・・
25丁を過ぎたあたり(ちょうど 行程の半分)から 周りは雪。


途中の休憩所 の寒暖計で マイナス10℃
てぶくろ外して オニギリ食べて
写真を撮ってたら
何と 指が動かなくなった・・・
「和光門」~「敬慎院」 も雪の中



山頂は マイナス12℃
寒い というより 痛い、
身が 引き締まります。
昼の10時半
快晴!
風もない
とっても いい気持・・・

坂を上りつめると「随身門」
富士山 が きっちり と枠の中に 鎮座している。
何度来ても 感激の一瞬です。
登り道、 何故 ここに来るのだろう? と考えていました。
僧侶としての 修行?
それも ある・・
でも
何も 考えず、 ただ ひたすら登る、 というのが イイ と思いました。
少々 キツイ思いをするけれど そのプロセス そのものが イイ とも感じました。
何よりも 澄み切った 山の空気が イイ ・・・

そんな時 出会った この立て札。
(七面山の 登山道は ところどころに このような 立て札が 立てられている)
「何度でも 初心に戻れる 七面山」
イイ言葉 だと思いました。
私たちは 「初心に戻る」 ということの大切さを よく思う。
だけど それは 「ヨシッ!」 と気合を入れて できるようなことでなく
肉体に 少し 負担をかけて その中で 改めて考えてみるのが いい と 思えます。
七面山に 参詣するには 誰もが 同じように この苦しい道のりを歩かなければならない。
ベテラン も 初めての人も まったく同じこと、
改めて 坊さんの 修行を始めたばかりの頃のことを思い出していました。
最近 坊さんとして 必要な 教学(仏教の勉強)を 怠っているなぁ、
運動もしてないなぁ~ だから こんなに キツイんだなぁ、
坊さんになって 6年ばかりで 解ったような エラソウなこと
言ってるんじゃないかなぁ~
も一度 あの頃の気持ちに 戻ってみよう と思いました。

オ・マ・ケ・・
実は 立て札を 見て 考えさせられて
そうだ これを ブログネタ にしようと、 帰り道 写真を撮りました。
ただ ポツン と撮っても おもしろくないので、 アクセントに 持ってた杖を 立てかけました。
もうここからは 下るだけ、 食べ物の残りも 食べて、 飲む物 飲んで、
歌いながら(私は 山の下りは ずっと歌を歌う) ピョコピョコと 上機嫌で下っていったのです。
しばらくしてから 「あぁ~ッ、 つッ・えェ・・・」
ここからの 戻り道のきつかったこと、 「あんな杖 どうでもいいかぁ~」 「いやいや それでは この登山の意味がない!」 と葛藤しながら やっとたどりつき
「フン!」 と」ひったくるようににして 下りてきたのです。
まだまだ 修行が足りません。
毎年、この日は 一人で 七面山に登ります。
お正月は 年始客等も多いので、 この日を1年の新たなるスタートと決め、 自分を見つめる機会ととらえています。
朝の5時に 家を出て、 登り始めたのが 6時半。
このところの 運動不足が端的に現れ かなりキツイ思いもしましたが だんだん慣れてきて・・・
25丁を過ぎたあたり(ちょうど 行程の半分)から 周りは雪。


途中の休憩所 の寒暖計で マイナス10℃
てぶくろ外して オニギリ食べて
写真を撮ってたら
何と 指が動かなくなった・・・
「和光門」~「敬慎院」 も雪の中



山頂は マイナス12℃
寒い というより 痛い、
身が 引き締まります。
昼の10時半
快晴!
風もない
とっても いい気持・・・

坂を上りつめると「随身門」
富士山 が きっちり と枠の中に 鎮座している。
何度来ても 感激の一瞬です。
登り道、 何故 ここに来るのだろう? と考えていました。
僧侶としての 修行?
それも ある・・
でも
何も 考えず、 ただ ひたすら登る、 というのが イイ と思いました。
少々 キツイ思いをするけれど そのプロセス そのものが イイ とも感じました。
何よりも 澄み切った 山の空気が イイ ・・・

そんな時 出会った この立て札。
(七面山の 登山道は ところどころに このような 立て札が 立てられている)
「何度でも 初心に戻れる 七面山」
イイ言葉 だと思いました。
私たちは 「初心に戻る」 ということの大切さを よく思う。
だけど それは 「ヨシッ!」 と気合を入れて できるようなことでなく
肉体に 少し 負担をかけて その中で 改めて考えてみるのが いい と 思えます。
七面山に 参詣するには 誰もが 同じように この苦しい道のりを歩かなければならない。
ベテラン も 初めての人も まったく同じこと、
改めて 坊さんの 修行を始めたばかりの頃のことを思い出していました。
最近 坊さんとして 必要な 教学(仏教の勉強)を 怠っているなぁ、
運動もしてないなぁ~ だから こんなに キツイんだなぁ、
坊さんになって 6年ばかりで 解ったような エラソウなこと
言ってるんじゃないかなぁ~
も一度 あの頃の気持ちに 戻ってみよう と思いました。

オ・マ・ケ・・
実は 立て札を 見て 考えさせられて
そうだ これを ブログネタ にしようと、 帰り道 写真を撮りました。
ただ ポツン と撮っても おもしろくないので、 アクセントに 持ってた杖を 立てかけました。
もうここからは 下るだけ、 食べ物の残りも 食べて、 飲む物 飲んで、
歌いながら(私は 山の下りは ずっと歌を歌う) ピョコピョコと 上機嫌で下っていったのです。
しばらくしてから 「あぁ~ッ、 つッ・えェ・・・」
ここからの 戻り道のきつかったこと、 「あんな杖 どうでもいいかぁ~」 「いやいや それでは この登山の意味がない!」 と葛藤しながら やっとたどりつき
「フン!」 と」ひったくるようににして 下りてきたのです。
まだまだ 修行が足りません。
Posted by kotokuji at
19:49
│Comments(0)
2011年01月08日
日本画の魅力
昨年の春 息子が来た時に 一緒に 箱根のポーラ美術館 に行きました。 たまたま 日本画の特集だったのですが 正直いって それまで 日本画とは どういうものかさえ知りませんでした。
横山大観、平山郁夫 等、名前は聞いたことがあるといった程度だったでしょうか。
どちらかといえば 奥の深い、繊細な絵 といったイメージをもっていたような気がします。
ところが その時初めて 日本画の本物に接して その圧倒されるような迫力に 信じられないような驚きと感動を覚えたのです。
色使いの鮮やかさ、繊細さ、きらめき 重なり合った色が織りなす深み、伝統的な技法と斬新な表現、 日本画の魅力に たちまちハマッテしまいました。
そのときに もっとも印象的だったのは 杉山寧 という作家です。
今回、「Japanist」 という雑誌で 偶然 日本画家 手塚雄二 を特集しており、その作品の写真をみて 「これは どうしても 本物を見たい!」 と思いました。
『こもれびの坂 手塚雄二 1996』
そして 名古屋の松坂屋のギャラリーで 展覧会が開かれていることを知り、 本日行ってきました。
写真や 印刷技術が進んでも 本物がもつ魅力はなかなか伝えられるものではない、 特に日本画においては 顕著だと思います。
この作家の「洗い」という技法;色をのせてから水を含ませた刷毛で色を落とす。また色を塗り、落とす。それを何百回と繰り返して残る偶発的な色合い。風合い。それを「味」と呼ぶ。 雑誌Japanistより。 本当に感動的な 深~い 深い色、 まさに 「味」です。
名古屋までは 250km、 丸々1日を費やしましたが 充分以上の価値がありました。 感動の余韻に今も 包まれていて カタログ見ながら ため息 をついているのです。

今朝の富士山、 富士川より
横山大観、平山郁夫 等、名前は聞いたことがあるといった程度だったでしょうか。
どちらかといえば 奥の深い、繊細な絵 といったイメージをもっていたような気がします。
ところが その時初めて 日本画の本物に接して その圧倒されるような迫力に 信じられないような驚きと感動を覚えたのです。
色使いの鮮やかさ、繊細さ、きらめき 重なり合った色が織りなす深み、伝統的な技法と斬新な表現、 日本画の魅力に たちまちハマッテしまいました。
そのときに もっとも印象的だったのは 杉山寧 という作家です。
今回、「Japanist」 という雑誌で 偶然 日本画家 手塚雄二 を特集しており、その作品の写真をみて 「これは どうしても 本物を見たい!」 と思いました。
『こもれびの坂 手塚雄二 1996』

そして 名古屋の松坂屋のギャラリーで 展覧会が開かれていることを知り、 本日行ってきました。
写真や 印刷技術が進んでも 本物がもつ魅力はなかなか伝えられるものではない、 特に日本画においては 顕著だと思います。
この作家の「洗い」という技法;色をのせてから水を含ませた刷毛で色を落とす。また色を塗り、落とす。それを何百回と繰り返して残る偶発的な色合い。風合い。それを「味」と呼ぶ。 雑誌Japanistより。 本当に感動的な 深~い 深い色、 まさに 「味」です。
名古屋までは 250km、 丸々1日を費やしましたが 充分以上の価値がありました。 感動の余韻に今も 包まれていて カタログ見ながら ため息 をついているのです。

今朝の富士山、 富士川より
Posted by kotokuji at
22:41
│Comments(0)
2011年01月05日
箱根駅伝
1昨日、箱根駅伝を 観戦に行ってきました。
その前日 「元旦会」も無事終了し、何となくほっとして TVで 駅伝の中継を観ていたのですが、5区 箱根の上り坂 東洋大 柏原選手の 走りを見ているうちに 何か急に行ってみたくなり、翌日の朝、5時40分に家を出ました。
行ったのは 復路 第7区の 小田原中継所。 新富士駅に バイクを置いて 新幹線で行ったのですが、1時間半も前に着いてしまった。 それでも 会場は もうかなりの熱気! これがいいんですね~
小田原中継所
多くの裏方さんたちの 黙々と準備する姿、 各大学の応援団も到着する・・・ 白バイが ヒュ~ンと飛んできて 目の前で クルッとターンする・・・ スッゲエ~! なんて、全然退屈しません。

選手達が出てきて ウォーミングアップを始める頃には 盛り上がり度も最高潮!

そして その時が 来たッ!
2位 東洋大 小池選手の フィニッシュ。

神奈川大学 高久選手 ゴール200m前

もともと土建屋~建築屋と ずっと現場を歩いてきたからか、現場第一主義。 現場に行かなきゃ ワカラナイ、 と思っています。
スポーツ観戦でも 観劇でも TVではなく 本物が観たい。 映画なら 映画館で観たい。
5感を通して 伝わってくる あのフンイキは 行ったことのない人には なかなか伝えられないのですが・・・
始まる前の緊張感 が好き。 コンサートなら 幕の向こう側から 聞こえてくる 音合わせ、 スポーツ観戦なら ウォーミングアップ時に見せる 鍛え抜かれた選手の 並外れた力量、 それらが 今か今かと その時を待つ観客に伝って 興奮度が高まってゆきます。
駅伝は 初めてでしたが 伴走車から激を飛ばすコーチの声が スピーカーを通して ガンガンと響く中で目の前を疾走する選手の 息遣いが 聞こえる。 どの選手にも 「ガンバレ~!」 と声をかけていました。
往復4時間、寒い中 待つこと1時間半、 なのに 観戦時間わずか10数分の ドラマ、
割に合わないような気もします。 でも 「来年は もう少し先、平塚あたりで観ようかな~」なんて 考えているのです。

生まれ変わったら・・・
やりたいことは いっぱいあるけれど この「箱根駅伝」 は 走ってみたいなぁ~
その前日 「元旦会」も無事終了し、何となくほっとして TVで 駅伝の中継を観ていたのですが、5区 箱根の上り坂 東洋大 柏原選手の 走りを見ているうちに 何か急に行ってみたくなり、翌日の朝、5時40分に家を出ました。
行ったのは 復路 第7区の 小田原中継所。 新富士駅に バイクを置いて 新幹線で行ったのですが、1時間半も前に着いてしまった。 それでも 会場は もうかなりの熱気! これがいいんですね~
小田原中継所

多くの裏方さんたちの 黙々と準備する姿、 各大学の応援団も到着する・・・ 白バイが ヒュ~ンと飛んできて 目の前で クルッとターンする・・・ スッゲエ~! なんて、全然退屈しません。

選手達が出てきて ウォーミングアップを始める頃には 盛り上がり度も最高潮!

そして その時が 来たッ!
2位 東洋大 小池選手の フィニッシュ。

神奈川大学 高久選手 ゴール200m前

もともと土建屋~建築屋と ずっと現場を歩いてきたからか、現場第一主義。 現場に行かなきゃ ワカラナイ、 と思っています。
スポーツ観戦でも 観劇でも TVではなく 本物が観たい。 映画なら 映画館で観たい。
5感を通して 伝わってくる あのフンイキは 行ったことのない人には なかなか伝えられないのですが・・・
始まる前の緊張感 が好き。 コンサートなら 幕の向こう側から 聞こえてくる 音合わせ、 スポーツ観戦なら ウォーミングアップ時に見せる 鍛え抜かれた選手の 並外れた力量、 それらが 今か今かと その時を待つ観客に伝って 興奮度が高まってゆきます。
駅伝は 初めてでしたが 伴走車から激を飛ばすコーチの声が スピーカーを通して ガンガンと響く中で目の前を疾走する選手の 息遣いが 聞こえる。 どの選手にも 「ガンバレ~!」 と声をかけていました。
往復4時間、寒い中 待つこと1時間半、 なのに 観戦時間わずか10数分の ドラマ、
割に合わないような気もします。 でも 「来年は もう少し先、平塚あたりで観ようかな~」なんて 考えているのです。

生まれ変わったら・・・
やりたいことは いっぱいあるけれど この「箱根駅伝」 は 走ってみたいなぁ~
Posted by kotokuji at
17:16
│Comments(0)
2011年01月03日
お正月は いいもんだ
「お正月は いいもんだ、 いくつになっても いいもんだ」
亡き父が好んで使っていた この言葉を 正月が 来るたびに 思い出します。
「なんとなく 今年はよいこと
あるごとし 元日の朝
晴れて風なし 啄木」
これも 私の好きな句。
お正月は 誰もが 幸せになれる日ですね。
平成23年の 「初日の出」

元日の朝の富士山

お正月って 本当に いいもんだなぁ~ って思います。
さて 昨日は 興徳寺の 『元旦会(がんたんえ)』
10時より 法要


10時40分より 住職の法話、
毎年、日本昔話より お話をひとつ。
今年は 「節分の鬼」 というお話をしました。
おかみさんと 一人息子に先立たれ 「早く迎えに来てくれや~・・・」と 毎日 お墓でお願いをしていた おじいさん。
福の神にも とっくに見放されたと 節分の夜 わざとあべこべに 「福は外~ 鬼は内~」と やったら 何と 節分で追われた鬼どもが 集まってきて・・・ 呑めや 歌えの 大宴会、
おじいさんも すっかり嬉しくなって 踊りだす・・・
春になって お墓の前で・・・
「おらぁ もう少し長生きすることにしただ~ 来年の節分も 鬼たちば 呼ばねばならねぇ~ そう約束したでな~」
そういって 晴れ晴れした顔で 山を下りていったとさ・・・
「死にたい」といって死ねるものでもない、「死にたくない」といっても そうはいかない。
遠い先のことなど 誰にも分からないのです
来年までは! と楽しい目標を作って 一年一年を 積み重ねてゆきましょう、 と結びました。

ハーモニカ を吹いたり 下手な 書初め を披露したりと あの手この手の ワンマンショー(?)

住職からの 「お年玉」 は 特注の 紅白餡入り落雁、

外では 「甘酒」 と 「お汁粉」 ・・・

富士山も きれいで いい お正月でした。

これが 終わって やっと 私の お正月です。
亡き父が好んで使っていた この言葉を 正月が 来るたびに 思い出します。
「なんとなく 今年はよいこと
あるごとし 元日の朝
晴れて風なし 啄木」
これも 私の好きな句。
お正月は 誰もが 幸せになれる日ですね。
平成23年の 「初日の出」

元日の朝の富士山

お正月って 本当に いいもんだなぁ~ って思います。
さて 昨日は 興徳寺の 『元旦会(がんたんえ)』
10時より 法要


10時40分より 住職の法話、
毎年、日本昔話より お話をひとつ。
今年は 「節分の鬼」 というお話をしました。
おかみさんと 一人息子に先立たれ 「早く迎えに来てくれや~・・・」と 毎日 お墓でお願いをしていた おじいさん。
福の神にも とっくに見放されたと 節分の夜 わざとあべこべに 「福は外~ 鬼は内~」と やったら 何と 節分で追われた鬼どもが 集まってきて・・・ 呑めや 歌えの 大宴会、
おじいさんも すっかり嬉しくなって 踊りだす・・・
春になって お墓の前で・・・
「おらぁ もう少し長生きすることにしただ~ 来年の節分も 鬼たちば 呼ばねばならねぇ~ そう約束したでな~」
そういって 晴れ晴れした顔で 山を下りていったとさ・・・
「死にたい」といって死ねるものでもない、「死にたくない」といっても そうはいかない。
遠い先のことなど 誰にも分からないのです
来年までは! と楽しい目標を作って 一年一年を 積み重ねてゆきましょう、 と結びました。

ハーモニカ を吹いたり 下手な 書初め を披露したりと あの手この手の ワンマンショー(?)

住職からの 「お年玉」 は 特注の 紅白餡入り落雁、

外では 「甘酒」 と 「お汁粉」 ・・・

富士山も きれいで いい お正月でした。

これが 終わって やっと 私の お正月です。
Posted by kotokuji at
18:09
│Comments(0)