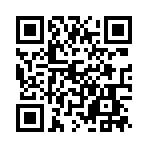2013年11月26日
たはむれに
『戯れに母を背負いて そのあまり
軽きに泣きて 三歩歩まず』 石川啄木

母の介護用品のレンタル会社に 手すり などをつけてもらったとき、ついでに 車イスもレンタルしました。
もう何ケ月も前のことです。
朝、翌日の法事のお膳に使う レンコンと油揚げを切らしていることを思い出し、「そうだツ、母を連れて スーパーに行こう!」と閃いたのです。
朝食の後 「オカアチャン、スーパーに行こうか?」 と言うと 嬉しそうに 「イイネッ~」と・・・ 週一回のデイサービスに行く日とは まるで反応が違います。
スーパーまでは 車で20分、 新車の車イスに母を乗せ 膝の上でかごを抱いてもらい、チョコチョコッと買い物を済ませ、 母の喜ぶキャラメルを買い、花屋の前を 通ったら 「花 買って~」と言うので 花も買い、
車イス・スーパーデビューの記念写真

!

通り合わせの買い物客が 「ア~ラ、いいわね~」などと・・・
母も嬉しそうです。

こんなことなら もっと早く連れてきてやれば・・・ などと思いながら 帰ってきたのですが 天気もよかったので 最近竣工した 墓地へ、車イスを押し上げてみました。
その時に 思い浮かんだのが 冒頭の一句、
背負ったらまだ重たそうだけど 車イスなら 何とか・・・

「ハイ 笑って、笑って~・・・」 と言うと ちゃんと笑ってくれるところが エライ!
新しい墓地、富士山が正面です。

いくつかの行事と お葬式が重なって、『興徳寺便り』も大幅に遅れています。 ギリギリの今週末に発送して、来週の月曜日から もう 暮のお経廻りです。 秋を堪能する間もなかったな~ なんて思っています。
軽きに泣きて 三歩歩まず』 石川啄木

母の介護用品のレンタル会社に 手すり などをつけてもらったとき、ついでに 車イスもレンタルしました。
もう何ケ月も前のことです。
朝、翌日の法事のお膳に使う レンコンと油揚げを切らしていることを思い出し、「そうだツ、母を連れて スーパーに行こう!」と閃いたのです。
朝食の後 「オカアチャン、スーパーに行こうか?」 と言うと 嬉しそうに 「イイネッ~」と・・・ 週一回のデイサービスに行く日とは まるで反応が違います。
スーパーまでは 車で20分、 新車の車イスに母を乗せ 膝の上でかごを抱いてもらい、チョコチョコッと買い物を済ませ、 母の喜ぶキャラメルを買い、花屋の前を 通ったら 「花 買って~」と言うので 花も買い、
車イス・スーパーデビューの記念写真

!

通り合わせの買い物客が 「ア~ラ、いいわね~」などと・・・
母も嬉しそうです。

こんなことなら もっと早く連れてきてやれば・・・ などと思いながら 帰ってきたのですが 天気もよかったので 最近竣工した 墓地へ、車イスを押し上げてみました。
その時に 思い浮かんだのが 冒頭の一句、
背負ったらまだ重たそうだけど 車イスなら 何とか・・・

「ハイ 笑って、笑って~・・・」 と言うと ちゃんと笑ってくれるところが エライ!
新しい墓地、富士山が正面です。


いくつかの行事と お葬式が重なって、『興徳寺便り』も大幅に遅れています。 ギリギリの今週末に発送して、来週の月曜日から もう 暮のお経廻りです。 秋を堪能する間もなかったな~ なんて思っています。
Posted by kotokuji at
21:10
│Comments(0)
2013年11月15日
青の洞門
福岡で 『ハル』のコンサート、
「ご当地アイドル」なんて言葉はちょっと似合わないけど、地元でこんなにも多くの方たちに愛されている、ということを改めて感じながら、至福の時を過ごさせていただきました。

翌日(11/12)レンタルバイクで『耶馬溪、青の洞門』へ・・・

『青の洞門』のことは 小学校の頃、仏教劇画みたいな本があって そこで初めて知り、その後、この話をモデルに書かれた 菊池寛の短編小説『恩讐の彼方に』を読んで 大いに感激し 一度は訪ねてみたいと 思っていたのです。
『恩讐の彼方に』・・・
凶状持ち(主人の愛妾と通じて主人を殺害)の市九郎、妾とともに江戸を出奔し、峠で旅人を殺す非道な暮らしをしていましたが、自らの罪業に恐れをなし、出家して「了海」と名乗ります。 修行が明け、全国行脚の旅に出、羅漢寺に向かう山国川沿いの断崖絶壁に鎖で結ばれた丸太の道で通行人が命を落とすのを見て この川沿いの岩山を掘削することで、自らの罪滅ぼしをしようと誓願を立てます。近在の者は嘲笑い、狂人扱いしますが、来る日も来る日も鑿(のみ)と槌(つち)をふるい、ついに21年目に洞門を貫通させるという内容です。

山国川上流から 望む
紅葉は 始まったばかり
菊池寛は、青の洞門を開削した実在の僧・禅海の史実をモチーフにして作品を作り上げたそうです。実際には 禅海和尚は 托鉢により資金を集め、享保20年(1735)から自ら鑿(のみ)と槌(つち)をふるい、付近の村人の協力も得て、30年の歳月をかけて明和元年(1764)に全長360m(そのうちトンネル部分は144m)にも及ぶ青の洞門を完成させたました。

洞門の入口に立って
禅海和尚に 思いを馳せる・・・
改めて この断崖絶壁の岩山に
鎖で縛り付けられた丸太の桟橋が
横たわっている様を想像してみました。
人だけならまだしも
馬を引いて歩くことも
馬がすくんで 暴れだせば
そのまま川にまっさかさまです。

そして このトンネルの長さ・・・
機械も何もない
ただ ハンマーと鑿(のみ)だけで
掘る・・・
掘る・・・
掘る・・・
一日で何センチ?
2日・3日・・・1年、2年・・・
10年、20年・・・

禅海和尚。
39歳から72歳までの 33年間を
ただ トンネル堀に費やした・・・
その情熱、
それを保ち続けた
真のモチベーションは
何であったのか?
僧侶としての生き方に 自分自身を重ねて
イメージしてみました。
誰のためでもない、
己自身のためであったな、
と 思います。
今わずかに残る 禅海和尚の手堀りのトンネルと明かり窓


羅漢寺の仁王門

同じく羅漢寺の 山門と 本堂


ちょうど 大相撲福岡場所の開催中、
『ハル』 たちを 「福岡のオヤジ・オフクロ」と慕う 九重部屋の 千代の国(十両)と 千代疾風(序二段)が 私の歓迎会に来てくれました。

若いのに 礼儀正しく 謙虚で いっぺんで ファンに、 TVの相撲観戦が待ち遠しくなりました。
一緒にバカなことを言っていた あの子たちが 土俵に上がると 別人です。 (本日まで 千代の国 3勝3敗、千代疾風は3勝0敗)。

「ご当地アイドル」なんて言葉はちょっと似合わないけど、地元でこんなにも多くの方たちに愛されている、ということを改めて感じながら、至福の時を過ごさせていただきました。

翌日(11/12)レンタルバイクで『耶馬溪、青の洞門』へ・・・

『青の洞門』のことは 小学校の頃、仏教劇画みたいな本があって そこで初めて知り、その後、この話をモデルに書かれた 菊池寛の短編小説『恩讐の彼方に』を読んで 大いに感激し 一度は訪ねてみたいと 思っていたのです。
『恩讐の彼方に』・・・
凶状持ち(主人の愛妾と通じて主人を殺害)の市九郎、妾とともに江戸を出奔し、峠で旅人を殺す非道な暮らしをしていましたが、自らの罪業に恐れをなし、出家して「了海」と名乗ります。 修行が明け、全国行脚の旅に出、羅漢寺に向かう山国川沿いの断崖絶壁に鎖で結ばれた丸太の道で通行人が命を落とすのを見て この川沿いの岩山を掘削することで、自らの罪滅ぼしをしようと誓願を立てます。近在の者は嘲笑い、狂人扱いしますが、来る日も来る日も鑿(のみ)と槌(つち)をふるい、ついに21年目に洞門を貫通させるという内容です。

山国川上流から 望む
紅葉は 始まったばかり
菊池寛は、青の洞門を開削した実在の僧・禅海の史実をモチーフにして作品を作り上げたそうです。実際には 禅海和尚は 托鉢により資金を集め、享保20年(1735)から自ら鑿(のみ)と槌(つち)をふるい、付近の村人の協力も得て、30年の歳月をかけて明和元年(1764)に全長360m(そのうちトンネル部分は144m)にも及ぶ青の洞門を完成させたました。

洞門の入口に立って
禅海和尚に 思いを馳せる・・・
改めて この断崖絶壁の岩山に
鎖で縛り付けられた丸太の桟橋が
横たわっている様を想像してみました。
人だけならまだしも
馬を引いて歩くことも
馬がすくんで 暴れだせば
そのまま川にまっさかさまです。

そして このトンネルの長さ・・・
機械も何もない
ただ ハンマーと鑿(のみ)だけで
掘る・・・
掘る・・・
掘る・・・
一日で何センチ?
2日・3日・・・1年、2年・・・
10年、20年・・・

禅海和尚。
39歳から72歳までの 33年間を
ただ トンネル堀に費やした・・・
その情熱、
それを保ち続けた
真のモチベーションは
何であったのか?
僧侶としての生き方に 自分自身を重ねて
イメージしてみました。
誰のためでもない、
己自身のためであったな、
と 思います。
今わずかに残る 禅海和尚の手堀りのトンネルと明かり窓


羅漢寺の仁王門

同じく羅漢寺の 山門と 本堂


ちょうど 大相撲福岡場所の開催中、
『ハル』 たちを 「福岡のオヤジ・オフクロ」と慕う 九重部屋の 千代の国(十両)と 千代疾風(序二段)が 私の歓迎会に来てくれました。

若いのに 礼儀正しく 謙虚で いっぺんで ファンに、 TVの相撲観戦が待ち遠しくなりました。
一緒にバカなことを言っていた あの子たちが 土俵に上がると 別人です。 (本日まで 千代の国 3勝3敗、千代疾風は3勝0敗)。

Posted by kotokuji at
21:53
│Comments(0)
2013年11月10日
お会式の伝説
本日、興徳寺の『お会式』でした。
宗祖日蓮大聖人(しょうにん)のお年忌で、ご命日(10月13日)の頃に 日本中の日蓮宗あるいは 日蓮聖人の教えを根本とするすべての寺院で 執り行われる行事です。
興徳寺は毎年 11月の第2日曜日としています。

開式まで2時間、
台所は お手伝いの 女衆(おんなしゅう、このあたりでは おんなし と呼びます)がテンヤワンヤ・・・


こちらは男衆、
お台所を支えてくれた 美人スタッフ=女衆

世話人さんたち=男衆


興徳寺のお会式伝説、
それは・・・
興徳寺のお会式は
・・・・
雨が降らない!
天気予報は 全国的に雨、
各地の予報でも
「曇り~雨、午後は本降り」
それが 開式前は 曇り、
式の途中でパラパラときましたが
みなさんがお帰りになるころは
ほとんど気にならないような降りに
変わっていたのです。
伝説、恐るべし!

開式に先立って 前列の方たちに 太鼓の稽古
「『だんだんよくなる 法華のタイコ』
という言葉があります。
だんだん気持ちよくなってテンポがどんどん
早くなることが ママありますので
そこだけ気をつけてください」

本堂にいっぱいのお参詣をいただきました。

法要の後は 東光寺住職 川名義博上人の 高座説教。

母親が 岩手県大船渡市の出身で 震災直後に被災地を訪れ、 以後 現在に至るまで支援活動を続けておられます。
皆でお食事

庫裏の 4つの8畳間の襖を全部外して 大広間に・・・ 古き日本建築は 実に合理的な建物であります。
また食事も シイタケのご飯とみそ汁・漬物、それに 春に塩蔵しておいた 筍・蕗、更に 今が旬の里芋と こんにゃくの煮っころがしと なます。 まったくの素朴な田舎料理ですが すべて女衆の手作りで、これもまた 興徳寺の伝統の味です。

1年の区切りの日、があるとしたら 私の場合、正月でも 誕生日でもなく 「お会式」です。
9年前の 「お会式」で 私は 出家しました。
今日から 僧侶としての10年目がスタートします。 10年を ひとつのステップとするなら まさに締めくくりの年、 来年のこの日、きちっと総括したく 精進して参ります。

明日から 九州に行きます。 毎年11月11日が 『ハル』のコンサートなのですが いつもお会式前で行けず、やっとチャンスがきました。
12日はレンタルバイクで 耶馬溪まで ツーリングしてきます。
*今回の 「お会式」の写真は 富士市のアマチュアカメラマン 加藤年一さんに お願いし 撮っていただきました。 ありがとうございました。
宗祖日蓮大聖人(しょうにん)のお年忌で、ご命日(10月13日)の頃に 日本中の日蓮宗あるいは 日蓮聖人の教えを根本とするすべての寺院で 執り行われる行事です。
興徳寺は毎年 11月の第2日曜日としています。

開式まで2時間、
台所は お手伝いの 女衆(おんなしゅう、このあたりでは おんなし と呼びます)がテンヤワンヤ・・・


こちらは男衆、
お台所を支えてくれた 美人スタッフ=女衆

世話人さんたち=男衆


興徳寺のお会式伝説、
それは・・・
興徳寺のお会式は
・・・・
雨が降らない!
天気予報は 全国的に雨、
各地の予報でも
「曇り~雨、午後は本降り」
それが 開式前は 曇り、
式の途中でパラパラときましたが
みなさんがお帰りになるころは
ほとんど気にならないような降りに
変わっていたのです。
伝説、恐るべし!

開式に先立って 前列の方たちに 太鼓の稽古
「『だんだんよくなる 法華のタイコ』
という言葉があります。
だんだん気持ちよくなってテンポがどんどん
早くなることが ママありますので
そこだけ気をつけてください」

本堂にいっぱいのお参詣をいただきました。

法要の後は 東光寺住職 川名義博上人の 高座説教。

母親が 岩手県大船渡市の出身で 震災直後に被災地を訪れ、 以後 現在に至るまで支援活動を続けておられます。
皆でお食事

庫裏の 4つの8畳間の襖を全部外して 大広間に・・・ 古き日本建築は 実に合理的な建物であります。
また食事も シイタケのご飯とみそ汁・漬物、それに 春に塩蔵しておいた 筍・蕗、更に 今が旬の里芋と こんにゃくの煮っころがしと なます。 まったくの素朴な田舎料理ですが すべて女衆の手作りで、これもまた 興徳寺の伝統の味です。

1年の区切りの日、があるとしたら 私の場合、正月でも 誕生日でもなく 「お会式」です。
9年前の 「お会式」で 私は 出家しました。
今日から 僧侶としての10年目がスタートします。 10年を ひとつのステップとするなら まさに締めくくりの年、 来年のこの日、きちっと総括したく 精進して参ります。

明日から 九州に行きます。 毎年11月11日が 『ハル』のコンサートなのですが いつもお会式前で行けず、やっとチャンスがきました。
12日はレンタルバイクで 耶馬溪まで ツーリングしてきます。
*今回の 「お会式」の写真は 富士市のアマチュアカメラマン 加藤年一さんに お願いし 撮っていただきました。 ありがとうございました。
Posted by kotokuji at
20:53
│Comments(0)
2013年11月02日
樹を倒す
永いこと ブログの更新ができずにおりましたが、この3日間 山の樹を伐っておりまして これを報告したく・・・

『YUNOどんぐりの会』の今年の植樹場所、約2000平方メートルに 杉の樹が植えられており、それを自分たちの手で伐採することとなりました。
メンバーの中に プロの樵(きこり)さんが 2人(長谷川さんと 伊藤さん)おりまして それに私を含めて計8名でした。
《作業開始》

かつては 畑だった
平らな土地。
50年前に 杉が植えられ
その後、隣の竹林から
孟宗(もうそう)竹が侵入、
まるで
ジャングル状態だったものを
この春
竹だけは撤去しました。
柚野小学校の一年生、25名が 来てくれました。

山に囲まれて住んでいますが 樹の名前も知らず、まして伐る現場はなかなか 体験できません。


固唾をのんで 見守る・・・・・・・・

倒れた瞬間は 全員で拍手!!!
切り株で年輪を数えてもらったら ぴったり 50 でした。

年輪の 真ん中の1cmほどの丸、
「この木も 50年前は この太さだったんだよ~」
「へぇ~ツ~!」
と興味しんしんです。
《作業工程》
実は私自身、樹を伐る現場には何度も 立ち会ったこともありますが ジックリとお手伝いさせていただいたのは 今回が初めてです。
その結果 分かったこと。 立っている樹は 伐る、のではなく 倒す。 地元の樵さんたちは 「転ばす」と言います。 私は ずっと チェンソーで伐るものだと思っていたのですが、 実際は 楔(くさび)を使って 樹の重心を移動させて 自重で転ばす、のです。

① まず 倒す方向を決める。
ここ、と決めた位置に
ピタッ とあの大きな樹が倒れてゆく
本当にビックリします。


②倒す方向に 受け口を作る。

③反対側に切り込みを入れる

④楔(くさび)を打ち込む。
この楔の入れ方、数や大きさは
その樹の現在の重心がどちらにあるかによって判断します。
すべては経験によるものですが まっすぐな樹も
微妙に傾いているし、 枝の張り具合によっても
重心の方向が違います。
本来の重心方向と反対側にでも倒す技術には
感動!です。
いつも控えめな 長谷川さんや伊藤さんが
実は とても偉大な人であることが解りました。




⑤決められた長さに切る。
⑥枝を伐る~運ぶ


ここらあたりが 助手の仕事ですが これが なかなか大変、
⑦トラックに積み込みやすいように集めて 積み上げる


この重い木を プロは鳶口(とびくち)という道具一丁を巧みに操って 運び、 重ねてゆく。 「見事!」 としかいいようもない。

木が倒されていって 今まで見えなかった風景が 現れる・・・
「こんな イイト所だったんだ~」と 皆で感動しました。

8人が3日間働いて・・・ 50年育てられた 杉の木を伐り出した・・・
来週、業者が来て引き取ることになってます。 無料です。
ここまでやって 仕事賃も出ない、 それが現実なのです。 日本中で 手つかずの放置林が問題になっていますが 伐採~運搬~次の植樹までの費用が捻出できて なお手元に残る程度の木の単価が示されない限り 解決はできないでしょう。
①

②

③

① 今年の初め。
孟宗竹と 木が混じって 密林の様だった。
② 今回の伐採前、
杉の林です。
③ 現在の様子。
すっかり明るくなりました。
「ご先祖様が遺してくれた 大切な山」という 地主さんたちの特別な思いを 「ご先祖様に喜んでいただける山」に 育て上げてゆきたく思います。

『YUNOどんぐりの会』は 来年の定期総会を NPO法人の発足とすべく準備中です。 今は個人名義となっているすべての土地も NPOに寄贈し、志を同じくする次世代の方たちに バトンタッチしたく思います。
今回の土地には桜を植えたい。 30年後は 見事な桜の園となることでしょう。
*12月4日の植樹祭、ご参加を!
** 来週の日曜日(12/4)『 興徳寺のお会式(えしき)』、日蓮聖人の 732回目のお年忌。10時半の法要に引き続き 下条 東光寺住職 川名義博上人の「高座説教」。 檀家さん以外の方も どうぞ。

『YUNOどんぐりの会』の今年の植樹場所、約2000平方メートルに 杉の樹が植えられており、それを自分たちの手で伐採することとなりました。
メンバーの中に プロの樵(きこり)さんが 2人(長谷川さんと 伊藤さん)おりまして それに私を含めて計8名でした。
《作業開始》

かつては 畑だった
平らな土地。
50年前に 杉が植えられ
その後、隣の竹林から
孟宗(もうそう)竹が侵入、
まるで
ジャングル状態だったものを
この春
竹だけは撤去しました。
柚野小学校の一年生、25名が 来てくれました。

山に囲まれて住んでいますが 樹の名前も知らず、まして伐る現場はなかなか 体験できません。


固唾をのんで 見守る・・・・・・・・

倒れた瞬間は 全員で拍手!!!
切り株で年輪を数えてもらったら ぴったり 50 でした。

年輪の 真ん中の1cmほどの丸、
「この木も 50年前は この太さだったんだよ~」
「へぇ~ツ~!」
と興味しんしんです。
《作業工程》
実は私自身、樹を伐る現場には何度も 立ち会ったこともありますが ジックリとお手伝いさせていただいたのは 今回が初めてです。
その結果 分かったこと。 立っている樹は 伐る、のではなく 倒す。 地元の樵さんたちは 「転ばす」と言います。 私は ずっと チェンソーで伐るものだと思っていたのですが、 実際は 楔(くさび)を使って 樹の重心を移動させて 自重で転ばす、のです。

① まず 倒す方向を決める。
ここ、と決めた位置に
ピタッ とあの大きな樹が倒れてゆく
本当にビックリします。


②倒す方向に 受け口を作る。

③反対側に切り込みを入れる

④楔(くさび)を打ち込む。
この楔の入れ方、数や大きさは
その樹の現在の重心がどちらにあるかによって判断します。
すべては経験によるものですが まっすぐな樹も
微妙に傾いているし、 枝の張り具合によっても
重心の方向が違います。
本来の重心方向と反対側にでも倒す技術には
感動!です。
いつも控えめな 長谷川さんや伊藤さんが
実は とても偉大な人であることが解りました。




⑤決められた長さに切る。
⑥枝を伐る~運ぶ


ここらあたりが 助手の仕事ですが これが なかなか大変、
⑦トラックに積み込みやすいように集めて 積み上げる


この重い木を プロは鳶口(とびくち)という道具一丁を巧みに操って 運び、 重ねてゆく。 「見事!」 としかいいようもない。

木が倒されていって 今まで見えなかった風景が 現れる・・・
「こんな イイト所だったんだ~」と 皆で感動しました。

8人が3日間働いて・・・ 50年育てられた 杉の木を伐り出した・・・
来週、業者が来て引き取ることになってます。 無料です。
ここまでやって 仕事賃も出ない、 それが現実なのです。 日本中で 手つかずの放置林が問題になっていますが 伐採~運搬~次の植樹までの費用が捻出できて なお手元に残る程度の木の単価が示されない限り 解決はできないでしょう。
①

②

③

① 今年の初め。
孟宗竹と 木が混じって 密林の様だった。
② 今回の伐採前、
杉の林です。
③ 現在の様子。
すっかり明るくなりました。
「ご先祖様が遺してくれた 大切な山」という 地主さんたちの特別な思いを 「ご先祖様に喜んでいただける山」に 育て上げてゆきたく思います。

『YUNOどんぐりの会』は 来年の定期総会を NPO法人の発足とすべく準備中です。 今は個人名義となっているすべての土地も NPOに寄贈し、志を同じくする次世代の方たちに バトンタッチしたく思います。
今回の土地には桜を植えたい。 30年後は 見事な桜の園となることでしょう。
*12月4日の植樹祭、ご参加を!
** 来週の日曜日(12/4)『 興徳寺のお会式(えしき)』、日蓮聖人の 732回目のお年忌。10時半の法要に引き続き 下条 東光寺住職 川名義博上人の「高座説教」。 檀家さん以外の方も どうぞ。
Posted by kotokuji at
21:27
│Comments(0)