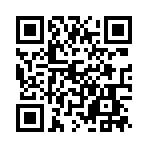2010年11月25日
獅子脅し 三代目
「獅子脅し」 を 作りました。
初めて作ったのが 2年前で、これが 3つ目です。
実物を見た事がないので、1作目は 結構苦労しましたが、今では そこそこのノウハウが蓄積されています。

裏庭にあるのですが、 山の水を引き込んで 余水を処理するという・・・(意味 わかるかな~?)
土建屋ならでは のノウハウもあります。


一番 苦労するのは 「コ~~ン」という音、
竹の 澄んだ 高い音が欲しいのだけれど
リバウンドして 「コ~ン、コッ」となってはダメ、
支点の位置 や 角度、竹を叩く石の位置、はてまた竹の種類や 竹の乾燥状態等、
名人の域には 程遠い・・・
ところで この「獅子脅し」、農業などに被害を与える鳥獣を威嚇し、追い払うために設けられる装置全般の総称で 本来は「鹿威し」と書くのだそうです。
私は いのしし を追い払う道具かと思っていました・・・?

「獅子脅し」
手前から
役目を終えた 初代、
~二代目、
~そして 三代目
・・・最近 裏山に かなり大きな いのししが出没している 形跡があったのですが、この日曜日 寺に隣接する竹林に仕掛けられた 罠 で 捕獲されました。 体重80kg以上だったとか。
その場で刺殺されたそう・・・
人と 山の動物たちが お互いの領域を守りつつ暮らせる 環境づくりが 急務であると思います。
初めて作ったのが 2年前で、これが 3つ目です。
実物を見た事がないので、1作目は 結構苦労しましたが、今では そこそこのノウハウが蓄積されています。

裏庭にあるのですが、 山の水を引き込んで 余水を処理するという・・・(意味 わかるかな~?)
土建屋ならでは のノウハウもあります。


一番 苦労するのは 「コ~~ン」という音、
竹の 澄んだ 高い音が欲しいのだけれど
リバウンドして 「コ~ン、コッ」となってはダメ、
支点の位置 や 角度、竹を叩く石の位置、はてまた竹の種類や 竹の乾燥状態等、
名人の域には 程遠い・・・
ところで この「獅子脅し」、農業などに被害を与える鳥獣を威嚇し、追い払うために設けられる装置全般の総称で 本来は「鹿威し」と書くのだそうです。
私は いのしし を追い払う道具かと思っていました・・・?

「獅子脅し」
手前から
役目を終えた 初代、
~二代目、
~そして 三代目
・・・最近 裏山に かなり大きな いのししが出没している 形跡があったのですが、この日曜日 寺に隣接する竹林に仕掛けられた 罠 で 捕獲されました。 体重80kg以上だったとか。
その場で刺殺されたそう・・・
人と 山の動物たちが お互いの領域を守りつつ暮らせる 環境づくりが 急務であると思います。
Posted by kotokuji at
14:47
│Comments(0)
2010年11月22日
寄り合い処
本日は 講演に行って来ました。
市内、内房(うつぶさ)地区の「寄り合い処(よりあいどころ)」です。
「寄り合い処」には、去年から これで4ケ所、年内にもう1ケ所が予定されています。
「寄り合い処」とは、富士宮市内の各地域で ボランティア・スタッフが自主的に運営する会。富士宮市社会福祉協議会の管轄で 現在 市内で77箇所の寄り合い処が開所しているそうです。
「地域のお茶の間」という位置づけで 誰でも自由に集い、おしゃべりできるところ、とされていますが 私が今まで訪ねた所は、毎月1回、地域の公民館で 近くに住むお年寄りの方を招き ボランティア・スタッフが食事を提供しています。

その食事の前に 指導員(交通・福祉・医療等)に来ていただいて 話を聞いたり、またミニコンサートを開いたり しているようですが、 私の講演も その時間帯で 行われます。
今日は 雨だったので 参加者が少なく(歩行補助用の手押し車で 来られる方もいるそう)12名、スタッフは6名でした。
参加者の平均年齢は 75歳以上、 スタッフは、70歳以下だったと思います。

与えられた時間は 1時間20分。分かりやすく、オモシロク、ナルホド! とうなずいてもらえるよう 慎重に 明るく 時に 童話や 唄も混ぜて 話を運びます。
「シアワセ いっぱい!」というテーマにしました。
「シアワセって何でしょう? どうしたら シアワセになれるでしょうか?」
私の過去も話しながら、苦しみ・悲しみ=不幸ではないこと、 お金があるとか・頭がいいとか・健康であること=幸せでもないこと、 世の中に偶然はないこと、 手を合わせ すべてに感謝できる状態を 幸せ、ということ などを話しました。
「みなさん、両手をじ~っと見てください。 いつの間にか シワがいっぱい、 アタシがムスメの頃は、白くてすべすべしたキレイな手だっただよ~、と 嘆かないで・・・ この刻まれた シワ、これが 今まで苦労してきた勲章です。 そのシワとシワを合わせて見ましょう。 ハイッ! シワ・アワセ=シ・ア・ワ・セ です」
古来 インドでは 右手は神聖なもの(=ほとけさま)左手は 不浄なもの(=衆生、つまり私たち) とされ、両手を合わせることによって、ほとけさまと私が ひとつになれる と教えます。


お楽しみの 食事、 本日は「カレーピラフ」。
とってもおいしかったです。
お年寄りが、 普段 自分の家では食べられないような、ちょっとしゃれたメニューにしているのかな?

食事の後は 楽しい おしゃべりタイムのようですが、私は失礼して 帰ってきました。
いつも感心するのは、このボランティア・スタッフが皆イキイキしていていること。
お年寄りを喜ばせたい、というそれだけの目的で、毎月毎月 講師を捜して、メニューを考えて、時には お家まで送り迎えもして・・・
私もその一員として 今後ともお役にたてれば、と思います。
市内、内房(うつぶさ)地区の「寄り合い処(よりあいどころ)」です。
「寄り合い処」には、去年から これで4ケ所、年内にもう1ケ所が予定されています。
「寄り合い処」とは、富士宮市内の各地域で ボランティア・スタッフが自主的に運営する会。富士宮市社会福祉協議会の管轄で 現在 市内で77箇所の寄り合い処が開所しているそうです。
「地域のお茶の間」という位置づけで 誰でも自由に集い、おしゃべりできるところ、とされていますが 私が今まで訪ねた所は、毎月1回、地域の公民館で 近くに住むお年寄りの方を招き ボランティア・スタッフが食事を提供しています。

その食事の前に 指導員(交通・福祉・医療等)に来ていただいて 話を聞いたり、またミニコンサートを開いたり しているようですが、 私の講演も その時間帯で 行われます。
今日は 雨だったので 参加者が少なく(歩行補助用の手押し車で 来られる方もいるそう)12名、スタッフは6名でした。
参加者の平均年齢は 75歳以上、 スタッフは、70歳以下だったと思います。

与えられた時間は 1時間20分。分かりやすく、オモシロク、ナルホド! とうなずいてもらえるよう 慎重に 明るく 時に 童話や 唄も混ぜて 話を運びます。
「シアワセ いっぱい!」というテーマにしました。
「シアワセって何でしょう? どうしたら シアワセになれるでしょうか?」
私の過去も話しながら、苦しみ・悲しみ=不幸ではないこと、 お金があるとか・頭がいいとか・健康であること=幸せでもないこと、 世の中に偶然はないこと、 手を合わせ すべてに感謝できる状態を 幸せ、ということ などを話しました。
「みなさん、両手をじ~っと見てください。 いつの間にか シワがいっぱい、 アタシがムスメの頃は、白くてすべすべしたキレイな手だっただよ~、と 嘆かないで・・・ この刻まれた シワ、これが 今まで苦労してきた勲章です。 そのシワとシワを合わせて見ましょう。 ハイッ! シワ・アワセ=シ・ア・ワ・セ です」
古来 インドでは 右手は神聖なもの(=ほとけさま)左手は 不浄なもの(=衆生、つまり私たち) とされ、両手を合わせることによって、ほとけさまと私が ひとつになれる と教えます。


お楽しみの 食事、 本日は「カレーピラフ」。
とってもおいしかったです。
お年寄りが、 普段 自分の家では食べられないような、ちょっとしゃれたメニューにしているのかな?

食事の後は 楽しい おしゃべりタイムのようですが、私は失礼して 帰ってきました。
いつも感心するのは、このボランティア・スタッフが皆イキイキしていていること。
お年寄りを喜ばせたい、というそれだけの目的で、毎月毎月 講師を捜して、メニューを考えて、時には お家まで送り迎えもして・・・
私もその一員として 今後ともお役にたてれば、と思います。
Posted by kotokuji at
20:54
│Comments(0)
2010年11月19日
富士山雪化粧
毎朝 5時40分頃 本堂に入り、朝勤(ちょうごん=朝のお勤め=お経を読むこと)をします。
脇机の時計に寒暖計がついていて、それを見るのが 癖になっていますが 今朝は5度でした。 この秋一番の冷え込みです。
こんな朝は 富士山がキレイだろうな~と 期待をしながら、お墓でのお経に カメラをぶら下げて行きました。
本堂の裏から。 朝の7時頃。
富士山が 雪化粧。
春夏秋冬、 富士山は その時々で 異なった表情を見せてくれますが、やはり雪の富士山はきれいです。

富士山の裾野(富士山の高まりがはじまっている部分)は153キロメートルだそうです。
そこに住む 誰もが 「自分の所から見た 富士山が 一番キレイ!」 と言います。
もちろん私も、「興徳寺からの 富士山が 一番!」 と思います。

でも 客観的に見ても ここからの 富士山は 日本一!ではないかと 思うのですが・・・
やはり 贔屓目でしょうか?
ブラジルに移住して7年後、初めて帰省した日のことを思い出します。
ちょうど 今頃の季節だったのですが、夜 帰宅して 翌日の明け方、しらじらとした光の中に 雪をいただいた富士山のシルエットを見たとき その神々しいまでの美しさに 思わず手を合わせていました。
何の変哲もない村ですが 富士山がある、というだけで 本当に シアワセだ、と思います。

「興徳寺展望台」より 興徳寺の全景。
画面左から 本堂~庫裏~車庫~墓地~ひまわり畑は もっと右の方
前に駐車場。新しい駐車場は 坂の下の方。前の白い建物が 小学校と中学校。
小川は 本堂より左奥方向。
脇机の時計に寒暖計がついていて、それを見るのが 癖になっていますが 今朝は5度でした。 この秋一番の冷え込みです。
こんな朝は 富士山がキレイだろうな~と 期待をしながら、お墓でのお経に カメラをぶら下げて行きました。
本堂の裏から。 朝の7時頃。

富士山が 雪化粧。
春夏秋冬、 富士山は その時々で 異なった表情を見せてくれますが、やはり雪の富士山はきれいです。

富士山の裾野(富士山の高まりがはじまっている部分)は153キロメートルだそうです。
そこに住む 誰もが 「自分の所から見た 富士山が 一番キレイ!」 と言います。
もちろん私も、「興徳寺からの 富士山が 一番!」 と思います。

でも 客観的に見ても ここからの 富士山は 日本一!ではないかと 思うのですが・・・
やはり 贔屓目でしょうか?
ブラジルに移住して7年後、初めて帰省した日のことを思い出します。
ちょうど 今頃の季節だったのですが、夜 帰宅して 翌日の明け方、しらじらとした光の中に 雪をいただいた富士山のシルエットを見たとき その神々しいまでの美しさに 思わず手を合わせていました。
何の変哲もない村ですが 富士山がある、というだけで 本当に シアワセだ、と思います。

「興徳寺展望台」より 興徳寺の全景。
画面左から 本堂~庫裏~車庫~墓地~ひまわり畑は もっと右の方
前に駐車場。新しい駐車場は 坂の下の方。前の白い建物が 小学校と中学校。
小川は 本堂より左奥方向。
Posted by kotokuji at
19:40
│Comments(0)
2010年11月16日
お会式
11月14日は お会式でした。

日蓮聖人の 729回目の ご命日です(実際は10月13日)。
10:30 法要

開式を告げる 鐘

お坊さん 計7名の 豪華な(?)法要になりました。

11:10 法話

今年の 法話は 常境寺の 金森了脩上人 をお招きいたしました。

金森上人 は私のお師匠さん。
私は 父を師匠として 出家しましたが、 翌年 修行途中で 遷化。
そこで 近くに在って 私を厳しく指導してくださる方に と 私からお願いし 引き受けていただきました。 年齢は 私よりも 2回りもお若いのですが 大変立派な お坊さんです。
その金森上人(身延山大学=日蓮宗本山の大学、の講師でもある)から 今年 大学の学生さんを引率し ガダルカナル島に行ってきた話をしていただきました。
ガダルカナル島は 言うまでもなく 先の大戦の激戦地。
36,204名の兵を投入し、戦死10,600名、餓死・戦病死15,000名(資料=ウィキペディア)と、それまで負け知らずだった日本軍が、全滅的敗戦を喫した地でもあります。
私も初めて知ったのですが
この島に 残砲弾という 帝国陸軍が残した大量の砲弾が存在し、それによって 島の住民が今も 傷つき、命を奪われるという現実があるのだそうです。
学生さんたちにも それぞれ 感想を話していただきました。


現地に赴いて 実際に 残砲弾を処理し、遺骨を収集し、慰霊祭を行ってきたお話。
平和な日本に住む私たちに 改めて いのち・幸福 等について考える機会を与えていただきました。
12:10 お食事
庫裏の 襖を外して 皆で食事をします。
興徳寺名物 味付けご飯 と 竹の子の煮物(春の竹の子を塩で保存しておいたもの)

実に 素朴な食事ではありますが とってもオイシイ! ・・・と思います。
* 常境寺のご好意で 今回の ガダルカナル島残砲弾処理を 記録した ドキュメンタリーDVD「命 輝き(109分)」を、お会式に参列の檀家さんに配布していただきました。 私の手元にまだ若干数ありますので、ご希望の方に差し上げます。メールにて お申し込みください。

日蓮聖人の 729回目の ご命日です(実際は10月13日)。
10:30 法要

開式を告げる 鐘

お坊さん 計7名の 豪華な(?)法要になりました。

11:10 法話

今年の 法話は 常境寺の 金森了脩上人 をお招きいたしました。

金森上人 は私のお師匠さん。
私は 父を師匠として 出家しましたが、 翌年 修行途中で 遷化。
そこで 近くに在って 私を厳しく指導してくださる方に と 私からお願いし 引き受けていただきました。 年齢は 私よりも 2回りもお若いのですが 大変立派な お坊さんです。
その金森上人(身延山大学=日蓮宗本山の大学、の講師でもある)から 今年 大学の学生さんを引率し ガダルカナル島に行ってきた話をしていただきました。
ガダルカナル島は 言うまでもなく 先の大戦の激戦地。
36,204名の兵を投入し、戦死10,600名、餓死・戦病死15,000名(資料=ウィキペディア)と、それまで負け知らずだった日本軍が、全滅的敗戦を喫した地でもあります。
私も初めて知ったのですが
この島に 残砲弾という 帝国陸軍が残した大量の砲弾が存在し、それによって 島の住民が今も 傷つき、命を奪われるという現実があるのだそうです。
学生さんたちにも それぞれ 感想を話していただきました。


現地に赴いて 実際に 残砲弾を処理し、遺骨を収集し、慰霊祭を行ってきたお話。
平和な日本に住む私たちに 改めて いのち・幸福 等について考える機会を与えていただきました。
12:10 お食事
庫裏の 襖を外して 皆で食事をします。
興徳寺名物 味付けご飯 と 竹の子の煮物(春の竹の子を塩で保存しておいたもの)

実に 素朴な食事ではありますが とってもオイシイ! ・・・と思います。
* 常境寺のご好意で 今回の ガダルカナル島残砲弾処理を 記録した ドキュメンタリーDVD「命 輝き(109分)」を、お会式に参列の檀家さんに配布していただきました。 私の手元にまだ若干数ありますので、ご希望の方に差し上げます。メールにて お申し込みください。
Posted by kotokuji at
21:54
│Comments(0)
2010年11月13日
小諸なる古城のほとり
昨日までの 1泊2日、長野県 上田市~小諸に行ってきました。
バイクの免許を取って ちょうど2年、初めてのツーリングです。 前日まで ウキウキ・ドキドキ でしたが、スタートしてしまえば 快調そのもの。 秋の信濃路は 紅葉の真っ盛り、おまけに雲ひとつないドピーカン(意味分かるかな~?)、あまりの美しさに興奮して 絶叫しながら走っていました。
 上田の友人の実家の お仏壇にて お経をあげさせていただき、その後 墓参。
上田の友人の実家の お仏壇にて お経をあげさせていただき、その後 墓参。
永年の思いを やっと果たす事ができました。
友人は 石井さんというのですが 美容師でした。
単身ブラジルに渡り、苦労の末 美容院7店のオーナーに、
建築屋であった私は 彼の店舗のすべてを施工させてもらいました。
私のことをよく理解してくれた かけがえのない友でありました。
さて、ここまで来たので これまた 永年の夢であった 小諸へ・・・
高校1年、現代国語の教科書の最初のページが 島崎藤村の『千曲川旅情のうた』でした。
「小諸なる古城のほとり雲白く 遊子悲しむ・・・」で始まるこの詩を そらんじ、折にふれては思い出し、いつかは 小諸に行って千曲川を見たい、と思っていました。
 それで 藤村が宿泊したといわれる 旅館『中棚荘』を予約し、まずは 古城=小諸城址に行ってみました。 今は「懐古園」という 公園になっています。
それで 藤村が宿泊したといわれる 旅館『中棚荘』を予約し、まずは 古城=小諸城址に行ってみました。 今は「懐古園」という 公園になっています。
ここも 紅葉の真っ盛り!

顔が 赤く染まりそうです。


茶店で 一休み。
『中棚荘』の玄関。 左側は 藤村の時代のもの、出入りはしていないが 今もそのまま保存されている。
右は今の玄関。



お風呂もとってもよかった。
脱衣場が畳。
その向こうに リンゴの浮いている お風呂。
宿の スタッフ全員が とっても感じがよくって、
料理もうまいし
おススメの宿です。


そして 憧れの「千曲川」 と 出会った。
ムカシのままの川、というイメージ。
藤村が 見た川も このままのものだっただろうか?
何だか とても懐かしく、しみじみと感動しました。

もうひとつ、「千曲川」で忘れられないのは、高校3年の時観た『千曲川絶唱』という映画。
当時 清純女優だった 星百合子の初ヌードシーンが見られるという、いささか不純な動機だったが、白血病で死んでゆく 主人公の 暴れん坊のダンプ運転手、北大路欣也の最後の願い、星百合子 演じる恋人の看護婦に「ナミちゃん、君を見たいんだ・・・」 すべてを悟った ナミちゃんが、サラリと白衣を脱ぐ・・・ 逆光、カーテンの向こうで シルエットのみ・・・(思わずため息・・あ~ッ)
「きれいだよ、ナミちゃん、 南の海で見た 人魚みたいだ・・・」(またまた ため息・・う~ンッ)
遺言で ナミちゃんが 遺骨を千曲川に 流すシーンで the end でした。
40年以上前に、1度だけ観た映画なのに 今だにくっきりと思い出します(白黒映画でした)。

信濃路は どこまで行っても どこまで行っても 里山全体が紅葉している。
何気ない風景の どこそこ美しい。 それだけで感動します。
ミキオちゃんが 夢中になるのも 良く分かる。
明日は お会式です。
準備は 万端! ・・・だと思う。
バイクの免許を取って ちょうど2年、初めてのツーリングです。 前日まで ウキウキ・ドキドキ でしたが、スタートしてしまえば 快調そのもの。 秋の信濃路は 紅葉の真っ盛り、おまけに雲ひとつないドピーカン(意味分かるかな~?)、あまりの美しさに興奮して 絶叫しながら走っていました。
 上田の友人の実家の お仏壇にて お経をあげさせていただき、その後 墓参。
上田の友人の実家の お仏壇にて お経をあげさせていただき、その後 墓参。永年の思いを やっと果たす事ができました。
友人は 石井さんというのですが 美容師でした。
単身ブラジルに渡り、苦労の末 美容院7店のオーナーに、
建築屋であった私は 彼の店舗のすべてを施工させてもらいました。
私のことをよく理解してくれた かけがえのない友でありました。
さて、ここまで来たので これまた 永年の夢であった 小諸へ・・・
高校1年、現代国語の教科書の最初のページが 島崎藤村の『千曲川旅情のうた』でした。
「小諸なる古城のほとり雲白く 遊子悲しむ・・・」で始まるこの詩を そらんじ、折にふれては思い出し、いつかは 小諸に行って千曲川を見たい、と思っていました。
 それで 藤村が宿泊したといわれる 旅館『中棚荘』を予約し、まずは 古城=小諸城址に行ってみました。 今は「懐古園」という 公園になっています。
それで 藤村が宿泊したといわれる 旅館『中棚荘』を予約し、まずは 古城=小諸城址に行ってみました。 今は「懐古園」という 公園になっています。ここも 紅葉の真っ盛り!

顔が 赤く染まりそうです。


茶店で 一休み。
『中棚荘』の玄関。 左側は 藤村の時代のもの、出入りはしていないが 今もそのまま保存されている。
右は今の玄関。



お風呂もとってもよかった。
脱衣場が畳。
その向こうに リンゴの浮いている お風呂。
宿の スタッフ全員が とっても感じがよくって、
料理もうまいし
おススメの宿です。


そして 憧れの「千曲川」 と 出会った。
ムカシのままの川、というイメージ。
藤村が 見た川も このままのものだっただろうか?
何だか とても懐かしく、しみじみと感動しました。

もうひとつ、「千曲川」で忘れられないのは、高校3年の時観た『千曲川絶唱』という映画。
当時 清純女優だった 星百合子の初ヌードシーンが見られるという、いささか不純な動機だったが、白血病で死んでゆく 主人公の 暴れん坊のダンプ運転手、北大路欣也の最後の願い、星百合子 演じる恋人の看護婦に「ナミちゃん、君を見たいんだ・・・」 すべてを悟った ナミちゃんが、サラリと白衣を脱ぐ・・・ 逆光、カーテンの向こうで シルエットのみ・・・(思わずため息・・あ~ッ)
「きれいだよ、ナミちゃん、 南の海で見た 人魚みたいだ・・・」(またまた ため息・・う~ンッ)
遺言で ナミちゃんが 遺骨を千曲川に 流すシーンで the end でした。
40年以上前に、1度だけ観た映画なのに 今だにくっきりと思い出します(白黒映画でした)。

信濃路は どこまで行っても どこまで行っても 里山全体が紅葉している。
何気ない風景の どこそこ美しい。 それだけで感動します。
ミキオちゃんが 夢中になるのも 良く分かる。
明日は お会式です。
準備は 万端! ・・・だと思う。
Posted by kotokuji at
21:05
│Comments(0)
2010年11月10日
参道・駐車場
元 土建屋だからか 工事が 大好き!
小さな工事を 2本、 同時進行させていたのですが このたび 完成しました。

ひとつは 本堂前の参道です。
古いコンクリートは それなりの 風情でしたが
この段差が 気になる・・・
歩くのに つかえる、というのではなく
本堂前の空間が 分断される。
というところが・・・
全部 壊して 地面と同じ高さにし、
御影石を貼りました。
たまたま 高校時代の クラブの後輩が石材店をやっていて
半額以下という破格値で 請け負ってくれました。


(before~after)


おかげで 本堂前が 広くなりました。
三明石材さん、 ありがとうございました。
もうひとつは 駐車場。
養豚をやっていた 檀家さんの 豚舎の跡地を そのまま 安く譲ってもらい、興徳寺の第二駐車場としました。
50台は楽に入ると思います。
今まで イベントの時は 学校のグラウンドを駐車場として 借りていたのですが、これで一安心です。
(before)
(after)
(before~after)


(before~after)


――― 明日から 長野の上田市に行って来ます。
ブラジル時代の親友のお墓参り。
3年前に亡くなって 遺言で実家の お墓に埋骨されました。
ずっと気になっていたのですが 住所が分からず・・・
それが 先週、書棚の古いノートを 何気なく抜き取って パラッとめくったら 何とそこに 彼の唯一の肉親である 福島在住の お姉さんの 電話番号が・・・
そういえば あの頃 一度だけ 電話をもらったことがあったっけ、 と思い出しました。
バイクの一人旅・・・ 何となく ウキウキ・ドキドキです。
小さな工事を 2本、 同時進行させていたのですが このたび 完成しました。

ひとつは 本堂前の参道です。
古いコンクリートは それなりの 風情でしたが
この段差が 気になる・・・
歩くのに つかえる、というのではなく
本堂前の空間が 分断される。
というところが・・・
全部 壊して 地面と同じ高さにし、
御影石を貼りました。
たまたま 高校時代の クラブの後輩が石材店をやっていて
半額以下という破格値で 請け負ってくれました。


(before~after)


おかげで 本堂前が 広くなりました。
三明石材さん、 ありがとうございました。
もうひとつは 駐車場。
養豚をやっていた 檀家さんの 豚舎の跡地を そのまま 安く譲ってもらい、興徳寺の第二駐車場としました。
50台は楽に入ると思います。
今まで イベントの時は 学校のグラウンドを駐車場として 借りていたのですが、これで一安心です。
(before)

(after)

(before~after)


(before~after)


――― 明日から 長野の上田市に行って来ます。
ブラジル時代の親友のお墓参り。
3年前に亡くなって 遺言で実家の お墓に埋骨されました。
ずっと気になっていたのですが 住所が分からず・・・
それが 先週、書棚の古いノートを 何気なく抜き取って パラッとめくったら 何とそこに 彼の唯一の肉親である 福島在住の お姉さんの 電話番号が・・・
そういえば あの頃 一度だけ 電話をもらったことがあったっけ、 と思い出しました。
バイクの一人旅・・・ 何となく ウキウキ・ドキドキです。
Posted by kotokuji at
21:14
│Comments(0)
2010年11月07日
おわた
来週 日曜日(14日)は 興徳寺の お会式です。
お会式とは、日蓮聖人がお亡くなりになられた日(ご入滅の忌日)に営む法要です。もともとの「お会式」の意味は「法会の儀式」の略語であり、日蓮宗に限ったものではありませんが、現在の日蓮聖人の忌日に行う報恩会の事を指すことになっています。 (興徳寺HPより)
妹たちにも手伝ってもらい 本堂の準備を始めました。
興徳寺所蔵の 軸を 毎年1回 風通しも兼ねて 展示します。

ほとんどが 曼荼羅ご本尊で かなり古いものも含めて20数幅。

もっとも 大きなものが この 「釈迦涅槃像」で、かなり傷んでいたようですが、先代住職の代に 百数十万円かけて 修復されました。

興徳寺は 日蓮宗のお寺で、本堂の中心に 祖師像(そしぞう=宗祖日蓮聖人の彫塑像)が 安置されていますが この像に 綿帽子を おつけします。
これは 文永元年十一月十一日の夕方、日蓮聖人が、安房の国東條郡小松原で、地頭東條景信の襲撃を受け額に傷を受けられた(世にいう 『小松原法難』)、 その時、不思議な老婆が現れ、傷を寒さから守るために 当時尊かった真綿を供養した・・・ という故事にもとづいています。
タイトルの「おわた」とは この綿帽子のこと、 内側が赤いのは その時 流れた 血 を表します。

日蓮聖人というと 一般に 独善的 とか 排他的とかいうイメージがあるようですが 実はとっても優しい方です。 それは 今なお残る お弟子さんや 信者さんに 宛てられた膨大なお手紙の文面から察することができます。
私たちは 親しみを込めて 「お祖師様(おそっしさま)」と呼びます。
私は 毎朝 お勤めの後 興徳寺の 「お祖師さま」とお話をします。
たいていは 微笑で応えてくれますが
「どうして そんな アホなこというの?」という 困ったようなお顔が返ってくることがあります。
お会式とは、日蓮聖人がお亡くなりになられた日(ご入滅の忌日)に営む法要です。もともとの「お会式」の意味は「法会の儀式」の略語であり、日蓮宗に限ったものではありませんが、現在の日蓮聖人の忌日に行う報恩会の事を指すことになっています。 (興徳寺HPより)
妹たちにも手伝ってもらい 本堂の準備を始めました。
興徳寺所蔵の 軸を 毎年1回 風通しも兼ねて 展示します。

ほとんどが 曼荼羅ご本尊で かなり古いものも含めて20数幅。

もっとも 大きなものが この 「釈迦涅槃像」で、かなり傷んでいたようですが、先代住職の代に 百数十万円かけて 修復されました。

興徳寺は 日蓮宗のお寺で、本堂の中心に 祖師像(そしぞう=宗祖日蓮聖人の彫塑像)が 安置されていますが この像に 綿帽子を おつけします。
これは 文永元年十一月十一日の夕方、日蓮聖人が、安房の国東條郡小松原で、地頭東條景信の襲撃を受け額に傷を受けられた(世にいう 『小松原法難』)、 その時、不思議な老婆が現れ、傷を寒さから守るために 当時尊かった真綿を供養した・・・ という故事にもとづいています。
タイトルの「おわた」とは この綿帽子のこと、 内側が赤いのは その時 流れた 血 を表します。

日蓮聖人というと 一般に 独善的 とか 排他的とかいうイメージがあるようですが 実はとっても優しい方です。 それは 今なお残る お弟子さんや 信者さんに 宛てられた膨大なお手紙の文面から察することができます。
私たちは 親しみを込めて 「お祖師様(おそっしさま)」と呼びます。
私は 毎朝 お勤めの後 興徳寺の 「お祖師さま」とお話をします。
たいていは 微笑で応えてくれますが
「どうして そんな アホなこというの?」という 困ったようなお顔が返ってくることがあります。
Posted by kotokuji at
20:37
│Comments(0)
2010年11月04日
富士山五合目 雲の上
本日は 午前中はお葬式。 午後から お寺の会計処理をやるつもりでいたのですが あんまりにもイイ天気だったので 急に思いついて 富士山の五合目(富士宮側登山口)まで行って来ました。
興徳寺から五合目までは 車で約1時間という距離です。
登るにしたがって 紅葉が進み 三合目くらいの地点が見ごろ、終点の五合目ではピークを過ぎていました。
五合目から見た富士山頂

白い部分が頂上の雪
遠くから眺めるのとは まったく違うフンイキですね。
このあたりが 標高 2500m。 ここから頂上まで 高低差で1200m。 体力・歩くペースにもよりますが 5~7時間くらいでしょうか。
山の天気は あっという間に変わる、
霧が下から湧き上がる・・・

目を転ずれば 五合目は雲の上。


・・・最近興味をもっている お話・・・
「雲の上でママを みていた ときのこと」 という本があります。 著者は 池川 明さんという産科医です。
産科医として、お産や子育てに役立つようにと 胎内記憶・誕生記憶の調査を続けている私は、聞き取りを重ねるうち、不思議な記憶をもつ子どもたちと出会うようになりました。
それはおなかにやどる前の記憶です。
子どもたちは、おなかにやどる前、
雲の上で天使や妖精やかみさまと暮らしていたと話します。
子どもたちは、世界中をぐるりと見回して
たったひとり、すてきな女の人を見つけ出します。
それがかけがえのない、大好きなおかあさんなのです。
リヨン社 「雲の上でママを みていた ときのこと」より抜粋
私たちは 生まれる前 雲の上にいて 自分で母親を選んできた・・・
だとしたら 「何で オレなんか生んだんだ~」とゴネたり
「こんなんじゃ 生まれてこなきゃヨカッタ」などと嘆いたり
「こんな風に生んでしまって カワイソウなことをした」 と母親が自らを責めたり、ということは
全くナンセンスということになります。
仏様の国から
自分の意思で両親を選び
それなりの苦労もし 喜びを知り 魂を磨き上げて
また仏様の国に 帰っていく・・・ こんな考え方が 今の私の バックボーンです。

興徳寺から五合目までは 車で約1時間という距離です。
登るにしたがって 紅葉が進み 三合目くらいの地点が見ごろ、終点の五合目ではピークを過ぎていました。
五合目から見た富士山頂

白い部分が頂上の雪
遠くから眺めるのとは まったく違うフンイキですね。
このあたりが 標高 2500m。 ここから頂上まで 高低差で1200m。 体力・歩くペースにもよりますが 5~7時間くらいでしょうか。
山の天気は あっという間に変わる、
霧が下から湧き上がる・・・

目を転ずれば 五合目は雲の上。


・・・最近興味をもっている お話・・・
「雲の上でママを みていた ときのこと」 という本があります。 著者は 池川 明さんという産科医です。
産科医として、お産や子育てに役立つようにと 胎内記憶・誕生記憶の調査を続けている私は、聞き取りを重ねるうち、不思議な記憶をもつ子どもたちと出会うようになりました。
それはおなかにやどる前の記憶です。
子どもたちは、おなかにやどる前、
雲の上で天使や妖精やかみさまと暮らしていたと話します。
子どもたちは、世界中をぐるりと見回して
たったひとり、すてきな女の人を見つけ出します。
それがかけがえのない、大好きなおかあさんなのです。
リヨン社 「雲の上でママを みていた ときのこと」より抜粋
私たちは 生まれる前 雲の上にいて 自分で母親を選んできた・・・
だとしたら 「何で オレなんか生んだんだ~」とゴネたり
「こんなんじゃ 生まれてこなきゃヨカッタ」などと嘆いたり
「こんな風に生んでしまって カワイソウなことをした」 と母親が自らを責めたり、ということは
全くナンセンスということになります。
仏様の国から
自分の意思で両親を選び
それなりの苦労もし 喜びを知り 魂を磨き上げて
また仏様の国に 帰っていく・・・ こんな考え方が 今の私の バックボーンです。

Posted by kotokuji at
21:14
│Comments(0)
2010年11月01日
我他彼此
1昨日の土曜日は台風14号が 接近していたので 場合によっては 本堂に雨戸を立てようかと思っていました。 幸いにも 風雨とも大したこともなく その必要もありませんでしたが、戸が古いので スムーズに動かず 少々手間取ります。
翌日、つまりは昨日ですが ふっと思いついて これを法話の ネタにしてやろうと 法事の後、
我他彼此 と ホワイトボードに書いて 「さぁ~ッ 何と読むでしょう?」
・・・誰も答えられない。
「これは ガタピシ と読みます。 古い戸が 良く動かない事を ガタピシいう などといいますね、 これは 我=オレだとか 他=オマエだとか あるいは 彼=アイツ(が悪い) だとか 此=コイツ(が悪い) だとか お互いが譲らずに ギクシャクしている様子 からきているんです」と言ったら ある程度の年齢の人たちは 「ヘエ~ツ」と喜んでくれましたが 若い人は ポカンとしている。 恐る恐る 「意味 分かりますよね?」と聞いたら 「よく解らない・・・」
聞いてみると、たてつけの悪い ガタピシするような戸など いまどき どこにも無く したがって そんな言葉も聞いたことがないとのこと。 雨戸というものさえ知りませんでした。
「それじゃあ 機械が古くなって ガタがきた という言葉は? ここからきているんだけど・・・」というと、 「アァ その言葉なら聞いたことがある」と 少し納得してくれました。
それで法話の後、雨戸を 引き出して見せてあげました。


興徳寺の本堂は 今だ 木のガラス戸です。
私が幼い頃、庫裏には ガラス戸はなく 障子の向こうは縁側で、毎晩 雨戸を引くのが私の役目。
これが それこそ ガタピシで 苦労しました。
朝日が射すと 節穴を通して 外の景色が逆さまに 障子に映る。 針穴写真機の原理ですが カラーの風景写真が いくつも 障子に広がる様は とっても不思議で幻想的でした。
ガタピシの言葉とともに 消え去ってしまうのでしょうか・・・
ところでこの「我他彼此」、仏教を説明する言葉として 使われます。
私たちは とかく 右か左か、とか 白か黒か、というように 物事を決め付けたがる。 しかし 絶対的な 右だとか 絶対的な白 というものはないのです。 仏教の根本思想である「中道」という考え方は、両極端にとらわれないこと、絶対、と決め付けないこと を基本とします。
自分にできたことを他人に押し付ける、 できるはずだと決め付ける。 あるいは じぶんが かつてできたことが できなくなると こんなはずじゃなかった と落ち込む・・・ それは 若くて体力があった頃の自分が 最高!と決め付けるからです。
「そんな風に ガタピシいわせて生きるより 執着から 離れて 柔軟に生きる事が 大切ですよ。」 と お釈迦様が 教えてくれました。
石蕗(つわぶき)


池の周りの 石蕗の花が 満開。
「アタシが 嫁に 来た時には もうここで咲いてたよ」
と 母が ぽつり・・・

本日、久しぶりに 富士山が 顔を出してくれました。
頭にチョコッと 雪を載せ 何ともイジラシイ・・・
翌日、つまりは昨日ですが ふっと思いついて これを法話の ネタにしてやろうと 法事の後、
我他彼此 と ホワイトボードに書いて 「さぁ~ッ 何と読むでしょう?」
・・・誰も答えられない。
「これは ガタピシ と読みます。 古い戸が 良く動かない事を ガタピシいう などといいますね、 これは 我=オレだとか 他=オマエだとか あるいは 彼=アイツ(が悪い) だとか 此=コイツ(が悪い) だとか お互いが譲らずに ギクシャクしている様子 からきているんです」と言ったら ある程度の年齢の人たちは 「ヘエ~ツ」と喜んでくれましたが 若い人は ポカンとしている。 恐る恐る 「意味 分かりますよね?」と聞いたら 「よく解らない・・・」
聞いてみると、たてつけの悪い ガタピシするような戸など いまどき どこにも無く したがって そんな言葉も聞いたことがないとのこと。 雨戸というものさえ知りませんでした。
「それじゃあ 機械が古くなって ガタがきた という言葉は? ここからきているんだけど・・・」というと、 「アァ その言葉なら聞いたことがある」と 少し納得してくれました。
それで法話の後、雨戸を 引き出して見せてあげました。


興徳寺の本堂は 今だ 木のガラス戸です。
私が幼い頃、庫裏には ガラス戸はなく 障子の向こうは縁側で、毎晩 雨戸を引くのが私の役目。
これが それこそ ガタピシで 苦労しました。
朝日が射すと 節穴を通して 外の景色が逆さまに 障子に映る。 針穴写真機の原理ですが カラーの風景写真が いくつも 障子に広がる様は とっても不思議で幻想的でした。
ガタピシの言葉とともに 消え去ってしまうのでしょうか・・・
ところでこの「我他彼此」、仏教を説明する言葉として 使われます。
私たちは とかく 右か左か、とか 白か黒か、というように 物事を決め付けたがる。 しかし 絶対的な 右だとか 絶対的な白 というものはないのです。 仏教の根本思想である「中道」という考え方は、両極端にとらわれないこと、絶対、と決め付けないこと を基本とします。
自分にできたことを他人に押し付ける、 できるはずだと決め付ける。 あるいは じぶんが かつてできたことが できなくなると こんなはずじゃなかった と落ち込む・・・ それは 若くて体力があった頃の自分が 最高!と決め付けるからです。
「そんな風に ガタピシいわせて生きるより 執着から 離れて 柔軟に生きる事が 大切ですよ。」 と お釈迦様が 教えてくれました。
石蕗(つわぶき)


池の周りの 石蕗の花が 満開。
「アタシが 嫁に 来た時には もうここで咲いてたよ」
と 母が ぽつり・・・

本日、久しぶりに 富士山が 顔を出してくれました。
頭にチョコッと 雪を載せ 何ともイジラシイ・・・
Posted by kotokuji at
20:52
│Comments(0)