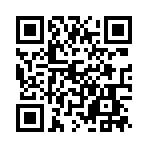2011年06月28日
妻の七回忌
一昨日は 妻の 「七回忌法要」でした。
七回忌ともなれば 身内でささやかに・・・ という方も多いですが 妻と仲がよかった方たちに、それなりに 遠慮がちに ご案内を差し上げたところ、 関東方面から数名、西は広島からも 来てくださって 総勢50余名・・・
ただ 感謝、です。

妻の 好きだった 白百合や ひまわりの花、 それに好物の ドラヤキや ミカンが 差し入れられ、 にぎやかで 暖かな 法要になりました。

妻のことは 昨年のブログに 書いたので 興味ある方は 覗いてください。
http://kotokuji.eshizuoka.jp/e583366.html
ブラジルで私は 小さな建築会社を経営していました。
2年目に 経営トラブルに陥り それからの足掛け10年は まさに自転車操業、 いつ倒産してもおかしくないような状態で 何とか保っていたのですが そんな時 妻はいつも 私を励ましてくれるのです、
それも具体的な言葉で・・・
「ダイジョウブよ! 会社は もうちょっとで よくなるから」
「ケンちゃん(私のこと)は 50歳を過ぎると 一気によくなるヨ」
霊感体質で 占いが大好き、私は 嫌いなので 聞いて聞かぬふり、 でも正直言って よく当っていた・・・
そして 励ましの言葉の後、 不思議な言葉を つぶやく・・・
「本当は お坊さんになるのが 一番いいんだけどネ~」
・・・それだけは どんなに想像しても 考えられない事でした。
ブラジルでは もちろん まして日本でなど 夢のまた夢・・・
前に紹介した(5月8日) ユメちゃんhttp://kotokuji.eshizuoka.jp/e720680.htmlこと 岡澤優明子さんも 裾野市から 来てくれました。
妻は 亡くなった年の1月、私の得度式に出席するため ブラジルから来ていたのですが、そのとき ユメちゃんが訪ねてくれました。 初めて出会ったのに 二人は意気投合し、 私をそっちのけで 延々と話が弾んでいました。

(右から 3番目が
ユメちゃん)
妻が 亡くなった後、ユメちゃんからいただいた メール。
― 前半略 ―
彼女は今、ブラジルではなく、あなたのそばにいます。
彼女の大きな愛が選択したのです。
悲しみは時とともに薄らぎますが、淋しさはときどきあなたを苦しめるかもしれません。
彼女は言いました。
「私が一緒にいたら彼の修業を長引かせます。彼は破れた足袋は自分でつくろい、寒い夜明けの掃除に耐えねばなりません。それが修業です。私はそれをあえて手伝わない選択をしました。早く一人前になる必要があるからです。私たちは空港でチャオ、さよならといって抱き合いました-。」

彼女はみごとにあなたを自立させて逝きましたね。
でもあなたのそばにいたかったのでしょう。
これからはあなたのそばで、ずっと続く修業の道を、導き助けて行くでしょう。
この寂しさをとおり抜けることが、彼女がくれた卒業試験かもしれません。
泰然さん、あなたには彼女のほかにも、たくさんの仲間がいますよ。
愛と勇気をおくります
ゆめこ
当時の 私には理解できなかったことが ひとつひとつ 形になり、 今、 妻の七回忌の導師を私が 務める・・・ すべては 完璧なシナリオの通りです。

本当は 昨日から明日までの3日間は 北海道に滞在しているはずでした。
妻と5年間過ごした 最北の地 天塩郡幌延町問寒別(といかんべつ)。 ここを33年ぶりに訪ねる事にし、かつての同僚、 ハラちゃん にも札幌から来てもらい、 加藤のオッカアこと 私の測量助手をずっと務めてくれた 加藤幸子さんにも会う段取りだったのです。
友人のオネエサンのご主人が亡くなり、 「その日が来たら、ケンちゃんにお願いしようと ずっと決めていたの」 とお姉さんからの電話。 友人の実家も ご主人の實家も他宗なのに・・・です。 ありがたく お受けいたしました。
お寺の宿命です。
母には ショートステイに行ってもらったので 私ひとり の夜です。
七回忌ともなれば 身内でささやかに・・・ という方も多いですが 妻と仲がよかった方たちに、それなりに 遠慮がちに ご案内を差し上げたところ、 関東方面から数名、西は広島からも 来てくださって 総勢50余名・・・
ただ 感謝、です。

妻の 好きだった 白百合や ひまわりの花、 それに好物の ドラヤキや ミカンが 差し入れられ、 にぎやかで 暖かな 法要になりました。

妻のことは 昨年のブログに 書いたので 興味ある方は 覗いてください。
http://kotokuji.eshizuoka.jp/e583366.html
ブラジルで私は 小さな建築会社を経営していました。
2年目に 経営トラブルに陥り それからの足掛け10年は まさに自転車操業、 いつ倒産してもおかしくないような状態で 何とか保っていたのですが そんな時 妻はいつも 私を励ましてくれるのです、
それも具体的な言葉で・・・
「ダイジョウブよ! 会社は もうちょっとで よくなるから」
「ケンちゃん(私のこと)は 50歳を過ぎると 一気によくなるヨ」
霊感体質で 占いが大好き、私は 嫌いなので 聞いて聞かぬふり、 でも正直言って よく当っていた・・・
そして 励ましの言葉の後、 不思議な言葉を つぶやく・・・
「本当は お坊さんになるのが 一番いいんだけどネ~」
・・・それだけは どんなに想像しても 考えられない事でした。
ブラジルでは もちろん まして日本でなど 夢のまた夢・・・
前に紹介した(5月8日) ユメちゃんhttp://kotokuji.eshizuoka.jp/e720680.htmlこと 岡澤優明子さんも 裾野市から 来てくれました。
妻は 亡くなった年の1月、私の得度式に出席するため ブラジルから来ていたのですが、そのとき ユメちゃんが訪ねてくれました。 初めて出会ったのに 二人は意気投合し、 私をそっちのけで 延々と話が弾んでいました。

(右から 3番目が
ユメちゃん)
妻が 亡くなった後、ユメちゃんからいただいた メール。
― 前半略 ―
彼女は今、ブラジルではなく、あなたのそばにいます。
彼女の大きな愛が選択したのです。
悲しみは時とともに薄らぎますが、淋しさはときどきあなたを苦しめるかもしれません。
彼女は言いました。
「私が一緒にいたら彼の修業を長引かせます。彼は破れた足袋は自分でつくろい、寒い夜明けの掃除に耐えねばなりません。それが修業です。私はそれをあえて手伝わない選択をしました。早く一人前になる必要があるからです。私たちは空港でチャオ、さよならといって抱き合いました-。」

彼女はみごとにあなたを自立させて逝きましたね。
でもあなたのそばにいたかったのでしょう。
これからはあなたのそばで、ずっと続く修業の道を、導き助けて行くでしょう。
この寂しさをとおり抜けることが、彼女がくれた卒業試験かもしれません。
泰然さん、あなたには彼女のほかにも、たくさんの仲間がいますよ。
愛と勇気をおくります
ゆめこ
当時の 私には理解できなかったことが ひとつひとつ 形になり、 今、 妻の七回忌の導師を私が 務める・・・ すべては 完璧なシナリオの通りです。

本当は 昨日から明日までの3日間は 北海道に滞在しているはずでした。
妻と5年間過ごした 最北の地 天塩郡幌延町問寒別(といかんべつ)。 ここを33年ぶりに訪ねる事にし、かつての同僚、 ハラちゃん にも札幌から来てもらい、 加藤のオッカアこと 私の測量助手をずっと務めてくれた 加藤幸子さんにも会う段取りだったのです。
友人のオネエサンのご主人が亡くなり、 「その日が来たら、ケンちゃんにお願いしようと ずっと決めていたの」 とお姉さんからの電話。 友人の実家も ご主人の實家も他宗なのに・・・です。 ありがたく お受けいたしました。
お寺の宿命です。
母には ショートステイに行ってもらったので 私ひとり の夜です。
Posted by kotokuji at
20:34
│Comments(0)
2011年06月25日
ブログ記念日

「この味いいね」と君が言ったから
七月六日は サラダ記念日
歌人 俵万智さんが 1987年に出版した
歌集「サラダ記念日」より
この歌集をブラジルで読んだときは 感動しました。
今でこそ このような自由な発想の短歌も 珍しくはありませんが、 当時としては 本当に衝撃的で 石川啄木に憧れていた私の 短歌への イメージが 大きく変わりました。
さて 私のブログが 本日 6月25日で ちょうど一年になりました。
いうなれば本日は「ブログ記念日」です。
ブログのスタートは こんな感じです。
ホームページ開設にあたり
念願であったホームページがようやく開設の運びとなりました。 これまで『興徳寺便り』という 檀家さん宛ての寺報の中で、自分なりのメッセージを伝えてきたつもりですが、インターネットという とてつもなくオープンな場に曝け出してしまうことは、正直いって 怖い・・・ でも 私の第二のふるさとであるブラジルや、友人が住む アメリカ・ペルー・マレーシア・中国・・・はてまた息子の住むオーストラリアなど世界中にメッセージが届けられるということは、とってもワクワクします。
記念すべき 初日に何か しゃれた言葉でもと 考えても何も浮かばず・・・
ワールドカップの寝不足のせいか?
気負わずにここから スタートします。
泰然
当時は 写真を添付する方法も知らず ただこれだけ(最初の数回は 文章だけでした)。
それも 書き始めて 何かの操作を間違えて 全部最初から やりなおし・・・ を何度繰り返した事か。 やがて 写真を貼り付けることを覚え、 読者の数もボチボチ増えて・・
「読んでますヨ~」などと言われると とても嬉しくて、 それだけで 今日まで 続けてこられたような気がします。


さて 本日の 冒頭の写真、
記念すべきこの日を ブラジリアン・サラダ で飾ってみました。
(ブラジルで読んでくださっている皆さん! E aprovado?
こんなもんで どう?)
Salada misto (サラダ・ミスト=ミックス・サラダ)
材料;レタス、トマト、人参・ジャガイモ・インゲンの茹でたもの、ゆで卵 等を適当に・・
画面上 缶詰の白いアスパラのようなものは、パルミット という ブラジル産 椰子の木の芯の柔らかい部分、説明が難しいが ブラジルでは まったくポピュラーな ちょい高級食材で、これは絶対 欲しい。
ドレッシングは 簡単明瞭、 オリーブオイルと 塩と 酢、好みで胡椒を少々、 これだけです。
単純ながら 素材の味がよくでて 本当に美味!
思わず「Saudade!(サウダージ)」と 叫んでしまいました。
(私の大好きなこの言葉、 ぴったりの日本語がない、 とっても、とっても懐かしいこと・・・)

「山寺の和尚さん日記」 これからも 続けていきます。 ご声援、ヨロシク。
明日は 妻の「七回忌法要」です。
Posted by kotokuji at
20:14
│Comments(0)
2011年06月22日
がんばれ という言葉
1昨日朝、東京の檀家さんの 訃報を受け取り 東京へ枕経に行き、 一旦戻って、昨日昼に再度出発、
通夜~本日の葬儀を執り行って 夕方帰宅しました。 あっという間の 3日間でした。
さて 今回の東北のことを 少し。
3・11 で 亡くなられた方々の遺体ですが・・・
火葬場の処理能力を大きく上回る数の遺体を 遺族の了解を取った上で、いったん土葬して、後に火葬する 「仮埋葬」 という苦渋の対応がとられました。
15日、ボランティア作業が終わった夕刻、東松島市の 「仮埋葬所」 を訪問しました。
ズラッと並んだ 白木の墓標に 圧倒され、否応もない現実に 最初に被災地を見たときのショックが 蘇ります。


ベニヤ板で 仕切っただけのスペースに
埋葬します

身元不明者の遺体も

通路を縫って
お経をあげさせていただきました。
ここを管理する 市役所の方が来てくれて お話を伺うことができました。
ここに 仮埋葬された遺体は 400体近く、 火葬所の処理能力から 1日2体づつ 順番に火葬を進め、
現在190体が 残っているとのこと。
完全に終わるのは まだ当分先のことです。

地元の新聞には 100日が過ぎた今でも
被災者の方々の葬儀を知らせる訃報広告が
連日紙面を埋め尽くしています。
家族4名の葬儀も・・・
本当に 重い現実です。
あれから よく 「がんばれ!」という 言葉を耳にします。
私は どうもこの言葉が好きではありません。
この言葉が もっとも適している場面も もちろんあります。
例えば 疾走する駅伝ランナーに声をかけるときは この言葉以外は ちょっと見つからない。
しかし 苦しみや 悲しみの中にある人を励ますなら もう少し具体的な言葉を 使ってあげたい、と思います。

私の事務所が かつて床上浸水したとき もっとも嬉しかった言葉は 「俺にできること 何かない?」だった・・・
妻が死んだ時は 「いいから泣けッ! 俺も一緒に泣くから」
妻が 落ち込んでいる私に言ってくれたのは 「だいじょうぶ!!」 でした。
「がんばれ」 が有効なのは 少なくとも 信頼関係が成り立っている、 ということが条件のような気がします。

仮埋葬所の ある墓碑の前で
私の読経中 ずっとうずくまったまま 肩を震わせていた夫人がおりました。
私は 小さな声で「ご苦労様です」 としか言えなかった。
通夜~本日の葬儀を執り行って 夕方帰宅しました。 あっという間の 3日間でした。
さて 今回の東北のことを 少し。
3・11 で 亡くなられた方々の遺体ですが・・・
火葬場の処理能力を大きく上回る数の遺体を 遺族の了解を取った上で、いったん土葬して、後に火葬する 「仮埋葬」 という苦渋の対応がとられました。
15日、ボランティア作業が終わった夕刻、東松島市の 「仮埋葬所」 を訪問しました。
ズラッと並んだ 白木の墓標に 圧倒され、否応もない現実に 最初に被災地を見たときのショックが 蘇ります。


ベニヤ板で 仕切っただけのスペースに
埋葬します

身元不明者の遺体も

通路を縫って
お経をあげさせていただきました。
ここを管理する 市役所の方が来てくれて お話を伺うことができました。
ここに 仮埋葬された遺体は 400体近く、 火葬所の処理能力から 1日2体づつ 順番に火葬を進め、
現在190体が 残っているとのこと。
完全に終わるのは まだ当分先のことです。

地元の新聞には 100日が過ぎた今でも
被災者の方々の葬儀を知らせる訃報広告が
連日紙面を埋め尽くしています。
家族4名の葬儀も・・・
本当に 重い現実です。
あれから よく 「がんばれ!」という 言葉を耳にします。
私は どうもこの言葉が好きではありません。
この言葉が もっとも適している場面も もちろんあります。
例えば 疾走する駅伝ランナーに声をかけるときは この言葉以外は ちょっと見つからない。
しかし 苦しみや 悲しみの中にある人を励ますなら もう少し具体的な言葉を 使ってあげたい、と思います。

私の事務所が かつて床上浸水したとき もっとも嬉しかった言葉は 「俺にできること 何かない?」だった・・・
妻が死んだ時は 「いいから泣けッ! 俺も一緒に泣くから」
妻が 落ち込んでいる私に言ってくれたのは 「だいじょうぶ!!」 でした。
「がんばれ」 が有効なのは 少なくとも 信頼関係が成り立っている、 ということが条件のような気がします。

仮埋葬所の ある墓碑の前で
私の読経中 ずっとうずくまったまま 肩を震わせていた夫人がおりました。
私は 小さな声で「ご苦労様です」 としか言えなかった。
Posted by kotokuji at
22:10
│Comments(0)
2011年06月18日
東北の空
行ってきました。

実は 15日夜、檀家さんの訃報を受け、予定を切り上げ16日の昼過ぎに 帰宅、
すぐに 坊さんモード(?) に 切り替えて、昨日が通夜、
今日は 前から予定されていた 法事 と葬儀を執り行い、
すべてが終わったのは 夕方の5時過ぎでした。
お寺は 時々こういうことが起こります。
それでも 支援物資も届け、1日だけでしたが 作業もできたこと、幸いでした。
今回運んだ 5000枚の 土のう袋です。
2ケ月ぶりの東北でしたが 静岡の ジメジメ・ムシムシとした空気と どんよりした空とは うって変わって カラリと晴れ渡り 吹く風は さわやかで まるで別世界。

東松島ボランティアセンターの前から
へどろにつかった 田んぼにも雑草が生えて 若草色に変わっていました。
市街地では ガレキも大分片付いて 復旧作業もそれなりに進んでいるようにも見えます。
でも 海岸線は まったく手付かずの状態、 何も変わっていませんでした・・・



いつもの 避難所は 半数以上の方が 仮設住宅に移られて ガラ~ンとしていました。

7月をメドに ここも閉鎖されるそう。 自衛隊による炊き出しも もうありません。
救われたのは お友達になった家族の顔が とっても明るくなっていたこと。

「明るくなったね」 って聞いたら しばらく間をおいて・・・
「あの頃は 夢と現実の区別もつかず ただその日その日を過ごす事で 精一杯だったけど それに比べれば余裕はできたかな、 でも はっきりとした現実を知るということは 不安要素もそれだけ見えてくるってことで・・・、 ウ~ン・・・」
勤めていた会社は津波で流され 従業員全員が解雇、 この避難所を出て 失業保険が切れる前に 何とか仕事が見つかりますように、 というのが 彼女の願いです。

東北で 考えた事、 また次回に。
明日は 『興徳寺を美しくする日』 です。
雨が降りませんように・・・

実は 15日夜、檀家さんの訃報を受け、予定を切り上げ16日の昼過ぎに 帰宅、
すぐに 坊さんモード(?) に 切り替えて、昨日が通夜、
今日は 前から予定されていた 法事 と葬儀を執り行い、
すべてが終わったのは 夕方の5時過ぎでした。
お寺は 時々こういうことが起こります。
それでも 支援物資も届け、1日だけでしたが 作業もできたこと、幸いでした。
今回運んだ 5000枚の 土のう袋です。
2ケ月ぶりの東北でしたが 静岡の ジメジメ・ムシムシとした空気と どんよりした空とは うって変わって カラリと晴れ渡り 吹く風は さわやかで まるで別世界。

東松島ボランティアセンターの前から
へどろにつかった 田んぼにも雑草が生えて 若草色に変わっていました。
市街地では ガレキも大分片付いて 復旧作業もそれなりに進んでいるようにも見えます。
でも 海岸線は まったく手付かずの状態、 何も変わっていませんでした・・・



いつもの 避難所は 半数以上の方が 仮設住宅に移られて ガラ~ンとしていました。

7月をメドに ここも閉鎖されるそう。 自衛隊による炊き出しも もうありません。
救われたのは お友達になった家族の顔が とっても明るくなっていたこと。

「明るくなったね」 って聞いたら しばらく間をおいて・・・
「あの頃は 夢と現実の区別もつかず ただその日その日を過ごす事で 精一杯だったけど それに比べれば余裕はできたかな、 でも はっきりとした現実を知るということは 不安要素もそれだけ見えてくるってことで・・・、 ウ~ン・・・」
勤めていた会社は津波で流され 従業員全員が解雇、 この避難所を出て 失業保険が切れる前に 何とか仕事が見つかりますように、 というのが 彼女の願いです。

東北で 考えた事、 また次回に。
明日は 『興徳寺を美しくする日』 です。
雨が降りませんように・・・
Posted by kotokuji at
21:43
│Comments(0)
2011年06月13日
もったいない
人に物をあげることが とっても好き。
物に対して あまり執着がない、 整理をするということは 捨てる事、と思っていた 私。
その気持ちは 今も 変わりはないけれど 最近 「もったいない」 ということを 強く意識するようになりました。

節電を始めてからかもしれません。 人がいないところで 灯りが点いていると 他所の家でも 気になる。
真っ暗な部屋で 待機電力のポツポツ とした 青や緑の光りが灯っていると 「もったいないな~」と消したくなります。

最近、レザープリンターが 不調で 20枚に一度くらいの割合で 黒い筋が入ります。
特に葉書などを印刷すると、その割合が増え、書き損じの枚数もバカになりません。
メーカーに調べてもらったら、紙を送るところの部品に原因があるらしく
部品をそっくり取り替えるしかない、その費用は 7万円。
「エェ~ッ!」という私に
「そこで ご提案なのですが~ いずれ ドラム(これも部品の名前で、7万円だとか)
なども 交換の時期に入りますし~
如何でしょうか、
今なら 最新モデルが11万円と 大変お求め安くなっておりますが~」
結局、5年使ったレザープリンター、今も現役で使っている機械を 取り替えることになりました。
「もったいないな~」と思います。
誰か 欲しい方がいたら差し上げますので 使ってください。
「Canon LBP5600」A3用紙 対応の機種です。

これまた 最近の話ですが シャワートイレが 機能しなくなり メーカーを呼んだら リモコンの本体側のセンサーが壊れているとのこと。 ただ、このトイレは10年を過ぎたので、部品は保管されてなく 本体一式を取り替えるしかない、とのこと。
シンプルなモデルでも15万円、またまた「エェ~ッ!」です。
同時期に設置された もう一台も まったく同じ故障で 仕方ない、一台だけ交換することにしました。 これは誰かに差し上げるという訳にはいきませんが、 小さな部品1個が無いために 本体一式を取り替える・・・
「もったいないな~」

(記事とは関係ありませんが)
竹 の成長過程です
「もったいない」は ポルトガル語では É um desperdício と訳されるように思いますが、どちらかといえば 「無駄」 という意味で ちょっとニュアンスが 違う、日本語の 「もったいない」は なかなか 深~い 言葉だと思えます。
環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性、ワンガリー・マータイさんが2005年の来日の際に 感銘を受けたのが この「もったいない」 という日本語だったそう。
マータイさんは この美しい日本語を 環境を守る世界共通語 「MOTTAINAI」 として広めることを提唱しました。
3・11を機会に 生き方を少し変える、 そのキーワードを 「もったいない」 に しようと思います。

今朝の富士山です
*予定通り、 明朝4時に出発します。 帰りは 17日夜。 幸い、降雨確率も低く 休まず仕事ができそうです。 報告を楽しみにしてください。
物に対して あまり執着がない、 整理をするということは 捨てる事、と思っていた 私。
その気持ちは 今も 変わりはないけれど 最近 「もったいない」 ということを 強く意識するようになりました。

節電を始めてからかもしれません。 人がいないところで 灯りが点いていると 他所の家でも 気になる。
真っ暗な部屋で 待機電力のポツポツ とした 青や緑の光りが灯っていると 「もったいないな~」と消したくなります。

最近、レザープリンターが 不調で 20枚に一度くらいの割合で 黒い筋が入ります。
特に葉書などを印刷すると、その割合が増え、書き損じの枚数もバカになりません。
メーカーに調べてもらったら、紙を送るところの部品に原因があるらしく
部品をそっくり取り替えるしかない、その費用は 7万円。
「エェ~ッ!」という私に
「そこで ご提案なのですが~ いずれ ドラム(これも部品の名前で、7万円だとか)
なども 交換の時期に入りますし~
如何でしょうか、
今なら 最新モデルが11万円と 大変お求め安くなっておりますが~」
結局、5年使ったレザープリンター、今も現役で使っている機械を 取り替えることになりました。
「もったいないな~」と思います。
誰か 欲しい方がいたら差し上げますので 使ってください。
「Canon LBP5600」A3用紙 対応の機種です。

これまた 最近の話ですが シャワートイレが 機能しなくなり メーカーを呼んだら リモコンの本体側のセンサーが壊れているとのこと。 ただ、このトイレは10年を過ぎたので、部品は保管されてなく 本体一式を取り替えるしかない、とのこと。
シンプルなモデルでも15万円、またまた「エェ~ッ!」です。
同時期に設置された もう一台も まったく同じ故障で 仕方ない、一台だけ交換することにしました。 これは誰かに差し上げるという訳にはいきませんが、 小さな部品1個が無いために 本体一式を取り替える・・・
「もったいないな~」

(記事とは関係ありませんが)
竹 の成長過程です
「もったいない」は ポルトガル語では É um desperdício と訳されるように思いますが、どちらかといえば 「無駄」 という意味で ちょっとニュアンスが 違う、日本語の 「もったいない」は なかなか 深~い 言葉だと思えます。
環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性、ワンガリー・マータイさんが2005年の来日の際に 感銘を受けたのが この「もったいない」 という日本語だったそう。
マータイさんは この美しい日本語を 環境を守る世界共通語 「MOTTAINAI」 として広めることを提唱しました。
3・11を機会に 生き方を少し変える、 そのキーワードを 「もったいない」 に しようと思います。

今朝の富士山です
*予定通り、 明朝4時に出発します。 帰りは 17日夜。 幸い、降雨確率も低く 休まず仕事ができそうです。 報告を楽しみにしてください。
Posted by kotokuji at
20:54
│Comments(0)
2011年06月09日
ファッコン
梅雨の合間に 裏山に入ります。

竹の子のシーズンは 終わりましたが
細い竹が ヒョロヒョロと生えてきて
放っておくと もちろん竹になってしまいます。
そうなると整理するのが 大変なので
今のうちに コマメに 伐ります。

このときに 役に立つのが “ファッコン”
ブラジルの山刀です。
鋼鉄製で 刃渡りが30~50cm、
日本では銃砲刀類の取り締まりで 許可にならないでしょうが
ブラジルではどこの雑貨屋でも売っている
田舎の必需品。
これが すこぶる 使い易い、
竹であろうが 柔らかな草であろうが
何でもスパスパと切れます。

私の 恩師 長澤亮太先生は 「刀道」の師範でした。
「刀道」とは 日本刀の真剣を使って 実際に巻藁などを斬る武道ですが、 かつて ブラジルを訪問された時、 演武で 四方に立てた竹を斬って見せてくれました。
ヤンヤの喝采の中、へそ曲がりの私は つい余分なことを言ってしまいます。
「これくらいのこと、ブラジルなら サトウキビ畑で働いている女の子が ファッコンで 片手で 斬ると思いますヨ」 つい口をすべらせて 「シマッタ!」 と思ったのですが、さすがは 師、
「フ~ム、ファッコンか~、 そうだ、 ブラジルで 『ファッコン道』 を立ち上げよう!」・・・
ナント、 『ファッコン道』なるものの型を 作り上げてしまったのです。
ブラジル2世の 若いお弟子さんたちが 繰り広げる『ファッコン道 お披露目演武』を 私は 神妙な面持ちで眺めていました。

あれから 10数年、
師は 昨年 他界し
日本に戻った 不肖の弟子が
今日も 裏山で ファッコンを振う・・・

富士山が たま~に 顔を出してくれます
母との会話
富士宮市役所から 母の介護度認定のための訪問がありました。
その後の 母との会話
「なんで 富士宮市役所から 来たかというとね、 もう 芝川町は ないのヨ」
「ない? 無くなっちゃったの?」
「イヤ、 無くなっちゃったわけではなくて~ 芝川町は 富士宮市になったの」
「あぁ~ 合併したんでしょ」
「なんだ、 わかってるじゃん、 で そんなこと言いたいわけではなくて~」
と話は脱線し・・・ 母が12人兄弟であった という話になると・・・
「ムカシは 夜は暗くて テレビもないし 他に楽しみは なかったんだネ~」
などと・・・ マジメな顔して シラッとのたもうた・・・

竹の子のシーズンは 終わりましたが
細い竹が ヒョロヒョロと生えてきて
放っておくと もちろん竹になってしまいます。
そうなると整理するのが 大変なので
今のうちに コマメに 伐ります。

このときに 役に立つのが “ファッコン”
ブラジルの山刀です。
鋼鉄製で 刃渡りが30~50cm、
日本では銃砲刀類の取り締まりで 許可にならないでしょうが
ブラジルではどこの雑貨屋でも売っている
田舎の必需品。
これが すこぶる 使い易い、
竹であろうが 柔らかな草であろうが
何でもスパスパと切れます。

私の 恩師 長澤亮太先生は 「刀道」の師範でした。
「刀道」とは 日本刀の真剣を使って 実際に巻藁などを斬る武道ですが、 かつて ブラジルを訪問された時、 演武で 四方に立てた竹を斬って見せてくれました。
ヤンヤの喝采の中、へそ曲がりの私は つい余分なことを言ってしまいます。
「これくらいのこと、ブラジルなら サトウキビ畑で働いている女の子が ファッコンで 片手で 斬ると思いますヨ」 つい口をすべらせて 「シマッタ!」 と思ったのですが、さすがは 師、
「フ~ム、ファッコンか~、 そうだ、 ブラジルで 『ファッコン道』 を立ち上げよう!」・・・
ナント、 『ファッコン道』なるものの型を 作り上げてしまったのです。
ブラジル2世の 若いお弟子さんたちが 繰り広げる『ファッコン道 お披露目演武』を 私は 神妙な面持ちで眺めていました。

あれから 10数年、
師は 昨年 他界し
日本に戻った 不肖の弟子が
今日も 裏山で ファッコンを振う・・・

富士山が たま~に 顔を出してくれます
母との会話
富士宮市役所から 母の介護度認定のための訪問がありました。
その後の 母との会話
「なんで 富士宮市役所から 来たかというとね、 もう 芝川町は ないのヨ」
「ない? 無くなっちゃったの?」
「イヤ、 無くなっちゃったわけではなくて~ 芝川町は 富士宮市になったの」
「あぁ~ 合併したんでしょ」
「なんだ、 わかってるじゃん、 で そんなこと言いたいわけではなくて~」
と話は脱線し・・・ 母が12人兄弟であった という話になると・・・
「ムカシは 夜は暗くて テレビもないし 他に楽しみは なかったんだネ~」
などと・・・ マジメな顔して シラッとのたもうた・・・
Posted by kotokuji at
19:32
│Comments(0)
2011年06月06日
早過ぎもせず 遅過ぎもせず
書道教室の展覧会 「恵泉展」 が昨日で終了。
3日間を通して たくさんの方に来ていただき、 ありがたくも 嬉しいことでした。

どんなイベントでもそうですが 主催者にとって 入場者数は 大きな関心事。
ところが どちらかといえば マジメな団体ほど 開催までは 大きな努力をするのだけれど
肝心の客寄せ(?)に対しては 消極的。
今回の展覧会、実は 3月18日~ に予定されていました。
各地でイベント中止の報が相次ぎ、 西嶋先生の心も揺れていましたが、 「書道展は 問題ないんじゃないですか?」 という周りからの声にも押され、いったんは開催を決意。
しかし 3月15日、富士宮地方を襲った地震で 市内各地に被害発生、という時点で中止を決定したのです。
そして 今回の開催ですが これにもドラマがありまして・・・
普通 市民会館のホールを利用するには 最低半年間前に予約が必要だそうです。 先生も 秋ごろの開催を目指して 再予約にいってみると・・ 秋までの間で この3日間だけが ポコッと空いていたそう。
「あまりにも急なので ちょっと迷ったけど 決めてしまったわ」
これが よかった と思います。


3月に開催しても お客様は これほど来てくれなかったろうし、
かといって 秋まで延ばすと あの日を目指して 努力した皆の作品が
”旬” を失ってしまう。

西嶋恵舟先生 と作品

初日、 展示の準備に集まった クラスメート。 平日なので 仕事で来れなかったメンバーが 他数名。
何事にも 絶妙のタイミングというものがあるナ~ と改めて思います。
私が 信条としている 「偶然はない、すべて必然」、 「やっぱり守られている」の裏づけでもあります。
こんな時に 思い出すのが 森信三先生(1896~1992)の言葉。
『人間は一生のうちに逢うべき人には必ず逢える。
しかも一瞬早過ぎず、一瞬遅すぎない時に。
ただし内に求める心無くば、縁は生ぜず』
その時々に すばらしき人に出逢わせていただき 今の自分があります。
回り道のようにも見える、 遅々たる歩みのようでもありますが、 振り返ってみれば それが 必要な時、でありました。 まさに 早過ぎもせず 遅すぎもせず、の 絶妙のタイミング だった、 と 思えます。
絶妙のタイミングとは 勝ち取ることではなく 与えられるものです。
だから これからも 与えられてゆくことでしょう。

富士山に また 雪が降りました。
昨日は結婚式に招かれて・・・
披露宴の司会を務めたのが FMしみず のパーソナリティー・柴田怜奈さん。
斎場での司会も担当し 私も 葬儀で よくお世話になります。
会場入り口で ばったり顔を合わせて 開口一番!
「ブログの更新が 止まってますね~ 今も出掛けに覗いてきたんですよ~ 」
そうなんです。 このところ 昼も夜も 出かけてばかりで・・・
本日、5日ぶりの更新になってしまいました。
でも 待っていてくれる人がいるということは とっても嬉しいです。
お報せ と お願い。
来週14日より 東松島市に行ってきます。 今回は 現地の依頼を受けて 「土のう袋(乾いたヘドロを処理するために入れる袋)」を 持って行きます。 とりあえず 5000枚を 発注しました。 いくらあっても足りない状況、とのことで 引き続き 支援してゆくつもりです。 ご協力いただける方、お願いいたします。 (袋は、1枚25円です)
3日間を通して たくさんの方に来ていただき、 ありがたくも 嬉しいことでした。

どんなイベントでもそうですが 主催者にとって 入場者数は 大きな関心事。
ところが どちらかといえば マジメな団体ほど 開催までは 大きな努力をするのだけれど
肝心の客寄せ(?)に対しては 消極的。
今回の展覧会、実は 3月18日~ に予定されていました。
各地でイベント中止の報が相次ぎ、 西嶋先生の心も揺れていましたが、 「書道展は 問題ないんじゃないですか?」 という周りからの声にも押され、いったんは開催を決意。
しかし 3月15日、富士宮地方を襲った地震で 市内各地に被害発生、という時点で中止を決定したのです。
そして 今回の開催ですが これにもドラマがありまして・・・
普通 市民会館のホールを利用するには 最低半年間前に予約が必要だそうです。 先生も 秋ごろの開催を目指して 再予約にいってみると・・ 秋までの間で この3日間だけが ポコッと空いていたそう。
「あまりにも急なので ちょっと迷ったけど 決めてしまったわ」
これが よかった と思います。


3月に開催しても お客様は これほど来てくれなかったろうし、
かといって 秋まで延ばすと あの日を目指して 努力した皆の作品が
”旬” を失ってしまう。

西嶋恵舟先生 と作品

初日、 展示の準備に集まった クラスメート。 平日なので 仕事で来れなかったメンバーが 他数名。
何事にも 絶妙のタイミングというものがあるナ~ と改めて思います。
私が 信条としている 「偶然はない、すべて必然」、 「やっぱり守られている」の裏づけでもあります。
こんな時に 思い出すのが 森信三先生(1896~1992)の言葉。
『人間は一生のうちに逢うべき人には必ず逢える。
しかも一瞬早過ぎず、一瞬遅すぎない時に。
ただし内に求める心無くば、縁は生ぜず』
その時々に すばらしき人に出逢わせていただき 今の自分があります。
回り道のようにも見える、 遅々たる歩みのようでもありますが、 振り返ってみれば それが 必要な時、でありました。 まさに 早過ぎもせず 遅すぎもせず、の 絶妙のタイミング だった、 と 思えます。
絶妙のタイミングとは 勝ち取ることではなく 与えられるものです。
だから これからも 与えられてゆくことでしょう。

富士山に また 雪が降りました。
昨日は結婚式に招かれて・・・
披露宴の司会を務めたのが FMしみず のパーソナリティー・柴田怜奈さん。
斎場での司会も担当し 私も 葬儀で よくお世話になります。
会場入り口で ばったり顔を合わせて 開口一番!
「ブログの更新が 止まってますね~ 今も出掛けに覗いてきたんですよ~ 」
そうなんです。 このところ 昼も夜も 出かけてばかりで・・・
本日、5日ぶりの更新になってしまいました。
でも 待っていてくれる人がいるということは とっても嬉しいです。
お報せ と お願い。
来週14日より 東松島市に行ってきます。 今回は 現地の依頼を受けて 「土のう袋(乾いたヘドロを処理するために入れる袋)」を 持って行きます。 とりあえず 5000枚を 発注しました。 いくらあっても足りない状況、とのことで 引き続き 支援してゆくつもりです。 ご協力いただける方、お願いいたします。 (袋は、1枚25円です)
Posted by kotokuji at
18:05
│Comments(0)
2011年06月01日
節電効果報告
今日から 6月、 衣替えの日だというのに あまりにも寒くて、まるで冬の格好です。

さて 「節電」を始めて、半月、 待望の(?)東京電力検針員(こういう名前かどうか?)の オネエサン(本当に若い女の方でした)が やって来て、 「5月分電気使用量」が判明。
ナント、 昨年の5月と比べて -27%です。 わずか半月でこの成果!
とっても嬉しい、 来月が ますます楽しみになりました。
537kw, 12,464円 (前年は728kw, 16,829円) 電気料金で 4,365円 の節約になりました。
それほど 特別のことをしたわけでもなく、 むしろ 今まで いかに無駄な電気を使っていたか、という反省材料になりました。

こちらは 節電というより 「風流の世界?」
計画停電のとき ローソクの灯りで お風呂に入って
ちょっと はまってしまいました。
最初は 「ムカシの人は ずいぶん 暗い生活をしてたんだな~」などと思っていましたが、目が慣れてくると 別に不自由することもなく・・・
揺れる炎が とてもイイ感じ、です。

私が 幼い頃、部屋の電灯は 60wの裸電球が 部屋に一つづつ、
広い本堂に100wが ポツンと一つだけ、 それでも さすが 100w、明るいな~ と思いました。
当時、村には 街灯が一つも無く 土曜日の夜は 本堂で 地域の子ども会が 開かれていたのですが 皆、提灯 を持って 通ってくるのです。 帰るときには それぞれに 火を点けてあげるのが 私の役目でした。

ただ 紙の提灯は 傾けると 燃えてしまうので 改良され ヒットしたのが、この「文化提灯」です。(「文化○○」という名前が 流行っていた)
紙の部分が金網になっていて 当時としては 画期的なものでした。
これは 昭和32~3年頃まで 私が実際に使っていたもの、
実際に足元を照らすと 懐中電灯より 明るい。
マイナス15パーセントの 節電は 今から 20年くらい前の水準だとか、
それくらいのことなら 一人ひとりが その自覚を持てば そんなに 無理しなくても 達成できそうな気もします。
「明るい」ということが あるいは「便利」ということが 文明の象徴のように思って ここまできましたが その裏に潜む 本質の部分まで見えなくなってしまった、ということは ないでしょうか?

昨日朝 梅雨の隙間から ちょこっとの時間 富士山が 顔を見せてくれました。
雪が 大分溶けて 夏の顔、

さて 「節電」を始めて、半月、 待望の(?)東京電力検針員(こういう名前かどうか?)の オネエサン(本当に若い女の方でした)が やって来て、 「5月分電気使用量」が判明。
ナント、 昨年の5月と比べて -27%です。 わずか半月でこの成果!
とっても嬉しい、 来月が ますます楽しみになりました。
537kw, 12,464円 (前年は728kw, 16,829円) 電気料金で 4,365円 の節約になりました。
それほど 特別のことをしたわけでもなく、 むしろ 今まで いかに無駄な電気を使っていたか、という反省材料になりました。

こちらは 節電というより 「風流の世界?」
計画停電のとき ローソクの灯りで お風呂に入って
ちょっと はまってしまいました。
最初は 「ムカシの人は ずいぶん 暗い生活をしてたんだな~」などと思っていましたが、目が慣れてくると 別に不自由することもなく・・・
揺れる炎が とてもイイ感じ、です。

私が 幼い頃、部屋の電灯は 60wの裸電球が 部屋に一つづつ、
広い本堂に100wが ポツンと一つだけ、 それでも さすが 100w、明るいな~ と思いました。
当時、村には 街灯が一つも無く 土曜日の夜は 本堂で 地域の子ども会が 開かれていたのですが 皆、提灯 を持って 通ってくるのです。 帰るときには それぞれに 火を点けてあげるのが 私の役目でした。

ただ 紙の提灯は 傾けると 燃えてしまうので 改良され ヒットしたのが、この「文化提灯」です。(「文化○○」という名前が 流行っていた)
紙の部分が金網になっていて 当時としては 画期的なものでした。
これは 昭和32~3年頃まで 私が実際に使っていたもの、
実際に足元を照らすと 懐中電灯より 明るい。
マイナス15パーセントの 節電は 今から 20年くらい前の水準だとか、
それくらいのことなら 一人ひとりが その自覚を持てば そんなに 無理しなくても 達成できそうな気もします。
「明るい」ということが あるいは「便利」ということが 文明の象徴のように思って ここまできましたが その裏に潜む 本質の部分まで見えなくなってしまった、ということは ないでしょうか?

昨日朝 梅雨の隙間から ちょこっとの時間 富士山が 顔を見せてくれました。
雪が 大分溶けて 夏の顔、
Posted by kotokuji at
20:43
│Comments(0)