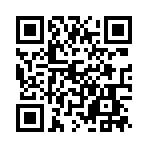2011年12月31日
泣いても笑っても
年の瀬が近づいてくると 「泣いても笑っても 後○○日・・・」などとよくいいます。
金持ちにも 貧乏人にも 年寄りにも 若者にも 公平に確実にその日がやって来ます。
遣り残したことも 多々ありますが やるべきことだけは 終わったような気がします。

昨日は恒例の「餅つき」でした。
妹たちや 甥・姪、その家族などが集まって にぎやかです。
今年は、アテにしていた力自慢の甥が仕事で来れなくて、搗きては 私を入れて3名、 交代で3回づつ搗いて 計9臼でした。




力水(ちからみず)を つける・・(?)
搗きたての餅を 大根おろし、納豆などと絡めて食べる・・・ これが楽しみです。

友人の 武蔵製菓㈱の茶畑(ちゃばた)さんが 今年も 餡を送ってくれました。 ナント10kg,

10kgの餡子に喜ぶ母
餡子は餅に絡めてきな粉をまぶしていただきます。 絶品!です。
いちご大福 もいっぱい作って 残りは明後日の『元旦会』で お汁粉にして 参詣者にふるまうことにしました。

姪の子ども 「さくらちゃん」
今年最後の日、
昨日用意した鏡餅を 本堂や仏壇・神棚や トイレの神様(?);ムカシからトイレにも・・ その他 境内地の 山の神様や 水の神様・・・等々 にお供えしました。 改めて 数えてみたら全部で12ケ所でした。 それから 玄関2ケ所を水洗いし、ついでにバイクも洗い、その合間に 昨夜から漬けておいた 黒豆を煮る・・・ 毎年 ちょっと油断した隙にふきこぼしては ため息をついていたので 今年は身の丈30cmのずんどう鍋でやってみました。
バッチリでした。

泣いても笑っても 後り8時間、
仮設住宅の 被災者の方々は どんな思いで 年を越すのだろうか? 寒くは ないだろうか? 新しき年が 希望の光に 包まれたものとなりますよう・・・ 切に祈ります。

それでは 皆様 今年一年 ありがとうございました。 来年も また よろしく おつきあいください。
金持ちにも 貧乏人にも 年寄りにも 若者にも 公平に確実にその日がやって来ます。
遣り残したことも 多々ありますが やるべきことだけは 終わったような気がします。

昨日は恒例の「餅つき」でした。
妹たちや 甥・姪、その家族などが集まって にぎやかです。
今年は、アテにしていた力自慢の甥が仕事で来れなくて、搗きては 私を入れて3名、 交代で3回づつ搗いて 計9臼でした。




力水(ちからみず)を つける・・(?)
搗きたての餅を 大根おろし、納豆などと絡めて食べる・・・ これが楽しみです。

友人の 武蔵製菓㈱の茶畑(ちゃばた)さんが 今年も 餡を送ってくれました。 ナント10kg,

10kgの餡子に喜ぶ母
餡子は餅に絡めてきな粉をまぶしていただきます。 絶品!です。
いちご大福 もいっぱい作って 残りは明後日の『元旦会』で お汁粉にして 参詣者にふるまうことにしました。

姪の子ども 「さくらちゃん」
今年最後の日、
昨日用意した鏡餅を 本堂や仏壇・神棚や トイレの神様(?);ムカシからトイレにも・・ その他 境内地の 山の神様や 水の神様・・・等々 にお供えしました。 改めて 数えてみたら全部で12ケ所でした。 それから 玄関2ケ所を水洗いし、ついでにバイクも洗い、その合間に 昨夜から漬けておいた 黒豆を煮る・・・ 毎年 ちょっと油断した隙にふきこぼしては ため息をついていたので 今年は身の丈30cmのずんどう鍋でやってみました。
バッチリでした。

泣いても笑っても 後り8時間、
仮設住宅の 被災者の方々は どんな思いで 年を越すのだろうか? 寒くは ないだろうか? 新しき年が 希望の光に 包まれたものとなりますよう・・・ 切に祈ります。

それでは 皆様 今年一年 ありがとうございました。 来年も また よろしく おつきあいください。
Posted by kotokuji at
16:23
│Comments(0)
2011年12月28日
毎日大掃除
25日の日曜日は 本堂の大掃除でした。 いつも一人でやっていたのですが、今年初めて、檀家さんにも お手伝いを呼びかけたところ 私や妹たちも含めて、総勢11名になりました。

大掃除のポイントは ガラス洗い、 興徳寺の本堂の仏さまは 合計12枚の 大きな透明ガラスで仕切られています。 これを外して、 洗って、 乾燥させて、 磨き上げる・・・
クリスタルのように ピカピカになったガラスを入れると、もうこれだけで「掃除をやった!」という気持になります。

本堂が片付いたので、午後から 庫裏の大掃除を開始し 以来 毎日・毎日、大掃除!!
特に私の仕事場附近は 夏以来の 書類・書籍等が散乱していて これを整理するのに丸二日間も費やしてしまいました。
読めなかったままの雑誌は さっと目を通してから解体し 興味あるページのみ切り取って ファイルに収めます。 またファイルの中味も 再点検し 永遠に必要もないと思われるものは バッサリ捨てます。
今回は 珍しく まとまった時間がとれ ありがたいことに何も起こらず(?) おかげでスッキリ と片付けることが できました。
何が快適といって お掃除に 勝るものはナイ! と つくづく思います。

きれいになった 私の 仕事場です。
心の中も たまには 大掃除をして たまっている 垢や汚れを バッサリと捨てられたら すっきりとするでしょうね。
心のもやもや、おもしろくないこと、気にいらない奴のこと・・・ バッサリと捨てて 笑って 新しい年を迎えましょう。

小学生が植えた木に点けられている短冊

今回植樹した山の上から
お知らせ
12月31日、夜11時半より 『年越しの唱題行』
揺れる和蝋燭の灯りの中で ただひたすら 「南無妙法蓮華経・・・ 」 と唱えながらの越年を経験してみませんか?
本堂の中ですが 寒いので それなりの格好で お出かけください。

大掃除のポイントは ガラス洗い、 興徳寺の本堂の仏さまは 合計12枚の 大きな透明ガラスで仕切られています。 これを外して、 洗って、 乾燥させて、 磨き上げる・・・
クリスタルのように ピカピカになったガラスを入れると、もうこれだけで「掃除をやった!」という気持になります。

本堂が片付いたので、午後から 庫裏の大掃除を開始し 以来 毎日・毎日、大掃除!!
特に私の仕事場附近は 夏以来の 書類・書籍等が散乱していて これを整理するのに丸二日間も費やしてしまいました。
読めなかったままの雑誌は さっと目を通してから解体し 興味あるページのみ切り取って ファイルに収めます。 またファイルの中味も 再点検し 永遠に必要もないと思われるものは バッサリ捨てます。
今回は 珍しく まとまった時間がとれ ありがたいことに何も起こらず(?) おかげでスッキリ と片付けることが できました。
何が快適といって お掃除に 勝るものはナイ! と つくづく思います。

きれいになった 私の 仕事場です。
心の中も たまには 大掃除をして たまっている 垢や汚れを バッサリと捨てられたら すっきりとするでしょうね。
心のもやもや、おもしろくないこと、気にいらない奴のこと・・・ バッサリと捨てて 笑って 新しい年を迎えましょう。

小学生が植えた木に点けられている短冊

今回植樹した山の上から
お知らせ
12月31日、夜11時半より 『年越しの唱題行』
揺れる和蝋燭の灯りの中で ただひたすら 「南無妙法蓮華経・・・ 」 と唱えながらの越年を経験してみませんか?
本堂の中ですが 寒いので それなりの格好で お出かけください。
Posted by kotokuji at
20:46
│Comments(0)
2011年12月23日
ご多幸を祈ります
年賀状書きが 一段落。
今年は 約230枚でしたが 年々増えてゆきます。
若い頃は 5色摺りくらいの 木版画でしたが、 ここに戻ってからは 興徳寺から撮った 富士山の写真を使います。 宛名も プリンターで刷るので ずいぶん楽になりましたが、それでも 一枚一枚、小筆で正月の決まり文句を入れて、ペンで 何かコメントを書くようにしているので、正味4日間を費やしました。
この 必ず自筆で書く、というパターンだけは何十年と 変わっていません。 ブラジル時代はクリスマスカードでしたが、それこそ信号待ちの車の中でも書いていました。

新年のお祝いの言葉を 「賀詞」 というそうですが、結びに
「○○様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます」という言葉をよく使います。

ところで 「・・・・祈ります」と書いて 実際に祈っている方って どれくらいいるでしょうか?
祈りの方法論は、ともかくとしても、 差し出す相手が 健康で 幸せであって欲しい、 と神様(ほとけ様)にお願いする、何らかの具体的な行動をとられているでしょうか?
このことに 気がついてから、私は 書き上げた 年賀状を 本堂の仏さまにいったん供えて、お経をあげ、1枚づつ名前を読み上げて、祈念するようにしています。

他人のために 祈ることができるって とても幸せなことです。

*明後日は 「本堂の大掃除」。
今まで 一人でやっていたのですが、 昨年など ナント12月31日でした。 それで 今年は 日だけは決めておこうと、 12月25日の8:00~ 。 もし 手伝っていただけると 助かります。 朝8時から11頃までです。
今年は 約230枚でしたが 年々増えてゆきます。
若い頃は 5色摺りくらいの 木版画でしたが、 ここに戻ってからは 興徳寺から撮った 富士山の写真を使います。 宛名も プリンターで刷るので ずいぶん楽になりましたが、それでも 一枚一枚、小筆で正月の決まり文句を入れて、ペンで 何かコメントを書くようにしているので、正味4日間を費やしました。
この 必ず自筆で書く、というパターンだけは何十年と 変わっていません。 ブラジル時代はクリスマスカードでしたが、それこそ信号待ちの車の中でも書いていました。

新年のお祝いの言葉を 「賀詞」 というそうですが、結びに
「○○様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます」という言葉をよく使います。
ところで 「・・・・祈ります」と書いて 実際に祈っている方って どれくらいいるでしょうか?
祈りの方法論は、ともかくとしても、 差し出す相手が 健康で 幸せであって欲しい、 と神様(ほとけ様)にお願いする、何らかの具体的な行動をとられているでしょうか?
このことに 気がついてから、私は 書き上げた 年賀状を 本堂の仏さまにいったん供えて、お経をあげ、1枚づつ名前を読み上げて、祈念するようにしています。

他人のために 祈ることができるって とても幸せなことです。

*明後日は 「本堂の大掃除」。
今まで 一人でやっていたのですが、 昨年など ナント12月31日でした。 それで 今年は 日だけは決めておこうと、 12月25日の8:00~ 。 もし 手伝っていただけると 助かります。 朝8時から11頃までです。
Posted by kotokuji at
21:41
│Comments(0)
2011年12月20日
お膳お願いします
母との二人暮らしも 6年になりました。

父は自宅から逝ったので、その日まで 母は懸命の介護をしてきました。
歩く事すらままならない父の世話は 80歳近くの身には 大変であったと思います。
大正生まれの気丈な母は 泣き言ひとつ言わず、黙々とその使命を果たしてきたのですが、その緊張の糸がゆるんだのか、父の死後、物忘れが激しくなり・・・
病院で診察してもらったところ、医師より「りっぱな認知症です」と告げられました。
少しばかりのショックを覚えましたが 「やっぱり・・・」 という 妙な安心感もありました。
以来、5年が経過しましたが、 認知の症状は 平衡状態を保っています。
前にも書きましたが、
母にとっての思い出したくない過去や 嫌な記憶はすべて消え、喜びと感謝の感情のみが残りました。
「わーウレシイ!」「おいしいね~」「うゎ~きれい!」・・・
そして何に対しても「ありがとうネ」「ありがたいね~」「アタシはしあわせだネ~」です。
欲はなく、怒りもなく、そして何の不安もない・・・ この世から あの世に移り行く者の 理想の姿とも思えます。

母へのメッセージは 冷蔵庫に貼った ホワイトボード。
1昨日の日曜日のボードです。

「お膳 お願いします」
「お膳」とは 仏さまの食事のこと、
母は 朝食後 黙って準備にとりかかります。
作りながら 話すことはいつも同じ・・・
「妙蓮寺(母の実家)じゃ、家の紋を入れたお膳をお寺に置いてある檀家さんがいっぱいいてさ~、そういう家の法事のときは 必ずそのお膳をつかわなくちゃならないので 大変だったよ~、 法事がいっぱい重なって お膳が足りなくなったときは 紋を後ろ向きにして 別の家に使っちゃったこともあったよ」と 楽しそうに・・・
・・・「へぇ~ッ!」と 驚いてみせることもいつも同じ。
でも認知症のおばあさんが 作るお膳は いつもながら きれい、です。

「はい できました!」と 差し出す母に
「故○○様に代わりまして 心より御礼申し上げます」 と言って うやうやしく(?)受け取ります。
いい年をした母と子が 小さなお膳を挟んで 笑い会えるとは 幸せなことです。

昨夜は 「寒行」の打ち合わせでした。
大寒(1/21)~節分 (2/3)までの14日間, 内容的には 昨年とほぼ同じですが、 有志の方から頂く浄財は、
柚野小学校の図書館 への寄付金と東日本大震災の義援金、それに最後の夜の節分の豆まきの実費に充てる、と決められました。 村の寺院の若いお坊さんたちですが、皆マジメで、宗教家として どう生きるべきか?を真剣に考えています。
田舎の中華料理屋で 食事をしながらの話し合いでしたが、ノンアルコールビール、割り勘、と最後までさわやかでした。
来年の寒行、 1月21日・22日・23日は興徳寺からスタートします。 近くの方、一度 参加してみませんか?

父は自宅から逝ったので、その日まで 母は懸命の介護をしてきました。
歩く事すらままならない父の世話は 80歳近くの身には 大変であったと思います。
大正生まれの気丈な母は 泣き言ひとつ言わず、黙々とその使命を果たしてきたのですが、その緊張の糸がゆるんだのか、父の死後、物忘れが激しくなり・・・
病院で診察してもらったところ、医師より「りっぱな認知症です」と告げられました。
少しばかりのショックを覚えましたが 「やっぱり・・・」 という 妙な安心感もありました。
以来、5年が経過しましたが、 認知の症状は 平衡状態を保っています。
前にも書きましたが、
母にとっての思い出したくない過去や 嫌な記憶はすべて消え、喜びと感謝の感情のみが残りました。
「わーウレシイ!」「おいしいね~」「うゎ~きれい!」・・・
そして何に対しても「ありがとうネ」「ありがたいね~」「アタシはしあわせだネ~」です。
欲はなく、怒りもなく、そして何の不安もない・・・ この世から あの世に移り行く者の 理想の姿とも思えます。

母へのメッセージは 冷蔵庫に貼った ホワイトボード。
1昨日の日曜日のボードです。

「お膳 お願いします」
「お膳」とは 仏さまの食事のこと、
母は 朝食後 黙って準備にとりかかります。
作りながら 話すことはいつも同じ・・・
「妙蓮寺(母の実家)じゃ、家の紋を入れたお膳をお寺に置いてある檀家さんがいっぱいいてさ~、そういう家の法事のときは 必ずそのお膳をつかわなくちゃならないので 大変だったよ~、 法事がいっぱい重なって お膳が足りなくなったときは 紋を後ろ向きにして 別の家に使っちゃったこともあったよ」と 楽しそうに・・・
・・・「へぇ~ッ!」と 驚いてみせることもいつも同じ。
でも認知症のおばあさんが 作るお膳は いつもながら きれい、です。

「はい できました!」と 差し出す母に
「故○○様に代わりまして 心より御礼申し上げます」 と言って うやうやしく(?)受け取ります。
いい年をした母と子が 小さなお膳を挟んで 笑い会えるとは 幸せなことです。

昨夜は 「寒行」の打ち合わせでした。
大寒(1/21)~節分 (2/3)までの14日間, 内容的には 昨年とほぼ同じですが、 有志の方から頂く浄財は、
柚野小学校の図書館 への寄付金と東日本大震災の義援金、それに最後の夜の節分の豆まきの実費に充てる、と決められました。 村の寺院の若いお坊さんたちですが、皆マジメで、宗教家として どう生きるべきか?を真剣に考えています。
田舎の中華料理屋で 食事をしながらの話し合いでしたが、ノンアルコールビール、割り勘、と最後までさわやかでした。
来年の寒行、 1月21日・22日・23日は興徳寺からスタートします。 近くの方、一度 参加してみませんか?
Posted by kotokuji at
19:54
│Comments(0)
2011年12月15日
お別れのかたち
暮のお経回りも 終番に近づいた12日、 知人の訃報を受けました。
小田義明さん。橋梁の技術者でしたが 昨年、第一線から手を引いたことを機に 奥様の母親の面倒をみるため 東京から富士宮へと移り住んでこられました。
良き仲間に恵まれ、積極的に社会活動をされておりました。
私の講演を聴いてくれたり、仲間と一緒に 興徳寺にも訪ねてくださいました。

9日の朝、自宅で発症し、意識も戻らぬまま、3日後に忽然と逝ってしまいました。
急性大動脈乖離、72歳でした。
遺族より 通夜~葬儀の導師を依頼されました。
親族だけの集まりではありましたが 心を込めて、務めさせていただきました。
参列者何百人という規模の葬儀も 昨日のように30人ほどの葬儀も 式に臨む気持は まったく変わりません。
夕刻から 場所を変えて 仲間が主催する 『お別れの会』、
遺骨と遺影が祀られた 祭壇の前で 音楽と 仲間たちの 追悼のメッセージ、
しみじみと そして温かく すばらしい告別式となりました。



民族学者 八木洋行氏
「今年はたくさんの方が あちらに渡って 三途の川の橋が 壊れかけているのでしょう。
責任感の強い彼は 放っとけなくて 修理に行ったのではないかと思います」
と 泣きながら・・・
「葬儀」とは 死者の魂を霊界へ送るための儀式、 それに対して 「告別式」は 会葬した人たちが、死者にお別れをする儀式のこと、
今回のように 別に行うことが 望ましい形であろうと思われます。
近年、『お別れの会』のみをもって 『葬儀』に代えるような傾向が見られますが、 これはまったく違う事です。 私たちの心に ケジメをつけるための「お別れの会」はあくまでも、残された者のためのものであり、「葬儀」は亡くなられた方の 霊のために行われるものです。
宗教家と呼ばれる方たちが 真剣に訴えていかなければならないことだと思います。
それにしても わずか1年間の滞在で これだけの方に愛された 義明さん、

「誰にも分け隔てなく愛情の手を差し伸べ、
一切の見返りを求めなかった・・・
心から尊敬し、生まれ変わったら
また 一緒になってください、とお願いしました」 と奥様の言葉・・・
私も
心より 尊敬申し上げます。

暮のお経回りを始めて お葬式が2回、 終了予定が少しずれましたが 残り10軒です。 終わったら、年賀状やら、会計処理やら、大掃除やらと、いつものように ドタバタと1年が終わってしまいそうです。
小田義明さん。橋梁の技術者でしたが 昨年、第一線から手を引いたことを機に 奥様の母親の面倒をみるため 東京から富士宮へと移り住んでこられました。
良き仲間に恵まれ、積極的に社会活動をされておりました。
私の講演を聴いてくれたり、仲間と一緒に 興徳寺にも訪ねてくださいました。

9日の朝、自宅で発症し、意識も戻らぬまま、3日後に忽然と逝ってしまいました。
急性大動脈乖離、72歳でした。
遺族より 通夜~葬儀の導師を依頼されました。
親族だけの集まりではありましたが 心を込めて、務めさせていただきました。
参列者何百人という規模の葬儀も 昨日のように30人ほどの葬儀も 式に臨む気持は まったく変わりません。
夕刻から 場所を変えて 仲間が主催する 『お別れの会』、
遺骨と遺影が祀られた 祭壇の前で 音楽と 仲間たちの 追悼のメッセージ、
しみじみと そして温かく すばらしい告別式となりました。



民族学者 八木洋行氏
「今年はたくさんの方が あちらに渡って 三途の川の橋が 壊れかけているのでしょう。
責任感の強い彼は 放っとけなくて 修理に行ったのではないかと思います」
と 泣きながら・・・
「葬儀」とは 死者の魂を霊界へ送るための儀式、 それに対して 「告別式」は 会葬した人たちが、死者にお別れをする儀式のこと、
今回のように 別に行うことが 望ましい形であろうと思われます。
近年、『お別れの会』のみをもって 『葬儀』に代えるような傾向が見られますが、 これはまったく違う事です。 私たちの心に ケジメをつけるための「お別れの会」はあくまでも、残された者のためのものであり、「葬儀」は亡くなられた方の 霊のために行われるものです。
宗教家と呼ばれる方たちが 真剣に訴えていかなければならないことだと思います。
それにしても わずか1年間の滞在で これだけの方に愛された 義明さん、

「誰にも分け隔てなく愛情の手を差し伸べ、
一切の見返りを求めなかった・・・
心から尊敬し、生まれ変わったら
また 一緒になってください、とお願いしました」 と奥様の言葉・・・
私も
心より 尊敬申し上げます。

暮のお経回りを始めて お葬式が2回、 終了予定が少しずれましたが 残り10軒です。 終わったら、年賀状やら、会計処理やら、大掃除やらと、いつものように ドタバタと1年が終わってしまいそうです。
Posted by kotokuji at
21:30
│Comments(0)
2011年12月09日
日本のお母さん
『興徳寺便り19号』で 「しあわせになってねといのりつづける お母さんがいる」 というタイトルで お母さんのことを書いてみました。
http://kotokuji.jp/howa/howa94.html
『知覧特攻平和会館』で 若い兵士たちが遺した膨大な遺書や手紙を読み、死に逝く彼らのもっとも深い思いは やはり母親であることを知りました。
徹底したマインドコントロールの中、 教えられたままに 「天皇陛下万歳!」と死んでいった者が 如何ほどいたか? 知る由もないけれど、脳裏をよぎるものが 「おかあさん」であったことは 容易に想像がつきます。

お檀家さんを廻る楽しみのひとつが このお母さんたちと会うこと・・・
戦前~戦後を生き抜き、すべてを受け入れ、じっと耐えてきた、強くて、たくましくて、明るくて、シッカリ者の 「日本のお母さん」たちです。






お経の後、お茶をいただきながら さりげない会話を交わしますが、時にポツポツと 身の上話を語ってくれることもあります。
そんな中で 拾った イイ話・・・

佐野富子さん;
「毎年12月になると 換気扇の掃除をするんです。
それが 今日だったんですが 掃除をしながら、
つくづく ありがたいな~ と思いました。
東北の被災者の方たちは 先も見えない不安の中で
お正月を迎えるんですものネ~」

佐野元恵さん;
「ご主人が亡くなって落ち込んでる友達とか
一人暮らしのおじいさんとか、朝 電話をかけるんです。
『おはようございま~す、 御飯食べた~?』 なんて、
ほんの一言だけど、
アタシ 車の運転もできないし、 こんなことしかできないから・・」
どんな人にも それぞれのドラマがあって 観客席で観ていると ハラハラ・ドキドキ、時に可笑しく、時に悲しく・・・
とってもオモシロイ。
最後は何らかの余韻を残して 幕!=the end,
悲しいだけのドラマは ないし、ただの つまらない人生、も ありません。

*お会いしたことのない方より コメントをいただきます。 とっても嬉しいです。 なるべく返事を書きます。 メルアドを載せてください。
http://kotokuji.jp/howa/howa94.html
『知覧特攻平和会館』で 若い兵士たちが遺した膨大な遺書や手紙を読み、死に逝く彼らのもっとも深い思いは やはり母親であることを知りました。
徹底したマインドコントロールの中、 教えられたままに 「天皇陛下万歳!」と死んでいった者が 如何ほどいたか? 知る由もないけれど、脳裏をよぎるものが 「おかあさん」であったことは 容易に想像がつきます。

お檀家さんを廻る楽しみのひとつが このお母さんたちと会うこと・・・
戦前~戦後を生き抜き、すべてを受け入れ、じっと耐えてきた、強くて、たくましくて、明るくて、シッカリ者の 「日本のお母さん」たちです。






お経の後、お茶をいただきながら さりげない会話を交わしますが、時にポツポツと 身の上話を語ってくれることもあります。
そんな中で 拾った イイ話・・・

佐野富子さん;
「毎年12月になると 換気扇の掃除をするんです。
それが 今日だったんですが 掃除をしながら、
つくづく ありがたいな~ と思いました。
東北の被災者の方たちは 先も見えない不安の中で
お正月を迎えるんですものネ~」

佐野元恵さん;
「ご主人が亡くなって落ち込んでる友達とか
一人暮らしのおじいさんとか、朝 電話をかけるんです。
『おはようございま~す、 御飯食べた~?』 なんて、
ほんの一言だけど、
アタシ 車の運転もできないし、 こんなことしかできないから・・」
どんな人にも それぞれのドラマがあって 観客席で観ていると ハラハラ・ドキドキ、時に可笑しく、時に悲しく・・・
とってもオモシロイ。
最後は何らかの余韻を残して 幕!=the end,
悲しいだけのドラマは ないし、ただの つまらない人生、も ありません。

*お会いしたことのない方より コメントをいただきます。 とっても嬉しいです。 なるべく返事を書きます。 メルアドを載せてください。
Posted by kotokuji at
20:59
│Comments(0)
2011年12月06日
お線香 あげさせてください
12月1日より 暮のお経回りを開始しました。
1昨日~昨日は、異常とも思える暖かさでしたが、今日は寒かった・・・ 途中で雨に叩かれたりもしましたが 何とか本日のノルマを達成できました。 (お葬式で遅れた分も ほぼ取り戻しました)

檀家さんを廻る時は お線香を持参します。
それは こんなできごとがきっかけです。
今から6年前、弟の新盆の時でした。
ある弔問客を 祭壇までご案内したところ、その方が 胸のポケットから小さなお線香のケースを取り出し、手向けてくださったのです。
初めてのことで 感心して尋ねたところ・・・
「お線香あげさせてください」と言っておきながら、他人のお線香を手向けるのはオカシイ、と気づいて・・・ と答えられました。
*「お線香あげさせてください」は このあたりでの 弔問客の決まり文句です。
「ナルホド!」と 思って、それからは 私も 線香持参。
興徳寺に仏具を納入してくれる業者さんは なかなか お商売が上手で 「いや~ 先代さん(父のことです)は イイお線香を使ってらっしゃいましたね~」 などと言うので、私も 負けずに イイお線香を使います。
檀家さんの何人かだけですが 「いい香りですね~」 と言ってくださいます。

「よい香り」は ほとけ様への供え物、
そこそこの 贅沢を楽しみたいと思います。
最近 都会では 煙の出ない線香が 流行っているそうですが、
線香の煙が 建物や調度品を 汚すとはとても思えません。
静かに昇る煙は なんともいえない 味わいで
香りだけでなく 眼でも楽しめる と思うのですが・・・
檀家さんを廻る時、線香とともに欠かせないのが 犬のオヤツ、
先代は いつも袂(たもと)に、小さなキャラメルの箱を しのばせ、
それが 子どもたちに大人気だったそうですが (当時、箱入りのキャラメルは 嬉しいプレゼントだった)、
今や 子どもの姿も消えて、歓迎してくれるのは 繋がれっぱなしの犬くらい、

オヤツで手なずけてあるので、
私のバイクを見かけたら どこの犬も ちぎれるばかりに尻尾を振って
すっ飛んで来ます。
カワイイですね。
犬のオヤツ代が 線香代と同じくらいかかりますが
これも ささやかなゼイタクのうちで・・・

* HP, 「紙上法話」 と 「住職のひとりごと」 up しました。
1昨日~昨日は、異常とも思える暖かさでしたが、今日は寒かった・・・ 途中で雨に叩かれたりもしましたが 何とか本日のノルマを達成できました。 (お葬式で遅れた分も ほぼ取り戻しました)

檀家さんを廻る時は お線香を持参します。
それは こんなできごとがきっかけです。
今から6年前、弟の新盆の時でした。
ある弔問客を 祭壇までご案内したところ、その方が 胸のポケットから小さなお線香のケースを取り出し、手向けてくださったのです。
初めてのことで 感心して尋ねたところ・・・
「お線香あげさせてください」と言っておきながら、他人のお線香を手向けるのはオカシイ、と気づいて・・・ と答えられました。
*「お線香あげさせてください」は このあたりでの 弔問客の決まり文句です。
「ナルホド!」と 思って、それからは 私も 線香持参。
興徳寺に仏具を納入してくれる業者さんは なかなか お商売が上手で 「いや~ 先代さん(父のことです)は イイお線香を使ってらっしゃいましたね~」 などと言うので、私も 負けずに イイお線香を使います。
檀家さんの何人かだけですが 「いい香りですね~」 と言ってくださいます。

「よい香り」は ほとけ様への供え物、
そこそこの 贅沢を楽しみたいと思います。
最近 都会では 煙の出ない線香が 流行っているそうですが、
線香の煙が 建物や調度品を 汚すとはとても思えません。
静かに昇る煙は なんともいえない 味わいで
香りだけでなく 眼でも楽しめる と思うのですが・・・
檀家さんを廻る時、線香とともに欠かせないのが 犬のオヤツ、
先代は いつも袂(たもと)に、小さなキャラメルの箱を しのばせ、
それが 子どもたちに大人気だったそうですが (当時、箱入りのキャラメルは 嬉しいプレゼントだった)、
今や 子どもの姿も消えて、歓迎してくれるのは 繋がれっぱなしの犬くらい、

オヤツで手なずけてあるので、
私のバイクを見かけたら どこの犬も ちぎれるばかりに尻尾を振って
すっ飛んで来ます。
カワイイですね。
犬のオヤツ代が 線香代と同じくらいかかりますが
これも ささやかなゼイタクのうちで・・・

* HP, 「紙上法話」 と 「住職のひとりごと」 up しました。
Posted by kotokuji at
21:23
│Comments(0)
2011年12月02日
今年いちばん嬉しかったこと
11月30日、 地元 柚野小学校の3~6年生、80名と先生7名 それにスタッフ28名で 植樹を行いました。
名づけて 『YUNOどんぐりの会 第一回植樹祭』
朝8時 スタッフのミーティング

9時半 子どもたちがやってきて・・・ 開会式

山に向けて 出発

山道を行く 5~6年生

こちらは 3~4年生


5~6年生

子どもたち 一人ひとりが 木の短冊に それぞれ自作の俳句を書いて来てくれた。


添え木に つける。
最後の記念写真

そして スタッフ、 平日なのに これだけの方が来てくれた(この他に この時点で 帰られた方が3名)

山に 子どもたちの 歓声が こだました。
「高い所の作業は 子どもには 無理だろう」 なんて おっさんたちの杞憂、
「ハアハア フウフウ」 言っているのは 大人たちで 子どもは元気そのもの、

この子らが植えた木が 彼らとともに成長する。
これから30年後、
今度は 彼らが子どもたちに 見せてやって欲しい
「この山の木は お父さんが 子どもの頃に植えたんだヨ」 って・・・
スタッフの皆様 お疲れ様でした。 そして 本当にありがとうございました。

今回 植樹をした 斜面よりの 富士山、 下に見えるのが 柚野小学校、
村の山には 紅葉がほとんどない。
毎年 正月2日の法要のあとの法話で 「昨年一年間で 一番嬉しかった事 何ですか?」 と聴きます。
「嬉しいことを きっちりと インプットして、 次々と 上書きしてゆきましょう」
今年もいよいよ 師走、 この時点で 今年の私がもっとも 嬉しかった こと、 「子どもたちと 一緒に 木を植えられたこと」です。
*昨日から 暮のお経回り、開始。 なのに 植樹の前日、夜半に 檀家さんが亡くなられ、昨日がお通夜、今日がお葬式でした。 お葬式最優先で 何とかノルマ(?)を果たすべく テンヤワンヤの3日間でした。
名づけて 『YUNOどんぐりの会 第一回植樹祭』
朝8時 スタッフのミーティング

9時半 子どもたちがやってきて・・・ 開会式

山に向けて 出発

山道を行く 5~6年生

こちらは 3~4年生


5~6年生

子どもたち 一人ひとりが 木の短冊に それぞれ自作の俳句を書いて来てくれた。


添え木に つける。
最後の記念写真

そして スタッフ、 平日なのに これだけの方が来てくれた(この他に この時点で 帰られた方が3名)

山に 子どもたちの 歓声が こだました。
「高い所の作業は 子どもには 無理だろう」 なんて おっさんたちの杞憂、
「ハアハア フウフウ」 言っているのは 大人たちで 子どもは元気そのもの、

この子らが植えた木が 彼らとともに成長する。
これから30年後、
今度は 彼らが子どもたちに 見せてやって欲しい
「この山の木は お父さんが 子どもの頃に植えたんだヨ」 って・・・
スタッフの皆様 お疲れ様でした。 そして 本当にありがとうございました。

今回 植樹をした 斜面よりの 富士山、 下に見えるのが 柚野小学校、
村の山には 紅葉がほとんどない。
毎年 正月2日の法要のあとの法話で 「昨年一年間で 一番嬉しかった事 何ですか?」 と聴きます。
「嬉しいことを きっちりと インプットして、 次々と 上書きしてゆきましょう」
今年もいよいよ 師走、 この時点で 今年の私がもっとも 嬉しかった こと、 「子どもたちと 一緒に 木を植えられたこと」です。
*昨日から 暮のお経回り、開始。 なのに 植樹の前日、夜半に 檀家さんが亡くなられ、昨日がお通夜、今日がお葬式でした。 お葬式最優先で 何とかノルマ(?)を果たすべく テンヤワンヤの3日間でした。
Posted by kotokuji at
21:37
│Comments(0)