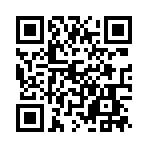2010年07月30日
棚経開始!
昨日より お盆の棚経を開始いたしました。
棚経=お盆に僧侶が檀家を回って精霊に経を誦し、回向すること。 棚経についての語義的いわれは、徳川幕府の宗教政策の一つである寺請制度のなかから起こったとされる。当時幕府は、庶民の土地の移動をおさえ、キリスト教の流入を防ぐために寺請制度・檀家制度をもうけ、檀家の家々にキリスト教信者がいるか否かを調べさせるために僧侶が起用された。以来、盆経に僧侶が棚をみわたすところから、棚経とよばれるようになった。 <日蓮宗事典より>
要するに、お盆のお経回り・檀家さん回り、のことです。 1軒・1軒 すべての檀家さんのお家を伺って、仏壇でお経をあげさせていただきます。
この時期は 毎朝7時にお寺を出て、夕方6時頃に帰るという 何となく、サラリーマンの生活のようであります。 春・秋のお彼岸と お盆と暮れ、計年4回ですが、お彼岸からお盆までは約5ケ月と開くので、久しぶりに伺ったお宅で つたい歩きだった赤ちゃんが、トコトコ歩いていたりするのを見るのはとっても嬉しい。 お年寄り留守番している家が ほとんどですが、皆 暖かく迎えてくれて お経の後 お茶をいただきながら 四方山話に花を咲かせるのも 楽しい時間です。
今日は 裏の山をひとつ越えた所の集落、「稲子地区」からスタートしましたが、もっぱらの話題は 猿の被害でした。 畑のトマト、かぼちゃ、スイカ、きゅうり、なす、しいたけまでが 場所によっては全滅状態です。 ネットをかけても、効果はなく、一人暮らしのお年寄りは 恐怖を感じるといいます。 玄関から堂々と進入し、仏壇に供えてある 果物等の供物が持っていかれるので、昼間から鍵をかけてある家もあります。 いのしし、鹿、たぬき、白鼻心(ハクビシン)そして猿と 野生動物による被害は増大する一方ですが 少なくとも 私が子供のころ それらの動物が ここの山に生息するなど聞いた事もありませんでした。
野生動物に餌付けなどするべきではない。 時、すでに遅し、の感もありますが、何とか動物と人間の棲み分けができるような かつての環境に少しでも 戻してやることが肝要だと思います。

こんな格好で回っています。
棚経=お盆に僧侶が檀家を回って精霊に経を誦し、回向すること。 棚経についての語義的いわれは、徳川幕府の宗教政策の一つである寺請制度のなかから起こったとされる。当時幕府は、庶民の土地の移動をおさえ、キリスト教の流入を防ぐために寺請制度・檀家制度をもうけ、檀家の家々にキリスト教信者がいるか否かを調べさせるために僧侶が起用された。以来、盆経に僧侶が棚をみわたすところから、棚経とよばれるようになった。 <日蓮宗事典より>
要するに、お盆のお経回り・檀家さん回り、のことです。 1軒・1軒 すべての檀家さんのお家を伺って、仏壇でお経をあげさせていただきます。
この時期は 毎朝7時にお寺を出て、夕方6時頃に帰るという 何となく、サラリーマンの生活のようであります。 春・秋のお彼岸と お盆と暮れ、計年4回ですが、お彼岸からお盆までは約5ケ月と開くので、久しぶりに伺ったお宅で つたい歩きだった赤ちゃんが、トコトコ歩いていたりするのを見るのはとっても嬉しい。 お年寄り留守番している家が ほとんどですが、皆 暖かく迎えてくれて お経の後 お茶をいただきながら 四方山話に花を咲かせるのも 楽しい時間です。
今日は 裏の山をひとつ越えた所の集落、「稲子地区」からスタートしましたが、もっぱらの話題は 猿の被害でした。 畑のトマト、かぼちゃ、スイカ、きゅうり、なす、しいたけまでが 場所によっては全滅状態です。 ネットをかけても、効果はなく、一人暮らしのお年寄りは 恐怖を感じるといいます。 玄関から堂々と進入し、仏壇に供えてある 果物等の供物が持っていかれるので、昼間から鍵をかけてある家もあります。 いのしし、鹿、たぬき、白鼻心(ハクビシン)そして猿と 野生動物による被害は増大する一方ですが 少なくとも 私が子供のころ それらの動物が ここの山に生息するなど聞いた事もありませんでした。
野生動物に餌付けなどするべきではない。 時、すでに遅し、の感もありますが、何とか動物と人間の棲み分けができるような かつての環境に少しでも 戻してやることが肝要だと思います。

こんな格好で回っています。
Posted by kotokuji at
21:07
│Comments(0)
2010年07月27日
お寺で遊ぼッ!
毎年 8月16日は 興徳寺の 「川施餓鬼」。
この柚野の里を 北から南に 「芝川」という一級河川が流れています。 大事な農業用水・生活用水として、夏には、子供たちの格好の遊び場として 昔から無くてはならない存在でした。 しかし、水は冷たく、急流のため、溺死する方も 多くあったようです。
「川施餓鬼」は その年に亡くなられた水没者の霊に対する回向供養と 施餓鬼法要、お盆の送り火、投げタイマツなどが合わさって出来上がった行事かと思われますが、歴史は古く、村の長老たちが子供の頃に存在したとのこと。私も 子供のころ 燃えるタイマツをわざと揺らして火の粉を飛ばしながら 走った記憶があります。
6年前、私がここに戻ってきたとき、 地元の子ども会によって この行事が続けられていることを知り、大変嬉しく思い、以来、子供たちが喜んでくれたら という思いをベースに 周りの大人たちも一緒に楽しませていただきましょう、という行事を続けてきました。
今年 子供たちに配ったチラシ、縮小してあるので 読みにくいかも知れませんが。

8月16日 11時 興徳寺に集合。 マイ箸 と マイ・カップを作ります。 12時から 「流しソーメン」。 お腹いっぱいになったら今度は タイマツを作ります。 ゲームをやって 汗をかいたら 「かき氷」「「ポン菓子」の実演、すべて食べ放題。
夕方、本堂で 「施餓鬼法要」 子供たちにも お経を読んでもらい、きっちりと作法通りに「お焼香」もします。
その後、プロの人形劇団「じゅごん」の公演、 演目は「こんじょうるり」、子供はもちろん 大人にも楽しんでもらえる40分間の大作だそうです。
あたりが 少し暗くなった頃、 法要の 灯りをいただいて タイマツに点火。 石段脇の300基の竹灯篭の灯がゆれる中を、子供たちのタイマツ行列が進みます。
芝川の 新柚野橋まで 約500メートルを歩き、ここでお経をあげ、大きな石の上にタイマツを積み上げて、燃やし 供養とします。
写真は 昨年の「川施餓鬼」です。



興味をもたれた方、遊びに来てください。
また近くに子供さんがおられたら どうぞ声をかけてあげてください。無料です。
前日の準備(流しソーメンの樋作り等)と 当日のお手伝い(ソーメンを茹でる等) のボランティア 大歓迎!!
この柚野の里を 北から南に 「芝川」という一級河川が流れています。 大事な農業用水・生活用水として、夏には、子供たちの格好の遊び場として 昔から無くてはならない存在でした。 しかし、水は冷たく、急流のため、溺死する方も 多くあったようです。
「川施餓鬼」は その年に亡くなられた水没者の霊に対する回向供養と 施餓鬼法要、お盆の送り火、投げタイマツなどが合わさって出来上がった行事かと思われますが、歴史は古く、村の長老たちが子供の頃に存在したとのこと。私も 子供のころ 燃えるタイマツをわざと揺らして火の粉を飛ばしながら 走った記憶があります。
6年前、私がここに戻ってきたとき、 地元の子ども会によって この行事が続けられていることを知り、大変嬉しく思い、以来、子供たちが喜んでくれたら という思いをベースに 周りの大人たちも一緒に楽しませていただきましょう、という行事を続けてきました。
今年 子供たちに配ったチラシ、縮小してあるので 読みにくいかも知れませんが。
8月16日 11時 興徳寺に集合。 マイ箸 と マイ・カップを作ります。 12時から 「流しソーメン」。 お腹いっぱいになったら今度は タイマツを作ります。 ゲームをやって 汗をかいたら 「かき氷」「「ポン菓子」の実演、すべて食べ放題。
夕方、本堂で 「施餓鬼法要」 子供たちにも お経を読んでもらい、きっちりと作法通りに「お焼香」もします。
その後、プロの人形劇団「じゅごん」の公演、 演目は「こんじょうるり」、子供はもちろん 大人にも楽しんでもらえる40分間の大作だそうです。
あたりが 少し暗くなった頃、 法要の 灯りをいただいて タイマツに点火。 石段脇の300基の竹灯篭の灯がゆれる中を、子供たちのタイマツ行列が進みます。
芝川の 新柚野橋まで 約500メートルを歩き、ここでお経をあげ、大きな石の上にタイマツを積み上げて、燃やし 供養とします。
写真は 昨年の「川施餓鬼」です。



興味をもたれた方、遊びに来てください。
また近くに子供さんがおられたら どうぞ声をかけてあげてください。無料です。
前日の準備(流しソーメンの樋作り等)と 当日のお手伝い(ソーメンを茹でる等) のボランティア 大歓迎!!
Posted by kotokuji at
15:01
│Comments(0)
2010年07月25日
猛暑の中の「唱題行」
毎月 第4日曜日の午後4時から『唱題行』をおこなっています。 昨年の8月にスタートしたので、ちょうど1年になりました。
最初の頃は もの珍しさもあってか 10数名の参加者がありましたが、最近は10名位で落ち着いています。 (因みに本日は、私を入れて10名でした)
「唱題行」は、2500年前、お釈迦さまがインドのブッダガヤにおいて、お悟りをお開きになられた「お姿」「呼吸」「境地」を、末法に生きる私たちが、時間、空間を越えて、私たち自身の内面に再現するための修行法―――<唱題行入門講座より抜粋>―――
私が、初めてこの「唱題行」と出会ったのは、出家して間もなくのこと。 千葉県の清澄寺にて行われた、最初の合宿修行でした。
灯りを落とした本堂で、仏様の中に溶けた~という 体が震えるような感動をし、 後にこれを「我入仏・仏入我」ということと知りましたが、実に 理に適った修行法だと思いました。
私自身が まったくの未熟なものですが、これからも ともに 励んでゆきたいと 願っています。
少しでも 興味のある方、是非1度参加してみてください。

それにしても 今日の暑かったこと! 本堂の中で 31度でした。
参加してくださった皆様、本当にご苦労様でした。
次回は 8月22日です。
最初の頃は もの珍しさもあってか 10数名の参加者がありましたが、最近は10名位で落ち着いています。 (因みに本日は、私を入れて10名でした)
「唱題行」は、2500年前、お釈迦さまがインドのブッダガヤにおいて、お悟りをお開きになられた「お姿」「呼吸」「境地」を、末法に生きる私たちが、時間、空間を越えて、私たち自身の内面に再現するための修行法―――<唱題行入門講座より抜粋>―――
私が、初めてこの「唱題行」と出会ったのは、出家して間もなくのこと。 千葉県の清澄寺にて行われた、最初の合宿修行でした。
灯りを落とした本堂で、仏様の中に溶けた~という 体が震えるような感動をし、 後にこれを「我入仏・仏入我」ということと知りましたが、実に 理に適った修行法だと思いました。
私自身が まったくの未熟なものですが、これからも ともに 励んでゆきたいと 願っています。
少しでも 興味のある方、是非1度参加してみてください。

それにしても 今日の暑かったこと! 本堂の中で 31度でした。
参加してくださった皆様、本当にご苦労様でした。
次回は 8月22日です。
Posted by kotokuji at
21:16
│Comments(0)
2010年07月23日
暑い~っ!
今朝、5時40分 本堂内の寒暖計が28度。 「今日も暑いゾ~」 と思わせる1日のスタートです。
昨日のことです。 久々に時間が空いたので、たまりにたまった寺務(お寺の事務仕事)に着手しました。 私にとって もっともやる気のでない 会計処理から。 伝票を机いっぱいに広げて 種分けうをするのですが 伝票が舞ってしまうので 扇風機の角度を微妙に調節する、当然 暑い。 私が仕事場にしているのは 庫裏の奥の6畳間で 風通しも悪く(クーラーはない)、おまけに 採光のため天井を切ってあるので 昼過ぎには 直射日光が射して 部屋の中で日焼けしそう(?)です・・・・
汗ダクダクになって、頭はボーッとしてきて、こりゃアカンと カメラ片手に外に出てみました。
外は 風が吹いて 暑いながらも気持ちがいい。
最初に出会ったのが 『サクラ』、 弟が彼女からもらった という由緒ある(?)名犬ですが、さすが暑さには勝てず、日陰に潜り込んでいました・・・

そのまま、サンダルで裏山にのぼってみます。 久しぶりの「富士山」。 夏の富士は 雄雄しくて かつ神々しい。 このお寺に富士山があったことは 本当に幸せです。

気分がスカッとしたところで 部屋に戻る前に 前日 友人のタカシちゃんが持ってきてくれた トマトを 丸ごとガブリ!
畑で完熟したトマトを 流しっぱなしの清水で冷やして 食べる・・・ なんとも ゼイタクなこと!

さぁ~ 仕事しよう! と部屋に戻って その前に今の感激をブログに入れときましょ、と書き始めたのに ナント、なんと~
またまた 写真が貼り付けられないじゃありませんか、 汗にまみれて悪戦苦闘してみたけど 結局、あきらめざるを得ませんでした・・・
一夜 明けて 本日・・・ 再び あちこちを ごちゃごちゃと触っていたら、 ポコンと写真が 挿入できた。 一体 昨日のあの苦労は何だったのか、と思うのですが、こうやって 人は成長していくのです。
それにしても、今日の暑さときたら・・・ 私が今 座っている所が 32度です。

(私の仕事場です)
午前中、お墓での回向が2軒あったのですが、くらくらするような炎天下、出てくる言葉は「いや~暑いですね~」「今年は特別ですね~」「アッチィ~・アッチィ~ 」 いくら言ったって 暑いものは暑い。 坊さんは 下着・襦袢・白衣・法衣・袈裟・袴と重装備、それに比べてアナタ いくら 平服でいいですよ と言われたからって、タンクトップに短パンですか~?
昨日のことです。 久々に時間が空いたので、たまりにたまった寺務(お寺の事務仕事)に着手しました。 私にとって もっともやる気のでない 会計処理から。 伝票を机いっぱいに広げて 種分けうをするのですが 伝票が舞ってしまうので 扇風機の角度を微妙に調節する、当然 暑い。 私が仕事場にしているのは 庫裏の奥の6畳間で 風通しも悪く(クーラーはない)、おまけに 採光のため天井を切ってあるので 昼過ぎには 直射日光が射して 部屋の中で日焼けしそう(?)です・・・・
汗ダクダクになって、頭はボーッとしてきて、こりゃアカンと カメラ片手に外に出てみました。
外は 風が吹いて 暑いながらも気持ちがいい。
最初に出会ったのが 『サクラ』、 弟が彼女からもらった という由緒ある(?)名犬ですが、さすが暑さには勝てず、日陰に潜り込んでいました・・・

そのまま、サンダルで裏山にのぼってみます。 久しぶりの「富士山」。 夏の富士は 雄雄しくて かつ神々しい。 このお寺に富士山があったことは 本当に幸せです。

気分がスカッとしたところで 部屋に戻る前に 前日 友人のタカシちゃんが持ってきてくれた トマトを 丸ごとガブリ!
畑で完熟したトマトを 流しっぱなしの清水で冷やして 食べる・・・ なんとも ゼイタクなこと!

さぁ~ 仕事しよう! と部屋に戻って その前に今の感激をブログに入れときましょ、と書き始めたのに ナント、なんと~
またまた 写真が貼り付けられないじゃありませんか、 汗にまみれて悪戦苦闘してみたけど 結局、あきらめざるを得ませんでした・・・
一夜 明けて 本日・・・ 再び あちこちを ごちゃごちゃと触っていたら、 ポコンと写真が 挿入できた。 一体 昨日のあの苦労は何だったのか、と思うのですが、こうやって 人は成長していくのです。
それにしても、今日の暑さときたら・・・ 私が今 座っている所が 32度です。

(私の仕事場です)
午前中、お墓での回向が2軒あったのですが、くらくらするような炎天下、出てくる言葉は「いや~暑いですね~」「今年は特別ですね~」「アッチィ~・アッチィ~ 」 いくら言ったって 暑いものは暑い。 坊さんは 下着・襦袢・白衣・法衣・袈裟・袴と重装備、それに比べてアナタ いくら 平服でいいですよ と言われたからって、タンクトップに短パンですか~?
Posted by kotokuji at
13:51
│Comments(0)
2010年07月19日
マウンテン・リリィ?
梅雨明け宣言! 昨朝そして今朝と 久しぶりに富士山がその美しい姿を現してくれました。 両日とも 朝のお勤めの前(5:40頃)だったのですが、お経が終わる頃には姿を隠してしまい、残念ながら カメラに収める事はできませんでした。 夏の富士山は雄々しくて、とっても雄大です。
さて、今 興徳寺の境内のあちこちで 「山百合」の花がいっせいに咲き誇り、香りが 風にのって 部屋の中まで流れてきます。





そういえば 先日 檀家さんのお家に伺ったとき、こんな話を聞きました。
「まったく近頃の子供ときたら・・・」 その家の小学校2年生の男の子のことです。
学校で先生に教わったとかで、山百合のことを 『マウンテン・リリィ』 と呼ぶのだそう。 「そりゃ、山百合のことを英語で言ってるだけだ。」 と言っても 「いや、マウンテン・リリィだ」 ときかないのだそうです。
帰ってから、念のため マウンテン・リリィ という別の植物があるのか調べてみましたが存在せず。 また 「山百合」は英語では、「a golden-banded lily] と呼ぶのだそうです。 件の先生が何を根拠に教えたのか解りませんが、おかしな話だと思います。
*やっと 写真が貼り付けられるようになりました。これからは 興徳寺のあちこちを紹介します。
Posted by kotokuji at
19:30
│Comments(0)
2010年07月16日
集中豪雨
西日本を中心に 各地で集中豪雨による被害が拡大しています。 被害に遭われた多くの方たちには 心からのお見舞いを申し上げるとともに、一刻も早い復興を 祈念いたします。
今から15年も前のことですが、私も床上浸水を体験したことがあります。 ブラジル・サンパウロ市で小さな建築会社を興し、数年が経過した頃でした。 前に広い庭のある家を借りて、社屋としていたのですが、道路より低い土地で、集中豪雨であっという間に浸水してしまいました。 平日の夕刻で たまたま私は不在だったのですが、居合わせた社員も為す術もなく、パソコンを引き揚げるのがやっと、という状況でした。 もっとも被害の大きかったのが 一番奥にあった私の部屋で、机の上まで水に浸かり、おまけに壁が水圧に耐えられなくて崩壊したので かなりのものが流出してしまいました。
翌日、カラッと晴れた青空のもと、復旧作業を開始しました。 当時、私がもっとも大事にしていた すでに終わった工事や見積もりを作成するのに必要な材料のファイル、それらを泥の中から引き出し、洗って一枚一枚薄皮を剥ぐように取り出して、干す・・・という気の遠くなるような作業でした。
しかし、どんなに丁寧に取り扱っても破れてしまうものもあるし、流出してしまったものもある。 完全復帰は不可能と知ったとき、すべての書類を放棄することを決めました。 それは「エェイ、どうにでもなれ!」といった 半ばヤケッパチな気持ちだったと思います。
創業間もない会社にあって、背面のキャビネットに並べられたファイルは、ある意味で勲章のような、また仕事を続けていくうえでは もっとも大切なものであると思っていました。 それらすべてを失い、何もなくなったガランとした部屋で、私は虚しかった・・・
しかし、しかし・・・ 結局のところ、それらを失って 困った事は 実は何もなかったのです・・・
以来、私は終わってしまった事に あまり未練をもたなくなりました。 思い出は とっても大事なもの、でもそれは自分の心に しまっておけばいい。 いつか役立つだろうからと色んなものを 溜めていっても その ‘いつか‘ は永遠に来ないかもしれない。 たとえ(その時が)来た所で それがすぐに取り出せなければ意味もないし、なくったって それはそれで何とかなるもの。
当時、いろんな方から お見舞いやら 励ましの言葉をいただきました。 そんな中で、一番嬉しかったのは、 何となく偉そうに見えていたある仲間から 「俺にできること何かない? どんなことでもいいから言って」 と言われたこと。 ただ 「がんばれよ!」 じゃなくて、このような具体的な言葉が 人を感動させるのだ、と知りました。
*「紙上法話」 と 「住職のひとりごと」 更新されました。
今から15年も前のことですが、私も床上浸水を体験したことがあります。 ブラジル・サンパウロ市で小さな建築会社を興し、数年が経過した頃でした。 前に広い庭のある家を借りて、社屋としていたのですが、道路より低い土地で、集中豪雨であっという間に浸水してしまいました。 平日の夕刻で たまたま私は不在だったのですが、居合わせた社員も為す術もなく、パソコンを引き揚げるのがやっと、という状況でした。 もっとも被害の大きかったのが 一番奥にあった私の部屋で、机の上まで水に浸かり、おまけに壁が水圧に耐えられなくて崩壊したので かなりのものが流出してしまいました。
翌日、カラッと晴れた青空のもと、復旧作業を開始しました。 当時、私がもっとも大事にしていた すでに終わった工事や見積もりを作成するのに必要な材料のファイル、それらを泥の中から引き出し、洗って一枚一枚薄皮を剥ぐように取り出して、干す・・・という気の遠くなるような作業でした。
しかし、どんなに丁寧に取り扱っても破れてしまうものもあるし、流出してしまったものもある。 完全復帰は不可能と知ったとき、すべての書類を放棄することを決めました。 それは「エェイ、どうにでもなれ!」といった 半ばヤケッパチな気持ちだったと思います。
創業間もない会社にあって、背面のキャビネットに並べられたファイルは、ある意味で勲章のような、また仕事を続けていくうえでは もっとも大切なものであると思っていました。 それらすべてを失い、何もなくなったガランとした部屋で、私は虚しかった・・・
しかし、しかし・・・ 結局のところ、それらを失って 困った事は 実は何もなかったのです・・・
以来、私は終わってしまった事に あまり未練をもたなくなりました。 思い出は とっても大事なもの、でもそれは自分の心に しまっておけばいい。 いつか役立つだろうからと色んなものを 溜めていっても その ‘いつか‘ は永遠に来ないかもしれない。 たとえ(その時が)来た所で それがすぐに取り出せなければ意味もないし、なくったって それはそれで何とかなるもの。
当時、いろんな方から お見舞いやら 励ましの言葉をいただきました。 そんな中で、一番嬉しかったのは、 何となく偉そうに見えていたある仲間から 「俺にできること何かない? どんなことでもいいから言って」 と言われたこと。 ただ 「がんばれよ!」 じゃなくて、このような具体的な言葉が 人を感動させるのだ、と知りました。
*「紙上法話」 と 「住職のひとりごと」 更新されました。
Posted by kotokuji at
19:31
│Comments(0)
2010年07月13日
興徳寺便り
「興徳寺便り88号(復刊13号)」を発行しました。檀家さん向けの「寺報」といったものです。
昭和50年、先代住職である私の父親が発刊し、平成10年、75号まで続けたものを、3年前に復刊させました。以来、年4回発行しています。 A3両面(A4x4ページ)で、1ページ目が法話=今の私が理解する仏さまの教えをできるだけ解りやすい言葉で伝えたいという、いわば私からのメッセージ。2ページは予定とトピックス。3ページは興徳寺のニュース。最後のページは「住職のひとりごと」というタイトルで、所感を書いています。
問題は1ページ目で、いわばこの便りの目玉というべきところですが いつもいつも 苦労してます。 ①私が感動し、かつ解りやすい詩を紹介する ②その詩から導き出して、ほとけ様の教えを伝える ③その内容に合わせた写真を 友人の写真家、ミキオちゃんこと高瀬幹雄氏に依頼する ④ 限られた枠の中で文章をはめこむ。 マ、こんなことですが、それぞれのプロセスがそれぞれに大変。毎回ギリギリになって頼むので、ミキオちゃんだって困ってしまうはず・・・ゴメン!
今回は 小林育子さんの 「ピンチの時のお願い」 という詩をとりあげさせていただきました。 今、ピンチの状況にある人に対し、僧侶として具体的に何をさせていただけるか? 謙虚に真摯に取り組んでいきたいテーマであります。 ホームページでも「紙上法話」として 間もなく掲載されますので、読まれた方はまた感想をお寄せください。
ところでこのホームページで、「紙上法話」を掲載して気がついたこと。それは限られた紙面上で、レイアウトも配慮しながら、きっちりと埋め込んだ文章は、まだそれなりの緊張感もあって、総合的なまとまりもみえるけど、この横書きの枠もないページに放り投げたとたんに 拙さが丸見え。 特に、「便り」の方は対象がどちらかといえばおばあさんなので、それなりの意識で書いているのだけれど、こちらの方は当然ながら若者も多く、そこでも違和感を感じてしまうのでしょうか?
ホームページ公開で、もうひとつの問題。例えば、82号と85号で掲載した詩は、著作権の問題が発生し、もし掲載するなら毎月5千円くらいを著作権協会に払い続けなければならないとのこと、もちろん掲載をやめましたが、文意はますます伝わりにくくなりました。
インターネットは大変便利なツールではありますが、自分はやはり紙がいいな、と思います。 近頃話題になっている「アイパッド」にも、今のところ興味はもてません。
昭和50年、先代住職である私の父親が発刊し、平成10年、75号まで続けたものを、3年前に復刊させました。以来、年4回発行しています。 A3両面(A4x4ページ)で、1ページ目が法話=今の私が理解する仏さまの教えをできるだけ解りやすい言葉で伝えたいという、いわば私からのメッセージ。2ページは予定とトピックス。3ページは興徳寺のニュース。最後のページは「住職のひとりごと」というタイトルで、所感を書いています。
問題は1ページ目で、いわばこの便りの目玉というべきところですが いつもいつも 苦労してます。 ①私が感動し、かつ解りやすい詩を紹介する ②その詩から導き出して、ほとけ様の教えを伝える ③その内容に合わせた写真を 友人の写真家、ミキオちゃんこと高瀬幹雄氏に依頼する ④ 限られた枠の中で文章をはめこむ。 マ、こんなことですが、それぞれのプロセスがそれぞれに大変。毎回ギリギリになって頼むので、ミキオちゃんだって困ってしまうはず・・・ゴメン!
今回は 小林育子さんの 「ピンチの時のお願い」 という詩をとりあげさせていただきました。 今、ピンチの状況にある人に対し、僧侶として具体的に何をさせていただけるか? 謙虚に真摯に取り組んでいきたいテーマであります。 ホームページでも「紙上法話」として 間もなく掲載されますので、読まれた方はまた感想をお寄せください。
ところでこのホームページで、「紙上法話」を掲載して気がついたこと。それは限られた紙面上で、レイアウトも配慮しながら、きっちりと埋め込んだ文章は、まだそれなりの緊張感もあって、総合的なまとまりもみえるけど、この横書きの枠もないページに放り投げたとたんに 拙さが丸見え。 特に、「便り」の方は対象がどちらかといえばおばあさんなので、それなりの意識で書いているのだけれど、こちらの方は当然ながら若者も多く、そこでも違和感を感じてしまうのでしょうか?
ホームページ公開で、もうひとつの問題。例えば、82号と85号で掲載した詩は、著作権の問題が発生し、もし掲載するなら毎月5千円くらいを著作権協会に払い続けなければならないとのこと、もちろん掲載をやめましたが、文意はますます伝わりにくくなりました。
インターネットは大変便利なツールではありますが、自分はやはり紙がいいな、と思います。 近頃話題になっている「アイパッド」にも、今のところ興味はもてません。
Posted by kotokuji at
22:58
│Comments(0)
2010年07月09日
ほめあげ商法
昨日朝のTVをみて、「あっ今日はこのテーマで書こう」と思ったのですが、夜になったら 睡魔が襲って断念、まだ9時だったのですが、ほんとに夜は弱いのです。 いつも9時半~10時に寝ます。 朝は4時に起きます。 ずっと若い頃から早起きでした。 25歳からの5年間を北海道の建設会社で働いたのですが、彼の地では現場は朝7時に開始、作業員の方たちは6時過ぎには集まってくるで、我々スタッフも5時には起きます。 最初はビックリしましたが、それが習い性になったみたいです。でもあの頃は毎晩真夜中まで飲んで、ちゃんと起きて仕事していたんだから、若いというのはすごいことだと思います。
さて 『ほめあげ商法』とは・・・
「あなたの短歌を同人誌でみました。大変感動いたしました。つきましては先生の作品をより多くの方に紹介させていただきたく・・・」などという電話が突然入り、「先生」「先生」と呼ばれているうちにだんだんその気になって、掲載を承諾する。 その時に掲載料を同意するケースもありますが、たいていは後から法外な請求書が送られてきて、解約を申し出ると、「既に印刷されているので・・・」と受け付けない。怖いのは、いったん承諾すると、色んな業者が入り込んできてその数があまりにも多く、掲載紙自体が存在するのかさえ解らないというケースもあるそうです。 狙われるのは、ある程度余裕のある俳句や短歌の同人誌のメンバーや絵をやっている人、ほとんどが70歳以上で80歳以上の方も多いそうです。
ちょっとケースが違いますが、私のところにこんな電話がありました。 サッカーの試合(日本xパラグアイ)が夜中だったので、少し寝ておこうと8時に横になったのですが、9時過ぎに起こされた。お寺でこの時間の電話といえば たいていは檀家さんの訃報なので、少し緊張して受話器をとりました。
「はい、興徳寺でございます」
『こちら 月刊00と申しますが、ご住職でいらっしゃいますか?』『月刊00はご存知でしょうか?』
「知りませんが・・・」
『実は、来月号で 「芝川町の寺社仏閣」 という特集を組みまして、女優の00さんが 0月0日インタビューに伺います。ご都合はいかがでしょうか?』
「あの~ 芝川町というのは もう存在しないんですけど・・・」
『あっ、そうですか~ 失礼いたしました。でも女優の00さんは ご存知ですよね~? あのおきれいな方です』
「知らないです(本当に知らなかった) それでちょっと聞きたいのだけど、私のお寺を取材するということで、取材費をくれ、とまでは言わないけれど、まさか私が お金を払うというようなことはないでしょうね?」
『いや、掲載料はいただきます。 女優さんが行くんですから・・・』
「あ、それなら結構です。 それからお寺の住職は朝が早いので、こんな時間には電話しない方がいいですヨ」
お寺の住職さんは、どちらかというと 人を疑う事を知らない、という方が多いので、よくこの手にのりやすい。
色んな業者さんから、電話が入ります。 私はかつて、売り込みをかけていた側の人間なので、何となく相手の気持ちが解ります。 「結構です、ガチャン!」とはやらないようにしています。 逆についカワイソウになって買ってしまうこともしばしば。
「ほめあげ商法」で、高いお金を払った本人が、それなりに納得できれば それはそれでいいのだと思う。 高級クラブに一晩に何10万円と払っても、それに見合う満足度を本人が得られればイイと同じ事。でも、これは弱者を狙った詐欺です。
だから許せない。
さて 『ほめあげ商法』とは・・・
「あなたの短歌を同人誌でみました。大変感動いたしました。つきましては先生の作品をより多くの方に紹介させていただきたく・・・」などという電話が突然入り、「先生」「先生」と呼ばれているうちにだんだんその気になって、掲載を承諾する。 その時に掲載料を同意するケースもありますが、たいていは後から法外な請求書が送られてきて、解約を申し出ると、「既に印刷されているので・・・」と受け付けない。怖いのは、いったん承諾すると、色んな業者が入り込んできてその数があまりにも多く、掲載紙自体が存在するのかさえ解らないというケースもあるそうです。 狙われるのは、ある程度余裕のある俳句や短歌の同人誌のメンバーや絵をやっている人、ほとんどが70歳以上で80歳以上の方も多いそうです。
ちょっとケースが違いますが、私のところにこんな電話がありました。 サッカーの試合(日本xパラグアイ)が夜中だったので、少し寝ておこうと8時に横になったのですが、9時過ぎに起こされた。お寺でこの時間の電話といえば たいていは檀家さんの訃報なので、少し緊張して受話器をとりました。
「はい、興徳寺でございます」
『こちら 月刊00と申しますが、ご住職でいらっしゃいますか?』『月刊00はご存知でしょうか?』
「知りませんが・・・」
『実は、来月号で 「芝川町の寺社仏閣」 という特集を組みまして、女優の00さんが 0月0日インタビューに伺います。ご都合はいかがでしょうか?』
「あの~ 芝川町というのは もう存在しないんですけど・・・」
『あっ、そうですか~ 失礼いたしました。でも女優の00さんは ご存知ですよね~? あのおきれいな方です』
「知らないです(本当に知らなかった) それでちょっと聞きたいのだけど、私のお寺を取材するということで、取材費をくれ、とまでは言わないけれど、まさか私が お金を払うというようなことはないでしょうね?」
『いや、掲載料はいただきます。 女優さんが行くんですから・・・』
「あ、それなら結構です。 それからお寺の住職は朝が早いので、こんな時間には電話しない方がいいですヨ」
お寺の住職さんは、どちらかというと 人を疑う事を知らない、という方が多いので、よくこの手にのりやすい。
色んな業者さんから、電話が入ります。 私はかつて、売り込みをかけていた側の人間なので、何となく相手の気持ちが解ります。 「結構です、ガチャン!」とはやらないようにしています。 逆についカワイソウになって買ってしまうこともしばしば。
「ほめあげ商法」で、高いお金を払った本人が、それなりに納得できれば それはそれでいいのだと思う。 高級クラブに一晩に何10万円と払っても、それに見合う満足度を本人が得られればイイと同じ事。でも、これは弱者を狙った詐欺です。
だから許せない。
Posted by kotokuji at
10:20
│Comments(0)
2010年07月05日
ワールドカップ その2
週末から、法事とお葬式が重なってちょっと忙しい思いをしました。 コメントを寄せてくださっている皆様、いつもありがとうございます。 とっても励みになります。 まだ顔を合わせたことのない方からのコメントは、今更ながらではありますが インターネットの威力(?)を つくづくと感じます。 まずは、御礼まで・・・
ブラジルがオランダに負けてしまった。 すばらしい先制点の後、何とも運の悪い2点を許してしまい、敗退・・・ 守備にウエートをかけていただけに 何とも悔やまれる試合でした。 リオデジャネイロの空港に 一行が戻ったそうですが、出迎えのファンから、さんざんな抗議の嵐であったそうな。 やっぱりな、と思いつつも、ちょっとカワイソウ。 ドゥンガ監督も解任だそうで、これも仕方ないと思うけど、私自身は彼の現役時代、とっても好きな選手の一人だったので、残念です。 意外だったのはアルゼンチンで、ドイツに4x0と大敗(完敗)したのに、国民がマラドーナの続投を求めて、熱烈歓迎だったそうです。 やっぱり 英雄なんですね。
一方、わが日本。敗れたとはいえ、日本中にさわやかな風を巻き起こしてくれました。 老いも若きも、「感動をありがとう。よくやった!」と絶賛。 どちらかといえば 高校野球の ノリでしょうか?
ドラマがすばらしかった。 大会前の予選ではボロ負けで、岡田監督バッシングもかなりのものでしたが、予選1試合目、カメルーンから 辛くも一勝をもぎとって勢いにのり、優勝候補オランダ戦では0-1の惜敗なるも、デンマーク戦では3-1の完勝! 1試合ごとに充実してきて、大いなる期待をもたしてくれました。 決勝トーナメントのパラグアイ戦も、引き分け、結果としての負け、というのがなかなかよくできたシナリオで、誰をも責めず、責められず、大いなる余韻を引っ張ってくれました。
すべてが終わり、岡田監督が「日本人の魂をもって戦ってくれた」と選手を評し、選手らが異口同音に口にしたのは、チームの一体感、「チームワークのよくとれた すばらしいチームだった」と。
日蓮聖人は『異体同心事』というお手紙の中で「異体同心なれば萬事を成じ、同体異心なれば諸事叶う事なし」と述べておられますが、この週末、日蓮宗の日本中のサッカー好きのお坊さんが、このお話をつかって 法話をされただろうなと想像します。 かくいう私も、土曜日の法事で この話をいたしました。
4年に1度のサッカーのお祭り、こうなったら せめて南米を代表して ウルグアイに優勝して欲しい。
ブラジルがオランダに負けてしまった。 すばらしい先制点の後、何とも運の悪い2点を許してしまい、敗退・・・ 守備にウエートをかけていただけに 何とも悔やまれる試合でした。 リオデジャネイロの空港に 一行が戻ったそうですが、出迎えのファンから、さんざんな抗議の嵐であったそうな。 やっぱりな、と思いつつも、ちょっとカワイソウ。 ドゥンガ監督も解任だそうで、これも仕方ないと思うけど、私自身は彼の現役時代、とっても好きな選手の一人だったので、残念です。 意外だったのはアルゼンチンで、ドイツに4x0と大敗(完敗)したのに、国民がマラドーナの続投を求めて、熱烈歓迎だったそうです。 やっぱり 英雄なんですね。
一方、わが日本。敗れたとはいえ、日本中にさわやかな風を巻き起こしてくれました。 老いも若きも、「感動をありがとう。よくやった!」と絶賛。 どちらかといえば 高校野球の ノリでしょうか?
ドラマがすばらしかった。 大会前の予選ではボロ負けで、岡田監督バッシングもかなりのものでしたが、予選1試合目、カメルーンから 辛くも一勝をもぎとって勢いにのり、優勝候補オランダ戦では0-1の惜敗なるも、デンマーク戦では3-1の完勝! 1試合ごとに充実してきて、大いなる期待をもたしてくれました。 決勝トーナメントのパラグアイ戦も、引き分け、結果としての負け、というのがなかなかよくできたシナリオで、誰をも責めず、責められず、大いなる余韻を引っ張ってくれました。
すべてが終わり、岡田監督が「日本人の魂をもって戦ってくれた」と選手を評し、選手らが異口同音に口にしたのは、チームの一体感、「チームワークのよくとれた すばらしいチームだった」と。
日蓮聖人は『異体同心事』というお手紙の中で「異体同心なれば萬事を成じ、同体異心なれば諸事叶う事なし」と述べておられますが、この週末、日蓮宗の日本中のサッカー好きのお坊さんが、このお話をつかって 法話をされただろうなと想像します。 かくいう私も、土曜日の法事で この話をいたしました。
4年に1度のサッカーのお祭り、こうなったら せめて南米を代表して ウルグアイに優勝して欲しい。
Posted by kotokuji at
22:01
│Comments(0)
2010年07月01日
妻の命日
今日、7月1日は 妻の命日です。
平成17年6月末のある朝、いつものように朝のお勤めを終えて、本堂から戻った私にブラジルから電話、妻の友人でした。 曰く「初代さんが空港で倒れ、近くの病院に収容されていますが、意識不明の重態です」・・・ 弟の訃報を受けたときとまったく同じ衝撃、瞬間頭の中がカラになり、目の前がモノクロ写真になりました。
ブラジルに着いたとき、妻は集中治療室のベッドでこん睡状態。オーストラリアの長男も駆けつけ、ブラジルの次男と3人で毎日病院に通い、許された10分間、1日2回の面会時間に 一方的にしゃべり続けました。 が、容態はまったく好転せず、私は最後の手段として、ブラジルでもっとも進んでいると言われている病院への転院を考えました。 保険はきかず、助かったとしても、植物人間になる可能性大 ではありましたが、それでもやってみたいと思いました。 植物人間になった妻を、興徳寺に連れ帰って、私が面倒をみようと思いました。 知人を通じて、転院の手続きをし、家に帰ったところ 「ママイ、デスカンソウだって・・・」と息子。それは「お母さんが休息に入った」という意味のポルトガル語です。 妻が「ありがとう、ケンちゃん。もういいよ」と言ってくれたような気がしました。 不思議なくらい 悲しみもなく、子供が用意してくれた昼飯を「今夜は遅くなるし、せっかくだから腹ごしらえだけでもしておこう」と3人で食べたのです。 お母さんが死んでメシ食ってるのは 俺らくらいのもんだろう、などといいながら・・・
妻はフリーの旅行ガイドでした。 彼女にとっては大きな仕事、日本からの政府の外郭団体の職員2人を案内して 1週間サンパウロ州内をまわり(サンパウロ州といっても日本と同じくらいの面積がある)最後に空港に送り、その直後に倒れて、空港の診療所で意識を失ったそうです。 くも膜下出血でした。
彼女が携行していたショルダーバッグから、2枚の名刺がでてきたので、電話をしてみました。 1週間の間に、何か変わったことはなかったかを聞きたかったからです。 ずっと楽しく過ごす事ができて、最後に一緒に夕食をした。変わったことは何もなかった。ただ、2人がゲートに入る直前、振り向いたら車椅子に座って手を振っていた。びっくりして戻ろうとしたけど、大丈夫というようなジェスチャーをしたので、そのまま出国してしまった、と大変驚いておられました。
プロのガイドがその戦場である空港で、制服姿で逝った・・・ カッコイイジャン! とまた息子たちと。
遺骨を抱いての帰路、給油のために寄ったニューヨークの空港で、飛行機の窓から外を眺めなが「初ちゃん、もうちょっとで日本だよ」と何気なくつぶやいたとたん、何故か大粒の涙がとめどもなくあふれ出し、私は席を立つ事さえできなくなってしまいました。 あそこで 初めて現実の世界に戻れたような気がします。 それは生まれて初めて体験した深い悲しみでありました。 心にポッカリ大きな穴が開いてしまって、何もかもがそこに落ち込んでしまうようでした。 また 年を重ねるほどに、寂しいということはツライもんだ ということも知りました。
それまでの私は強い男に憧れ、「男は泣かない」をモットーに 子供たちを育ててきました。 いつも笑っていて 「明るい松永さん!」と呼ばれることを ヨシとしました。 でも、今は 泣きたきゃ泣けばいい、泣いた分だけやさしくなれる、と思います。 そして、悲しさ・寂しさを知るということが、坊さんとして 不可欠の要素であるということに気づかされたのです。
弟は事故、妻は病気でした。 でも、2人とも倒れる10分前には笑っていた、まさか自分が死ぬなんて予想だにしていなかった・・・ 私も明日は死ぬのかもしれない、と思います。 だからこそ今生きていることが、生かされていることが、ありがたいと思えます。
早いもので、来年が7回忌。 年をとったのはこっちだけで、あいつは永遠に年をとらない・・・
平成17年6月末のある朝、いつものように朝のお勤めを終えて、本堂から戻った私にブラジルから電話、妻の友人でした。 曰く「初代さんが空港で倒れ、近くの病院に収容されていますが、意識不明の重態です」・・・ 弟の訃報を受けたときとまったく同じ衝撃、瞬間頭の中がカラになり、目の前がモノクロ写真になりました。
ブラジルに着いたとき、妻は集中治療室のベッドでこん睡状態。オーストラリアの長男も駆けつけ、ブラジルの次男と3人で毎日病院に通い、許された10分間、1日2回の面会時間に 一方的にしゃべり続けました。 が、容態はまったく好転せず、私は最後の手段として、ブラジルでもっとも進んでいると言われている病院への転院を考えました。 保険はきかず、助かったとしても、植物人間になる可能性大 ではありましたが、それでもやってみたいと思いました。 植物人間になった妻を、興徳寺に連れ帰って、私が面倒をみようと思いました。 知人を通じて、転院の手続きをし、家に帰ったところ 「ママイ、デスカンソウだって・・・」と息子。それは「お母さんが休息に入った」という意味のポルトガル語です。 妻が「ありがとう、ケンちゃん。もういいよ」と言ってくれたような気がしました。 不思議なくらい 悲しみもなく、子供が用意してくれた昼飯を「今夜は遅くなるし、せっかくだから腹ごしらえだけでもしておこう」と3人で食べたのです。 お母さんが死んでメシ食ってるのは 俺らくらいのもんだろう、などといいながら・・・
妻はフリーの旅行ガイドでした。 彼女にとっては大きな仕事、日本からの政府の外郭団体の職員2人を案内して 1週間サンパウロ州内をまわり(サンパウロ州といっても日本と同じくらいの面積がある)最後に空港に送り、その直後に倒れて、空港の診療所で意識を失ったそうです。 くも膜下出血でした。
彼女が携行していたショルダーバッグから、2枚の名刺がでてきたので、電話をしてみました。 1週間の間に、何か変わったことはなかったかを聞きたかったからです。 ずっと楽しく過ごす事ができて、最後に一緒に夕食をした。変わったことは何もなかった。ただ、2人がゲートに入る直前、振り向いたら車椅子に座って手を振っていた。びっくりして戻ろうとしたけど、大丈夫というようなジェスチャーをしたので、そのまま出国してしまった、と大変驚いておられました。
プロのガイドがその戦場である空港で、制服姿で逝った・・・ カッコイイジャン! とまた息子たちと。
遺骨を抱いての帰路、給油のために寄ったニューヨークの空港で、飛行機の窓から外を眺めなが「初ちゃん、もうちょっとで日本だよ」と何気なくつぶやいたとたん、何故か大粒の涙がとめどもなくあふれ出し、私は席を立つ事さえできなくなってしまいました。 あそこで 初めて現実の世界に戻れたような気がします。 それは生まれて初めて体験した深い悲しみでありました。 心にポッカリ大きな穴が開いてしまって、何もかもがそこに落ち込んでしまうようでした。 また 年を重ねるほどに、寂しいということはツライもんだ ということも知りました。
それまでの私は強い男に憧れ、「男は泣かない」をモットーに 子供たちを育ててきました。 いつも笑っていて 「明るい松永さん!」と呼ばれることを ヨシとしました。 でも、今は 泣きたきゃ泣けばいい、泣いた分だけやさしくなれる、と思います。 そして、悲しさ・寂しさを知るということが、坊さんとして 不可欠の要素であるということに気づかされたのです。
弟は事故、妻は病気でした。 でも、2人とも倒れる10分前には笑っていた、まさか自分が死ぬなんて予想だにしていなかった・・・ 私も明日は死ぬのかもしれない、と思います。 だからこそ今生きていることが、生かされていることが、ありがたいと思えます。
早いもので、来年が7回忌。 年をとったのはこっちだけで、あいつは永遠に年をとらない・・・
Posted by kotokuji at
20:11
│Comments(0)