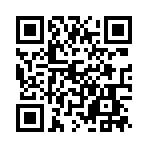2010年09月29日
はっかけばあさん
彼岸花が 境内のあちこちで 所狭しと咲き誇っています。


幼い頃、この 彼岸花 のことをなぜか 「はっかけばあさん」 と呼んでいました。 あまり 良いイメージはなく ただ意味も分からず エンギガワルイ と言っていたような記憶が あります。
彼岸花は、球根に毒があり もぐらが来ないよう 田んぼの畦(あぜ)に植えたそう。 その毒性と お彼岸という 死者につながるイメージが そう言わせたのか? と思います。
調べたところ、彼岸花には 300以上の呼び名があります。 有名なのは 曼殊沙華(まんじゅしゃげ)ですが 我が「はっかけばあさん」 も堂々と(?)登録されていました。
ところで この 「はっかけばあさん」、 当然のように 歯欠け婆さん と理解していましたが、葉が出る前に花が咲く、つまりは 葉欠け の意味という説もあります。 もっともらしい説ですが そうなると 婆さんを どう説明するのか?

去る 6月20日、「第一回 興徳寺をきれいにする日」に 裏山の 竹を伐採した跡地に この彼岸花の 球根を約40kg 皆で 手分けして植えました。 広い面積なので まだまばらですが これから 増えていくことでしょう。

来年以降、裏山全体が 真っ赤な華で埋め尽くされるかと 思うと それだけで ワクワク・ドキドキです。



幼い頃、この 彼岸花 のことをなぜか 「はっかけばあさん」 と呼んでいました。 あまり 良いイメージはなく ただ意味も分からず エンギガワルイ と言っていたような記憶が あります。
彼岸花は、球根に毒があり もぐらが来ないよう 田んぼの畦(あぜ)に植えたそう。 その毒性と お彼岸という 死者につながるイメージが そう言わせたのか? と思います。
調べたところ、彼岸花には 300以上の呼び名があります。 有名なのは 曼殊沙華(まんじゅしゃげ)ですが 我が「はっかけばあさん」 も堂々と(?)登録されていました。
ところで この 「はっかけばあさん」、 当然のように 歯欠け婆さん と理解していましたが、葉が出る前に花が咲く、つまりは 葉欠け の意味という説もあります。 もっともらしい説ですが そうなると 婆さんを どう説明するのか?

去る 6月20日、「第一回 興徳寺をきれいにする日」に 裏山の 竹を伐採した跡地に この彼岸花の 球根を約40kg 皆で 手分けして植えました。 広い面積なので まだまばらですが これから 増えていくことでしょう。

来年以降、裏山全体が 真っ赤な華で埋め尽くされるかと 思うと それだけで ワクワク・ドキドキです。

Posted by kotokuji at
17:15
│Comments(0)
2010年09月26日
青い瞳の 嫁っこ
オーストラリアに住む 長男の嫁、アリソンが 1昨日我家に。 公立高校の先生です。
私も初めて知ったのですが、オーストラリアは4学期制で 今は学期末の休みだそう。
これまた意外だったのですが オーストラリアでは 第2外国語として 日本語とフランス語を専攻する生徒がもっとも多く 中国語、ラテン語と続くそうです。 今回は 日本語を習っている生徒の中から 希望者13人が大阪の姉妹校の父兄宅にホームステイ、その引率として来て 2日間のフリーデイをもらったとのこと。
アリソンはかつて 大阪で英語塾の講師をしていたことがあり、また別の機会には静岡県の裾野市の高校で1年間教師として勤め、通算3年以上 日本に滞在しました。 だから 日本語はかなり上手(少なくとも私の英語より)です。 長男・拓朗が ブラジルから日本へ 出稼ぎに来ている時 大阪で知り合ったみたいで、当時の2人の共通語は日本語であったそう。(今は英語です)
1977年、長男が生まれたことを機に 私はブラジル移住を決め、朗らかに拓く、という意をこめて 拓朗と名づけました。 4歳でブラジルへ。22歳の頃 日本を経由してオーストラリアに渡り、苦労して大学を出て(私は一銭の仕送りもしていない)広告関係の仕事で独立しました。 一方、アリソンの両親はスコットランド人、彼の地で結婚し 2人でオーストラリアに移住しました。
この2月に結婚。日本とスコットランドから双方の親戚がそれぞれ10数人づつ、他は彼らの友人、仲間たち、計150人の手づくりの、和やかで楽しい結婚式でした。(披露宴が夜7時から なんと翌朝の5時までだった)
結婚式から帰ってきて「安心したでしょう」 とよく言われましたが、移住者の息子と 移住者の娘が こんなにスバラシイ仲間たちに支えられている ということを確認できたことが 何よりもの安心でした。
拓朗が初めてオーストラリアからブラジルに戻った時のこと、 アリソンの写真を見せられて 酔っ払っていた私は 息子に半ば嫉妬し「イイナ イイナ~ こんなきれいな娘とつきあって~」と言ったら 顔を少し赤らめて 「お父さんだって こんなきれいなお母さんと一緒になったんじゃないか~」とマジメに言ったのには、びっくりしました。


元 体操選手だそうで 頼みもしないのに こんなポーズ。 なかなか ヒョウキンな奴です。
今年の2月27日、メルボルンで 私が導師を務めて 仏式結婚式を挙げました。


私も初めて知ったのですが、オーストラリアは4学期制で 今は学期末の休みだそう。
これまた意外だったのですが オーストラリアでは 第2外国語として 日本語とフランス語を専攻する生徒がもっとも多く 中国語、ラテン語と続くそうです。 今回は 日本語を習っている生徒の中から 希望者13人が大阪の姉妹校の父兄宅にホームステイ、その引率として来て 2日間のフリーデイをもらったとのこと。
アリソンはかつて 大阪で英語塾の講師をしていたことがあり、また別の機会には静岡県の裾野市の高校で1年間教師として勤め、通算3年以上 日本に滞在しました。 だから 日本語はかなり上手(少なくとも私の英語より)です。 長男・拓朗が ブラジルから日本へ 出稼ぎに来ている時 大阪で知り合ったみたいで、当時の2人の共通語は日本語であったそう。(今は英語です)
1977年、長男が生まれたことを機に 私はブラジル移住を決め、朗らかに拓く、という意をこめて 拓朗と名づけました。 4歳でブラジルへ。22歳の頃 日本を経由してオーストラリアに渡り、苦労して大学を出て(私は一銭の仕送りもしていない)広告関係の仕事で独立しました。 一方、アリソンの両親はスコットランド人、彼の地で結婚し 2人でオーストラリアに移住しました。
この2月に結婚。日本とスコットランドから双方の親戚がそれぞれ10数人づつ、他は彼らの友人、仲間たち、計150人の手づくりの、和やかで楽しい結婚式でした。(披露宴が夜7時から なんと翌朝の5時までだった)
結婚式から帰ってきて「安心したでしょう」 とよく言われましたが、移住者の息子と 移住者の娘が こんなにスバラシイ仲間たちに支えられている ということを確認できたことが 何よりもの安心でした。
拓朗が初めてオーストラリアからブラジルに戻った時のこと、 アリソンの写真を見せられて 酔っ払っていた私は 息子に半ば嫉妬し「イイナ イイナ~ こんなきれいな娘とつきあって~」と言ったら 顔を少し赤らめて 「お父さんだって こんなきれいなお母さんと一緒になったんじゃないか~」とマジメに言ったのには、びっくりしました。


元 体操選手だそうで 頼みもしないのに こんなポーズ。 なかなか ヒョウキンな奴です。
今年の2月27日、メルボルンで 私が導師を務めて 仏式結婚式を挙げました。


Posted by kotokuji at
20:49
│Comments(0)
2010年09月23日
業務用かき氷機 を買ってしまった
そうなんです。 昨日夕刻 配達されました。
事の発端は・・・
「川施餓鬼」で使った かき氷シロップ が、余ってしまい、そうだそうだ、と「家庭用かき氷機」を買いに 町に出たのです。・・・ところが、 連日の猛暑で どの店も 完売! やっとのことで見つけた一台を買ってきて、さっそく 試してみたのですが 「ウ~ン???・・・」の連続・・・
シロップのせいか? それともそれとも・・と考えたあげく 達したある結論、「業務用カキ氷機、を買うしかない!」
私が求めていたのは フワツフワの氷、 上から蜜をかけると スッと中にしみて 表面が雪のような純白が残る あのとんがったカキ氷! 家庭用の機械では まず構造的にそれは無理だし、何よりも 氷の質そのものの問題でもあるらしい。 やはり氷屋さんの ブロック氷を カンナの理屈で うす~く スライスして初めてあの ふわふわ氷ができるのです。
もちろん 昔懐かしい 手回しの機械でもいいのだけれど 来年のイベントのことも考えれば 電動がいいなぁ~ ブロック氷を いつも冷凍庫にストックしておいて、夏に 興徳寺に来てくれた人には 誰にでも オイシイカキ氷をふるまってあげましょう。 そうなったら いちごシロップ、抹茶、小倉 などは手作りで・・・ などと 夢はふくらむばかり・・・
とりあえず ネット上で 値段を調べ、シーズンが終われば 「在庫一層処分」の掘り出し物が 出るか? などとあさましい(?)ことも思ったが 猛暑のせいか カキ氷機需要は衰えを見せず、 そのうち お彼岸で私がそれどころではなくなり、やっと一息ついた 3日前に 「今 買おう!」と決めたのです。

「カキ氷機 最新モデル」 と 今まで働いてくれた 「家庭用 カキ氷機」
昨日、配送センター まで機械が届いたことを確認し、 あわてて町に出て 一貫目(3,75キkg)の氷を買って、待ち構えて(?) いるところに 配達されました。 さっそく 作った 「カキ氷」 まさに まさに私の求めていたものでした・・・

カキ氷の定番 イチゴミルク
昨日の 猛暑にも感謝。 今年の カキ氷 ラストチャンスだったかも知れません。 今日は 雨が降って とても そのフンイキでは ありません。
オーストラリアに住む長男の嫁が 今、日本に来ていて 今夜は我家に泊まる。 今から、「新富士駅」まで 迎えに行ってきます。
事の発端は・・・
「川施餓鬼」で使った かき氷シロップ が、余ってしまい、そうだそうだ、と「家庭用かき氷機」を買いに 町に出たのです。・・・ところが、 連日の猛暑で どの店も 完売! やっとのことで見つけた一台を買ってきて、さっそく 試してみたのですが 「ウ~ン???・・・」の連続・・・
シロップのせいか? それともそれとも・・と考えたあげく 達したある結論、「業務用カキ氷機、を買うしかない!」
私が求めていたのは フワツフワの氷、 上から蜜をかけると スッと中にしみて 表面が雪のような純白が残る あのとんがったカキ氷! 家庭用の機械では まず構造的にそれは無理だし、何よりも 氷の質そのものの問題でもあるらしい。 やはり氷屋さんの ブロック氷を カンナの理屈で うす~く スライスして初めてあの ふわふわ氷ができるのです。
もちろん 昔懐かしい 手回しの機械でもいいのだけれど 来年のイベントのことも考えれば 電動がいいなぁ~ ブロック氷を いつも冷凍庫にストックしておいて、夏に 興徳寺に来てくれた人には 誰にでも オイシイカキ氷をふるまってあげましょう。 そうなったら いちごシロップ、抹茶、小倉 などは手作りで・・・ などと 夢はふくらむばかり・・・
とりあえず ネット上で 値段を調べ、シーズンが終われば 「在庫一層処分」の掘り出し物が 出るか? などとあさましい(?)ことも思ったが 猛暑のせいか カキ氷機需要は衰えを見せず、 そのうち お彼岸で私がそれどころではなくなり、やっと一息ついた 3日前に 「今 買おう!」と決めたのです。

「カキ氷機 最新モデル」 と 今まで働いてくれた 「家庭用 カキ氷機」
昨日、配送センター まで機械が届いたことを確認し、 あわてて町に出て 一貫目(3,75キkg)の氷を買って、待ち構えて(?) いるところに 配達されました。 さっそく 作った 「カキ氷」 まさに まさに私の求めていたものでした・・・

カキ氷の定番 イチゴミルク
昨日の 猛暑にも感謝。 今年の カキ氷 ラストチャンスだったかも知れません。 今日は 雨が降って とても そのフンイキでは ありません。
オーストラリアに住む長男の嫁が 今、日本に来ていて 今夜は我家に泊まる。 今から、「新富士駅」まで 迎えに行ってきます。
Posted by kotokuji at
10:21
│Comments(0)
2010年09月21日
雨蛙めんどうくさき余生かな
毎朝 本堂でのお勤めの後 お墓でお経を読みます。 興徳寺の歴代住職の廟(びょう)と 永代供養墓、そして松永家のお墓 です。 その時々の 朝の空気を感じる事ができる 大変気持ちのイイ時間です。

今朝 お墓の石垣で 出会った「雨蛙」 石と同じ色に変身してじっと うずくまっている姿が 何ともいじらしく あわててカメラを取りに戻って 撮った1枚。
「雨蛙 めんどくさき 余生かな」 永田耕衣(1900-1997)
雨蛙は 環境に合わせて自分の体の色を変えることができる。 私たち 人間は この保護色という機能は持ちあわせてはいないけれど、 相手によって態度を変えたりします。 目上の人、目下の人、お客さん、友人、恋人・・・ それがエチケットでもあるわけだけど 年をとると それがだんだんメンドウクサクなる。いよいよ余生に入ったかな? ・・・・永田耕衣の晩年の句だそうですが 私はそんな風に理解しました。
もう20年近くも前のことですが・・・ 亀井民治著「実践経営指南録」という本を読んでいたら、こんな一節に出会いました。
「老化とは億劫がる心」と題して「身体を動かすのが億劫、歩くのが億劫、出掛けて行くのが億劫、人に会うのが億劫、手紙を書くのが億劫、仕事のやり方を考えるのが億劫、考えるのが億劫、風呂に入るのが億劫、そして食べるのが億劫となって死に至る」・・・
当時の私は 今では信じられないような話ですが 酒好きで、毎晩のように飲み歩き 午前様が当たり前、やっとのことで家にたどりつくと そのままベッドに倒れ込む・・・ 当然のことのように 風呂など入らない。「宮本武蔵は生涯風呂に入らなかったらしい」という どこかで聞いてきたセリフを信じていたようでもありますが、この本を読んで 何と俺は 死に至る一歩手前だ! と気づき、それから 毎晩風呂に入るようになったのであります。 妻が喜んだのは言うまでもなく、作者の亀井さんにブラジルから お礼の手紙を出し、亀井さんからは、ご丁寧な御返事をいただき、そのご縁で 本日まで親しくさせていただいております。
改めて、雨蛙 の話。
エチケットとしての 保護色は必要かもしれませんが、 自分は自分らしく そのまんまで生きるのが、楽でいいなぁ~ と思います。

昨日の興徳寺よりの 富士山
おかげさまで 「彼岸法要」への参加者も 少しづつ 増えてきて、今回はちょうど50名でした。
書いた お塔婆は 68本。 嬉しい事です。

参詣の方に 差し上げた 「おはぎ」。 生まれて初めて(かなりいい年になってから)この 中にあんこ の入ったおはぎを食べた時の感激が忘れられなくて 特注しています。

今朝 お墓の石垣で 出会った「雨蛙」 石と同じ色に変身してじっと うずくまっている姿が 何ともいじらしく あわててカメラを取りに戻って 撮った1枚。
「雨蛙 めんどくさき 余生かな」 永田耕衣(1900-1997)
雨蛙は 環境に合わせて自分の体の色を変えることができる。 私たち 人間は この保護色という機能は持ちあわせてはいないけれど、 相手によって態度を変えたりします。 目上の人、目下の人、お客さん、友人、恋人・・・ それがエチケットでもあるわけだけど 年をとると それがだんだんメンドウクサクなる。いよいよ余生に入ったかな? ・・・・永田耕衣の晩年の句だそうですが 私はそんな風に理解しました。
もう20年近くも前のことですが・・・ 亀井民治著「実践経営指南録」という本を読んでいたら、こんな一節に出会いました。
「老化とは億劫がる心」と題して「身体を動かすのが億劫、歩くのが億劫、出掛けて行くのが億劫、人に会うのが億劫、手紙を書くのが億劫、仕事のやり方を考えるのが億劫、考えるのが億劫、風呂に入るのが億劫、そして食べるのが億劫となって死に至る」・・・
当時の私は 今では信じられないような話ですが 酒好きで、毎晩のように飲み歩き 午前様が当たり前、やっとのことで家にたどりつくと そのままベッドに倒れ込む・・・ 当然のことのように 風呂など入らない。「宮本武蔵は生涯風呂に入らなかったらしい」という どこかで聞いてきたセリフを信じていたようでもありますが、この本を読んで 何と俺は 死に至る一歩手前だ! と気づき、それから 毎晩風呂に入るようになったのであります。 妻が喜んだのは言うまでもなく、作者の亀井さんにブラジルから お礼の手紙を出し、亀井さんからは、ご丁寧な御返事をいただき、そのご縁で 本日まで親しくさせていただいております。
改めて、雨蛙 の話。
エチケットとしての 保護色は必要かもしれませんが、 自分は自分らしく そのまんまで生きるのが、楽でいいなぁ~ と思います。

昨日の興徳寺よりの 富士山
おかげさまで 「彼岸法要」への参加者も 少しづつ 増えてきて、今回はちょうど50名でした。
書いた お塔婆は 68本。 嬉しい事です。

参詣の方に 差し上げた 「おはぎ」。 生まれて初めて(かなりいい年になってから)この 中にあんこ の入ったおはぎを食べた時の感激が忘れられなくて 特注しています。
Posted by kotokuji at
17:09
│Comments(0)
2010年09月17日
ぼたもち と おはぎ
お彼岸の お経廻り、本日をもって ほぼ終了。 明日は 『彼岸法要』 の準備です。
ところで 「お彼岸って何?」 と聞かれて、 「それはね~・・・」と きちっと応えられる人って どれくらいいるでしょうか? 私も 恥ずかしながら、出家する前は知りませんでした。 先祖のお墓参りして おはぎ を食べる日・・・?
この ホームページの 行事案内、「お彼岸」 の項に 簡単な説明を載せておきましたので 知らない方は ご覧になってください。http://kotokuji.jp/event.html#higan
さて、それでは ぼたもち と おはぎ の違いは?
こしあんがおはぎで、粒あんがぼたもち という説、 米粒が残っているのがおはぎで、完全に餅になっているのがぼたもち という説もありますが 基本的に同じもので 春が牡丹で ぼたもち(牡丹餅)、秋は萩で おはぎ(お萩)と言います。 ですが いわゆる高級和菓子屋さんは 年中通して 「おはぎ」と呼ぶ所が多く また スーパーマーケットなどで売られているものでは 大きいのがぼたもちで、小さいのがおはぎ と 分けているメーカーもあります ・・・持ち前の好奇心で調べて 最初の頃 彼岸法要の法話のネタに使いました・・・
『彼岸法要』 明後日(19日)の10時から。 どなたでも参詣できます。 皆で一緒にお経を唱え、その後、私の「法話」。 帰りに 「特製おはぎ(きなこの中にあんこが入っている)」 をプレゼントします。 近くの方、是非 いらしてください。
お経廻りの途中で 出会った 「案山子」




ところで 「お彼岸って何?」 と聞かれて、 「それはね~・・・」と きちっと応えられる人って どれくらいいるでしょうか? 私も 恥ずかしながら、出家する前は知りませんでした。 先祖のお墓参りして おはぎ を食べる日・・・?
この ホームページの 行事案内、「お彼岸」 の項に 簡単な説明を載せておきましたので 知らない方は ご覧になってください。http://kotokuji.jp/event.html#higan
さて、それでは ぼたもち と おはぎ の違いは?
こしあんがおはぎで、粒あんがぼたもち という説、 米粒が残っているのがおはぎで、完全に餅になっているのがぼたもち という説もありますが 基本的に同じもので 春が牡丹で ぼたもち(牡丹餅)、秋は萩で おはぎ(お萩)と言います。 ですが いわゆる高級和菓子屋さんは 年中通して 「おはぎ」と呼ぶ所が多く また スーパーマーケットなどで売られているものでは 大きいのがぼたもちで、小さいのがおはぎ と 分けているメーカーもあります ・・・持ち前の好奇心で調べて 最初の頃 彼岸法要の法話のネタに使いました・・・
『彼岸法要』 明後日(19日)の10時から。 どなたでも参詣できます。 皆で一緒にお経を唱え、その後、私の「法話」。 帰りに 「特製おはぎ(きなこの中にあんこが入っている)」 をプレゼントします。 近くの方、是非 いらしてください。
お経廻りの途中で 出会った 「案山子」




Posted by kotokuji at
21:15
│Comments(0)
2010年09月14日
そとうば・そとば?
前回、お塔婆について書いたところ 読者の方からコメントをいただきました。
要約しますと・・・昔読んだ小説で 卒塔婆に‘そとば’とルビがふられていたのでずっとそう呼んできたのだけれど、私の文章で‘そとうば’と読むのが正しいと知った・・・
私の方がちょっと言葉足らずだったみたいなので 補足します。
卒塔婆は サンスクリット語 ストゥーパ(stu-pa)の音訳 で ‘そとば’ もしくは ‘そとうば’ と読みます。 私は ルビをつける時は そとば、 発音するときは そとうば かな? どちらも 正解ということで ご理解ください。 コメントありがとうございました。
さて、お彼岸のお経廻りも あと数日というところ、 今日は 三島市の檀家さんに行って来ました。40kmほどの距離ですが、東名高速道路を使います。
ちょっと前のことですが、東名高速のサービスエリアに入り、バイク専用の駐車場に停めたときのこと。 ズラッとかっこいい大型バイクが並び、レザーウェアでビシッときめたライダーたちが 談笑しながらコーヒーなどを飲んでいる・・・ そこに現れた私のいでたちときたら 坊さんルックに袂(たもと)が はためかないよう、たすきをかけ、足元は雪駄(せった)・・・ 何ともいえない 気まずさ・恥ずかしさを感じたのです。 ライダーに対してのマナー違反というか エチケット違反というか あるいは 神聖なる 高速道路に対する冒涜というか・・・ 以来、レザーとまではいかないけれど 高速道路を走る時は、袖口がピシッしたジャケットに レーシングブーツを着用します。
当たり前のことですが 運転しやすく、安全です。
でも インター出てから、 コンビニの駐車場などで 再び坊さんルックに着替える時は あまり見られたくない、と正直思いますが・・・
昨日の富士山は とっても美しかった・・・ 今日は見えませんでした。

これは 興徳寺からの富士山です。
・・・友人の母親が亡くなって(行年90歳) お通夜に行って来ました。 喪主(友人の父親)の挨拶が よかった。
「結婚して 60数年、ずっと家内に喜ばれたくて 生きてきました。 突然、逝かれて 一人ぼっちになってしまいましたが、これからも 家内が喜んでくれるように 生きてゆきたいと思います。」
お父様の お年を確認できませんでしたが、少なくとも 奥様と同じくらいだと思います。
ステキなご夫婦だったんでしょうね。
要約しますと・・・昔読んだ小説で 卒塔婆に‘そとば’とルビがふられていたのでずっとそう呼んできたのだけれど、私の文章で‘そとうば’と読むのが正しいと知った・・・
私の方がちょっと言葉足らずだったみたいなので 補足します。
卒塔婆は サンスクリット語 ストゥーパ(stu-pa)の音訳 で ‘そとば’ もしくは ‘そとうば’ と読みます。 私は ルビをつける時は そとば、 発音するときは そとうば かな? どちらも 正解ということで ご理解ください。 コメントありがとうございました。
さて、お彼岸のお経廻りも あと数日というところ、 今日は 三島市の檀家さんに行って来ました。40kmほどの距離ですが、東名高速道路を使います。
ちょっと前のことですが、東名高速のサービスエリアに入り、バイク専用の駐車場に停めたときのこと。 ズラッとかっこいい大型バイクが並び、レザーウェアでビシッときめたライダーたちが 談笑しながらコーヒーなどを飲んでいる・・・ そこに現れた私のいでたちときたら 坊さんルックに袂(たもと)が はためかないよう、たすきをかけ、足元は雪駄(せった)・・・ 何ともいえない 気まずさ・恥ずかしさを感じたのです。 ライダーに対してのマナー違反というか エチケット違反というか あるいは 神聖なる 高速道路に対する冒涜というか・・・ 以来、レザーとまではいかないけれど 高速道路を走る時は、袖口がピシッしたジャケットに レーシングブーツを着用します。
当たり前のことですが 運転しやすく、安全です。
でも インター出てから、 コンビニの駐車場などで 再び坊さんルックに着替える時は あまり見られたくない、と正直思いますが・・・
昨日の富士山は とっても美しかった・・・ 今日は見えませんでした。


これは 興徳寺からの富士山です。
・・・友人の母親が亡くなって(行年90歳) お通夜に行って来ました。 喪主(友人の父親)の挨拶が よかった。
「結婚して 60数年、ずっと家内に喜ばれたくて 生きてきました。 突然、逝かれて 一人ぼっちになってしまいましたが、これからも 家内が喜んでくれるように 生きてゆきたいと思います。」
お父様の お年を確認できませんでしたが、少なくとも 奥様と同じくらいだと思います。
ステキなご夫婦だったんでしょうね。
Posted by kotokuji at
21:49
│Comments(0)
2010年09月11日
お塔婆 って?
今月 19日(日)の「彼岸法要」に向けて、毎日、「お塔婆」を書いています。
ところで 「お塔婆」って ご存知ですか?
かなり前のことですが、友達の女の子との 電話での会話。
「何してんの~?」
「お塔婆、書いてんの。 ところで お塔婆って知ってる?」
「オト~バァ~ッ? あぁ~ あのお化け屋敷に 立ってるあれでしょ?」
・・・・ お化け屋敷の小道具ですか~ こちらがビックリです。(マレーシアに住んでる サクラさん! アンタのことだよッ、覚えてる?)
こんなこともありました。 夏休みのある夜 小学生が肝試しをやるので お寺の境内を使わせて欲しい、との申し入れ、もちろんOKですが・・・
「あの~ できれば 書き損じの「オトーバ」なんかを適当に、道端に立ててもらって、ついでに 本堂で なるべく怖そうなお経など唱えてくれると ありがたいんですが・・・」
・・・丁重にお断り申し上げました。
「お塔婆」とは・・・
正式には 卒塔婆(そとうば)といいます。
お釈迦様が亡くなられた後、そのお墓に 暑さや雨をしのげるようにと信者たちが つぎからつぎへと傘をさしかけました。 その数があまりにも多かったので 収拾がつかなくなり、相談の結果、大勢の人たちで立派な傘をつくり 墓に建てかけた。 それが「塔」と名づけられ 中国を経由して日本に伝わって「五重塔」に発展した・・・ 板のお塔婆は それを簡素化したもので 上の方に4つのきざみこみがあり、五重になっています(五重は お釈迦様の 身体そのもので、頭・首・胸・腹・足 を現している)。 亡くなった方は、塔婆を供養されることによって(仏様そのものを受けることによって)生前の苦しみを断ち切ることができ、そのことによって、供養する側もまた 功徳を積むことができます。
この時期、日中は お檀家さんを廻り、夜は 「お塔婆」を書くという毎日。 現時点で 申し込みが 60数本なので 1日5本をノルマとしています。 書くのは遅いし、裏表なので なかなか大変ですが これを私自身の「彼岸の修行」ととらえています。
「お塔婆」を書く。

書きあがった 「お塔婆」の一部

坊さんは 少々辛い事も すべて 修行! で 片付ければいいので 難しいことは考えなくてもイイ。 ある意味で 気楽なモンです。
ところで 「お塔婆」って ご存知ですか?
かなり前のことですが、友達の女の子との 電話での会話。
「何してんの~?」
「お塔婆、書いてんの。 ところで お塔婆って知ってる?」
「オト~バァ~ッ? あぁ~ あのお化け屋敷に 立ってるあれでしょ?」
・・・・ お化け屋敷の小道具ですか~ こちらがビックリです。(マレーシアに住んでる サクラさん! アンタのことだよッ、覚えてる?)
こんなこともありました。 夏休みのある夜 小学生が肝試しをやるので お寺の境内を使わせて欲しい、との申し入れ、もちろんOKですが・・・
「あの~ できれば 書き損じの「オトーバ」なんかを適当に、道端に立ててもらって、ついでに 本堂で なるべく怖そうなお経など唱えてくれると ありがたいんですが・・・」
・・・丁重にお断り申し上げました。
「お塔婆」とは・・・
正式には 卒塔婆(そとうば)といいます。
お釈迦様が亡くなられた後、そのお墓に 暑さや雨をしのげるようにと信者たちが つぎからつぎへと傘をさしかけました。 その数があまりにも多かったので 収拾がつかなくなり、相談の結果、大勢の人たちで立派な傘をつくり 墓に建てかけた。 それが「塔」と名づけられ 中国を経由して日本に伝わって「五重塔」に発展した・・・ 板のお塔婆は それを簡素化したもので 上の方に4つのきざみこみがあり、五重になっています(五重は お釈迦様の 身体そのもので、頭・首・胸・腹・足 を現している)。 亡くなった方は、塔婆を供養されることによって(仏様そのものを受けることによって)生前の苦しみを断ち切ることができ、そのことによって、供養する側もまた 功徳を積むことができます。
この時期、日中は お檀家さんを廻り、夜は 「お塔婆」を書くという毎日。 現時点で 申し込みが 60数本なので 1日5本をノルマとしています。 書くのは遅いし、裏表なので なかなか大変ですが これを私自身の「彼岸の修行」ととらえています。
「お塔婆」を書く。

書きあがった 「お塔婆」の一部

坊さんは 少々辛い事も すべて 修行! で 片付ければいいので 難しいことは考えなくてもイイ。 ある意味で 気楽なモンです。
Posted by kotokuji at
19:54
│Comments(0)
2010年09月08日
赤いレインスーツ
「お彼岸のお経廻り」5日目。
台風9号の影響で、朝から土砂降りの雨。 少し躊躇したけど カッパを着てバイクに跨る。 新聞配達さんや 郵便配達さんには 雨だから躊躇(ためら)うなんてコトはない。 自分は まだまだアマイ・・・
実のところ 雨の中、バイクで走るのは とっても楽しい。 寒くなければ シャワーを浴びながら走っているようなもの。 大粒の雨は、カッパの上から パチパチと素肌を叩く・・ 痛いので 速度を緩める・・・ それも又よし。
こんなシーンに合う唄はないかと あれこれ思いをめぐらすのだけど どうもピッタリの唄がない・・・
石原裕次郎 「嵐を呼ぶ男」?・・・

カッパの下は坊さんの格好、信じられないでしょうけど・・・
ところで このカッパは 通販で買ったのだけど、いつものバイク用品ショップで、「カッパ」と検索したら「この検索条件に該当する商品はありませんでした」というメッセージが返ってきて 「そんなバカな・・・?」と調べてみたら、今では 「レインスーツ」もしくは 「レインウェア」というのだそうです。
今や ズボンのことをパンツ、チョッキはベスト、ジャンパーはブルゾン、と呼ぶらしい。 時代とともに呼び名も変わる。 コーデュロイなどというから何のことかと思いきや、コール天のことだった・・・ クダラン!と思うけど 言っても仕方がないですね。 でも、この間 どこかのおばさんが 「今は スパゲッティなんて呼ばないのよ、パスタって言うの」 なんて したり顔で言ってたけど、それは違うと思います。
話は、変わって 「富士山ピースフェスティバル」 無事終了! 赤字にもならず、映画のオペレーションもバッチリで、一応、私の責任は果たす事ができて ほっとしました。
映画『地球交響曲(ガイアシンフォニー)第七番』 「霊性」というテーマを縦軸に 自発的治癒力の医学博士アンドルー・ワイル、「ツール・ド・フランス」の覇者、グレッグ・レモン、環境教育活動家、高野孝子さんが取り上げられました。 目に見えないものを見、耳に聞こえないものを聴く・・・この映画の見所かな、と思います。 私個人としては、グレッグレモンが息子と2人 日本の山岳地帯を自転車で旅するシーンが、とっても印象深く、お彼岸が 終わったら また自転車に乗ろうと思いました(ロードバイクという自転車を持っています)。


(昨日の 富士山、お経廻りの途中で・・・)
台風9号の影響で、朝から土砂降りの雨。 少し躊躇したけど カッパを着てバイクに跨る。 新聞配達さんや 郵便配達さんには 雨だから躊躇(ためら)うなんてコトはない。 自分は まだまだアマイ・・・
実のところ 雨の中、バイクで走るのは とっても楽しい。 寒くなければ シャワーを浴びながら走っているようなもの。 大粒の雨は、カッパの上から パチパチと素肌を叩く・・ 痛いので 速度を緩める・・・ それも又よし。
こんなシーンに合う唄はないかと あれこれ思いをめぐらすのだけど どうもピッタリの唄がない・・・
石原裕次郎 「嵐を呼ぶ男」?・・・

カッパの下は坊さんの格好、信じられないでしょうけど・・・
ところで このカッパは 通販で買ったのだけど、いつものバイク用品ショップで、「カッパ」と検索したら「この検索条件に該当する商品はありませんでした」というメッセージが返ってきて 「そんなバカな・・・?」と調べてみたら、今では 「レインスーツ」もしくは 「レインウェア」というのだそうです。
今や ズボンのことをパンツ、チョッキはベスト、ジャンパーはブルゾン、と呼ぶらしい。 時代とともに呼び名も変わる。 コーデュロイなどというから何のことかと思いきや、コール天のことだった・・・ クダラン!と思うけど 言っても仕方がないですね。 でも、この間 どこかのおばさんが 「今は スパゲッティなんて呼ばないのよ、パスタって言うの」 なんて したり顔で言ってたけど、それは違うと思います。
話は、変わって 「富士山ピースフェスティバル」 無事終了! 赤字にもならず、映画のオペレーションもバッチリで、一応、私の責任は果たす事ができて ほっとしました。
映画『地球交響曲(ガイアシンフォニー)第七番』 「霊性」というテーマを縦軸に 自発的治癒力の医学博士アンドルー・ワイル、「ツール・ド・フランス」の覇者、グレッグ・レモン、環境教育活動家、高野孝子さんが取り上げられました。 目に見えないものを見、耳に聞こえないものを聴く・・・この映画の見所かな、と思います。 私個人としては、グレッグレモンが息子と2人 日本の山岳地帯を自転車で旅するシーンが、とっても印象深く、お彼岸が 終わったら また自転車に乗ろうと思いました(ロードバイクという自転車を持っています)。


(昨日の 富士山、お経廻りの途中で・・・)
Posted by kotokuji at
21:15
│Comments(0)
2010年09月04日
輝ける96歳
本日 ピースフェスティバル・メインエベント初日。
朝霧高原「麓・山の家」が 会場です。 かつての「井の頭小学校・麓分校」の校舎。

標高800m。毛無山(1994m)の麓に位置します。 本来なら 今頃は さわやかな 秋の風が 吹き渡る頃なのですが ここも 猛暑・・・
16時。
このイベントのために 藤枝市に在住の 民族学者 八木洋行(やぎようこう)先生が 書き下ろした、一人芝居「口笛の草原」開演。


長野~満州~シベリア抑留~そして、この朝霧高原に移住した 老移民の半生を 石松常彦氏が 演じきりました。クーラーのない 閉め切った会場で 滴り落ちる汗は涙のごとく、鑑賞している我々も しばし暑さを忘れました。

サプライズは この芝居のモデルとなった 後藤さんが 作者の八木洋行さんとともに登場。

何と明日が 誕生日で 96歳。
「トシをとると動きが遅くなってイカン」などと言いながら、舞台に上がってこられました。
最近、車の免許も書き換えたそうで 曰く「焼酎買うのに、誰かに頼めないもんな~」

1日2食のソマツな食事でシベリアでの捕虜時代を生き抜くことができたこと、移民初期の苦しい時代を耐えられた事、「ゼイタクをしなかったから・・・」と たんたん と話されました。 なんとも おだやかな 表情と 透き通ったような 魂の輝きを感じました。
前回のブログで 「もし私が長生きしたら・・・」と書きましたが、 「もし 長生きできたら この後藤さんのように なりたい!」と思いました。
最後は、陬波靖行さんとブルースファクトリのライブ。

陬波さんのブルースハープ。
美しく どこか哀しく そしてエネルギッシュ!

「ピースフェスティバル」 明日は、映画「ガイアシンフォニー第7番」と 国際的に活躍されている バイオリニスト 河村典子さんとピアニスト 細川恵美子さんの コンサート。
私は 映画のオペレーションを担当しています。 うまくいけるかどうか 少々心配・・・
朝霧高原「麓・山の家」が 会場です。 かつての「井の頭小学校・麓分校」の校舎。

標高800m。毛無山(1994m)の麓に位置します。 本来なら 今頃は さわやかな 秋の風が 吹き渡る頃なのですが ここも 猛暑・・・
16時。
このイベントのために 藤枝市に在住の 民族学者 八木洋行(やぎようこう)先生が 書き下ろした、一人芝居「口笛の草原」開演。


長野~満州~シベリア抑留~そして、この朝霧高原に移住した 老移民の半生を 石松常彦氏が 演じきりました。クーラーのない 閉め切った会場で 滴り落ちる汗は涙のごとく、鑑賞している我々も しばし暑さを忘れました。

サプライズは この芝居のモデルとなった 後藤さんが 作者の八木洋行さんとともに登場。

何と明日が 誕生日で 96歳。
「トシをとると動きが遅くなってイカン」などと言いながら、舞台に上がってこられました。
最近、車の免許も書き換えたそうで 曰く「焼酎買うのに、誰かに頼めないもんな~」

1日2食のソマツな食事でシベリアでの捕虜時代を生き抜くことができたこと、移民初期の苦しい時代を耐えられた事、「ゼイタクをしなかったから・・・」と たんたん と話されました。 なんとも おだやかな 表情と 透き通ったような 魂の輝きを感じました。
前回のブログで 「もし私が長生きしたら・・・」と書きましたが、 「もし 長生きできたら この後藤さんのように なりたい!」と思いました。
最後は、陬波靖行さんとブルースファクトリのライブ。

陬波さんのブルースハープ。
美しく どこか哀しく そしてエネルギッシュ!

「ピースフェスティバル」 明日は、映画「ガイアシンフォニー第7番」と 国際的に活躍されている バイオリニスト 河村典子さんとピアニスト 細川恵美子さんの コンサート。
私は 映画のオペレーションを担当しています。 うまくいけるかどうか 少々心配・・・
Posted by kotokuji at
23:36
│Comments(0)
2010年09月01日
美しき99歳
『興徳寺便り89号』を発行しました。
半径5km位までの檀家さんには バイクで配達し、それ以遠の方には郵送いたしました。
このHP上の「紙上法話」と「住職のひとりごと」も 更新しましたので そちらの方も ご覧になってください。
さて「紙上法話」は 一遍の詩を紹介し それに仏教的な解釈を試みるというスタイルをとっているのですが、 よい詩との出合いは 私自身が大いに感動させられます。
詩人・柴田トヨさん、現在99歳。
90歳を過ぎて 詩を書き始め 、98歳で 処女詩集『くじけないで』を出版。 これが「勇気と元気が出る詩集」として ブームとなり、8月3日、出版流通大手「トーハン」の週間ベストセラーで総合1位。 今なお 再販を重ねているそうです。
化粧
柴田トヨ
倅が小学生の時
お前の母ちゃん
きれいだなって
友達に言われたと
うれしそうに
言ったことがあった
それから丹念に
九十七の今も
おつくりをしている
誰かに
ほめられたくて

人は ほめられる事によって さらに美しくなる。
それにしても 女の人は イイナァ~ って思う。 私が もしも99歳まで 生きていたら 何とほめられるだろう? 「よく生きてますね~」???・・・
生まれ変わったら、 今度は 女の人をやってみます。
明日より 「お彼岸のお経廻り」。 またまた 7時前に寺を出て~ というサラリーマン的毎日が始まります。
*HP、「高瀬幹雄のフォトギャラリー」も更新しました。 友人・ミキオちゃんの作品、「夏の富士山」。
いずれも、興徳寺のすぐ近くで撮ったものです。 どうぞ ご覧になってください。
半径5km位までの檀家さんには バイクで配達し、それ以遠の方には郵送いたしました。
このHP上の「紙上法話」と「住職のひとりごと」も 更新しましたので そちらの方も ご覧になってください。
さて「紙上法話」は 一遍の詩を紹介し それに仏教的な解釈を試みるというスタイルをとっているのですが、 よい詩との出合いは 私自身が大いに感動させられます。
詩人・柴田トヨさん、現在99歳。
90歳を過ぎて 詩を書き始め 、98歳で 処女詩集『くじけないで』を出版。 これが「勇気と元気が出る詩集」として ブームとなり、8月3日、出版流通大手「トーハン」の週間ベストセラーで総合1位。 今なお 再販を重ねているそうです。
化粧
柴田トヨ
倅が小学生の時
お前の母ちゃん
きれいだなって
友達に言われたと
うれしそうに
言ったことがあった
それから丹念に
九十七の今も
おつくりをしている
誰かに
ほめられたくて

人は ほめられる事によって さらに美しくなる。
それにしても 女の人は イイナァ~ って思う。 私が もしも99歳まで 生きていたら 何とほめられるだろう? 「よく生きてますね~」???・・・
生まれ変わったら、 今度は 女の人をやってみます。
明日より 「お彼岸のお経廻り」。 またまた 7時前に寺を出て~ というサラリーマン的毎日が始まります。
*HP、「高瀬幹雄のフォトギャラリー」も更新しました。 友人・ミキオちゃんの作品、「夏の富士山」。
いずれも、興徳寺のすぐ近くで撮ったものです。 どうぞ ご覧になってください。
Posted by kotokuji at
19:29
│Comments(0)